vol.57
広島から世界へ。止まらないマツダとマルニ木工の躍進
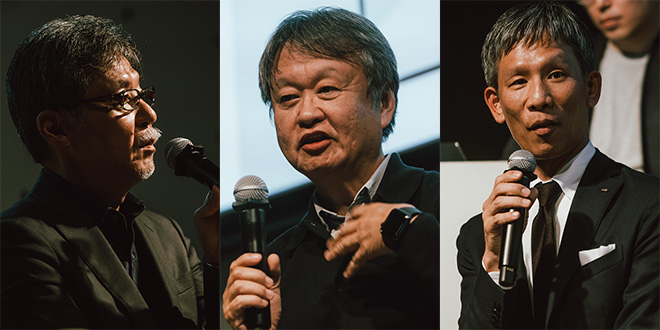
Text by Sotaro Yamada
Photographs by Taio Konishi
日本の美意識と感性を再考しデザインすることで、世界でプレミアムブランドとしての地位を確立したふたつの企業があります。ひとつは、「魂動(KODO)」デザインという揺るぎないフィロソフィーを持ち、国内外から高い評価を得ているマツダ。カリフォルニアにあるアップル社の社屋「アップル・パーク」に数千脚の「HIROSHIMA」アームチェアが納品され話題を呼んだマルニ木工。両社ともに広島という地に誕生し、創業から現在まで世界へと発信を続けてきました。
これらふたつの企業の成功の裏には「デザイン」、そしてデザインを支える優れた「ディレクション」という共通点があります。今回は、世界レベルに押し上げた両社のキーパーソンであるマツダの前田育男さん、マルニ木工のアートディレクターであり、プロダクトデザイナーの深澤直人さんと代表の山中武さんをお招きして、両社が考える「日本のデザイン」と「日本人のクラフトマンシップ」について語っていただきました。
タジリケイスケ(「H」編集長/以下、タジリ):本日の「H(エイチ)」は、日本の“いま”のプレミアムを発信している弊社メディア「プレミアムジャパン」による企画です。「プレミアムジャパン」編集長の藤野とゲストの3名に、「日本の感性と美意識」をテーマにクロストークを展開していただきたいと思います。まずは、山中さんと前田さんより自社の紹介をお願いします。
山中 武(株式会社マルニ木工代表取締役社長/以下、山中):今日はこのような機会をいただきありがとうございます。早速、マルニ木工について説明させていただきます。マルニ木工は約10年前に深澤直人さんをアートディレクターとしてお招きし、デザインを一新させて以降、当社をめぐる環境は大きく変わりつつあります。代表的な例が、
カリフォルニア州のアップル本社にあるアップル・パークです。ここにある椅子は、すべて弊社でつくらせていただきました。
創業は昭和3年(1928年)で、2019年の5月22日に91周年を迎えました。創業者の山中武夫は私の祖父の兄に当たります。彼は木工業が非常に盛んな広島県宮島の出身で、幼いころから木の魅力に取りつかれ、製造業を志すようになりました。創業以来のモットーは、工芸的な美しさを残しながら機械化を徹底的に進める「工芸の工業化」です。それにより、床と畳しかなかった日本の住宅文化のレベルが上がっていくという確信がありました。
簡単な曲木椅子の量産からスタートし、戦後は日本の復興とともにじわじわと成長してきました。1960年代には猫脚を中心とした複雑なクラシックスタイルの家具の量産に成功し、1980年代には自他ともに認める唯一無二の家具メーカーに成長しましたが、バブル経済崩壊後は非常に厳しい時代を過ごしました。
もともと勤めていた銀行を退職し、マルニ木工へ入社した2001年ごろは何をやってもうまくいかず、「マルニ木工の強みは何なんだろう」とずっと悩んでいました。そんなときに、深澤直人さんとの素晴らしい出会いがあったんです。
2004年、当社の工場に深澤さんとプロダクトデザイナーのジャスパー・モリソンさんに来ていただく機会がありました。その数日後、深澤さんからいただいたメールに「せっかく優れた木工加工技術があるのに、最後にベトベト塗装するのは木のよさを殺しているようでとても残念です」という言葉がありました。トップデザイナーの方から技術面をお褒めいただけ、ようやくマルニ木工の技術に自信が持てましたが、デザイン面の課題を強く感じました。
そこで、技術が評価されているのなら、デザインが変われば会社自体も大きく変わる可能性があるんじゃないかという考えに至り、2006年の冬、深澤さんにデザインを依頼しに行きました。そのとき、深澤さんに「世界の定番をつくろうよ」と言われたんです。われわれのような田舎の中小企業にそんなことができるんだろうかと半信半疑でしたが、言われた直後はすごくドキドキして、事務所を出た瞬間に身体が震えたのを思い出します。
マルニ木工の特徴は、試作職人がつくった美しい試作品を機械加工すべく、5軸のCNC(数値制御)機械をプログラミングする職人がいることです。人間の手のように自由に動く機械を使い、職人が1日かけてつくるものを機械だと20分でつくれるようになりました。そして、最後に職人が一脚一脚丁寧に仕上げます。2008年には「MARUNI COLLECTION 2008 BY NAOTO FUKASAWA」として「HIROSHIMA」という名前の椅子とテーブルを発表しました。

こちらは2019年のミラノサローネの様子です。「HIROSHIMA」を発表した翌年の2009年から毎年、世界最大の家具・インテリアの見本市であるミラノサローネに出展しています。最初は経済産業省のジャパンブースの隅で発表していましたが、2019年はトップブランドしか出展が許されない選抜ホールに、日本から唯一選ばれました。このサローネを通じて世界のさまざまなパートナーとのご縁ができ、世界トップの建築家であるデイヴィッド・チッパーフィールドさんのベルリンオフィスやブルーボトルコーヒーのビバリーヒルズ店、イギリスのテートモダン新館や、冒頭にご紹介したアップル・パークなど、さまざまなところに当社の家具を入れていただいております。

マルニ木工は、100年たっても「世界の定番」として認められる木工家具をつくり続けるというビジョンを掲げています。マツダさんをはじめ、日本のいろんなメーカーが世界でブランドを確立させていますが、家具でそれを成し得た会社は、いまのところ一社もありません。それを当社のような広島の田舎の中小企業が実現させることができたら格好いいと思っています。

こちらが工場の全景です。人間より動物の方が圧倒的に多い田舎ですが、2028年のマルニ木工100歳の誕生日までには、木工を志す世界中の人たちが一度は行きたいと思えるような場所にしたいと思っています。
タジリ:ありがとうございます。家具の魅力についてはこの後、深澤さんを交えてお話できればと思います。続いて、前田さんのプレゼンテーションです。
前田育男(マツダ株式会社常務執行役員デザイン・ブランドスタイル担当/以下、前田):マツダの前田です。2009年にマツダのデザインをリードする立場になり、「魂動(KODO)デザイン」というテーマと「CAR AS ART」というスローガンを掲げています。これらは、車をアートのような美しいものにしたいという想いのもと決めました。現在は本当の「美」を追求したものがつくりにくい時代なので、「アート」と言い切るくらいの覚悟がないとモノの形も美しくならないと思います。

そういう意味で本日、深澤さんと山中さんとお話できることをとても楽しみにしていました。というのも、おふたりが発せられている「世界の定番をつくっていく」というメッセージは、われわれが目指しているものと同じだからです。奇をてらったものでなく、美しい定番をつくっていく。そこは重なる部分だと感じています。

タジリ:前田さんありがとうございます。ではここから、「プレミアムジャパン」編集長の藤野を迎え、クロストークに移っていきたいと思います。
藤野淑恵(「プレミアムジャパン」編集長/以下、藤野):本日は皆さんにたっぷりお話していただきたく、3つのテーマを掲げさせていただきました。1つ目のテーマは「un-veil(アンヴェール)」です。前田さんが2018年に出版された本『デザインが日本を変える~日本人の美意識を取り戻す~』(光文社新書)の冒頭にこの言葉が出てきます。「アンヴェールする」という言葉は、自動車業界では頻繁に使われるそうですね。
前田:新車発表会やコンセプトカーをお披露目する際に、モデルにかけている黒いヴェールを取って皆さんにお披露目するときに使う言葉です。なので「アンヴェール」と聞くとわれわれは緊張しますね。自分の子どものように2、3年間ずっと手塩にかけて育てた車が日の目を見る、もっとも緊張感漂う瞬間です。
藤野:本書には、前田さんがデザイン本部長になって初めてつくられた車がアンヴェールされたときのストーリーも描かれています。当時の緊張感が伝わってきて、ドキドキしながら読んだことを覚えています。深澤さんにお伺いしたいのですが、プロダクトデザインの世界でも「アンヴェール」という言葉を使うのでしょうか?
深澤直人(株式会社マルニ木工アートディレクター/以下、深澤):「アンヴェール」とは「姿を表す・登場する」という意味だと思います。登場するのは「形」ではなく「姿」。「姿」という言葉のなかには、その「周り」も含まれているんです。「形」を囲んでいるすべてのなかにあるものが「姿」。だから「アンヴェール」という言葉には、デザイナーとして形をつくってはいるけれども、見えなかった姿をそこに登場させるという感覚があります。どんな姿がいいかを考えて形をつくらないと、単に形だけになってしまい、周りとマッチしなくなってしまう。
藤野:なるほど。前田さんは現在の立場になられた1年後に、イタリアのミラノで初めての「アンヴェール」を行っていますね。マルニ木工は先ほどの山中社長のプレゼンテーションにもあったように、深澤さんと協働を始められた次の年にミラノサローネに出展されたというお話がありました。ミラノというのはやはり、デザインの世界でも特別なのでしょうか。

山中:ミラノサローネは、世界最大の家具見本市です。ミラノ市の人口は約130万人ですが、ミラノサローネの会期中は世界中から約40万人が来場します。メーカーもこのサローネにあわせて新商品を開発しますし、メディアもたくさん集まります。そういう場所でお披露目することが一番発信力が強いと考え、私たちも毎年出展しています。
藤野:前田さんは、ミラノサローネに合わせて開催されるミラノデザインウィークに出展されたことはありますか?
前田:2回出展しています。ミラノデザインウィークはもともと芸術祭のようなものなので、単に車を展示するのではなく、アート作品のようなものと車とをフュージョンさせて展示しました。独特な空間でしたが、ミラネーゼの方々には高い評価をいただきました。
藤野:深澤さんは、マルニ木工で初めてデザインされた家具がお披露目されたときのことを覚えていらっしゃいますか?
深澤:覚えています。椅子のデザインは最初に失敗してしまうとその人のデザイナー生命が絶たれることになりかねないので、かなりの覚悟をもってやらなくてはいけません。特に木製の椅子は製作が難しいうえに好まれる素材ですから、一生モノとして購入する人が多いんです。偉大な先輩たちの多くは、ひとつの木製家具メーカーとタッグを組み、アイコンとなる家具を残してきました。自分もそのような仕事を一生かけてやってみたいという想いがあったんです。どうせやるなら、最初は一番難しくて失敗できないものをつくりたい、と。
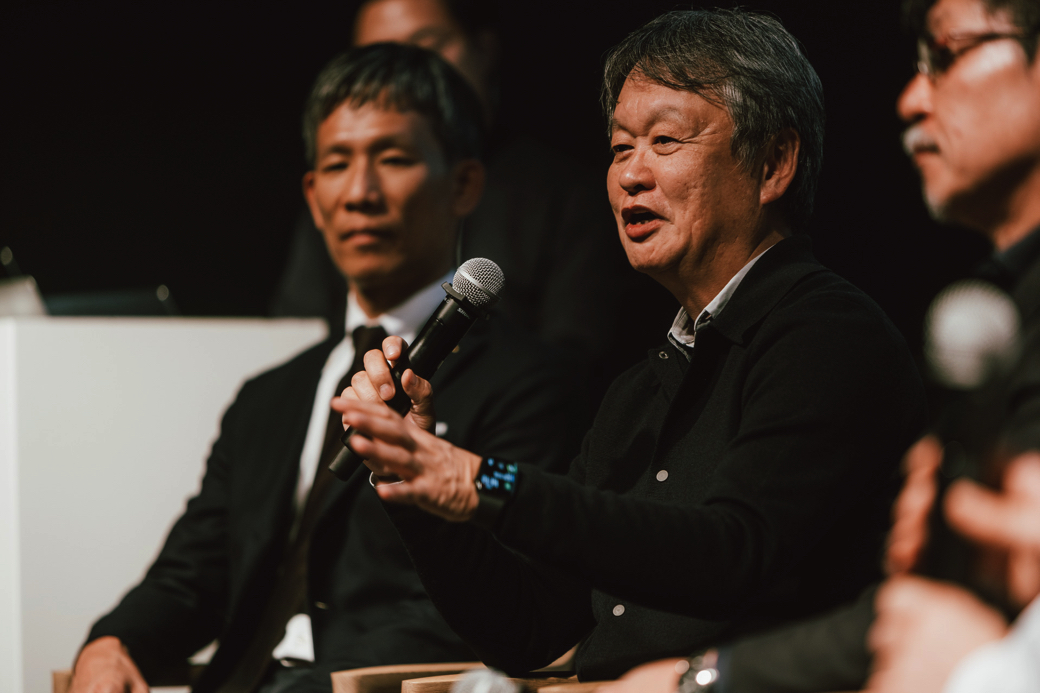
藤野:ちなみに、本日私たちが座っている椅子が、まさに「HIROSHIMA」のアームチェアとテーブルです。前田さん、いかがですか?
前田:いい意味で、存在感を忘れるくらいフィットします。硬い素材なのに全然硬い印象がない。何より、綺麗ですね。


藤野:また、本日お三方にはこちらの会場まで「MAZDA 3」で移動していただきました。深澤さんには15分ほどドライブをしていただきましたが、乗り心地はいかがでしたか。
深澤:スポーティーな車はアグレッシブにつくられがちですが、ある程度謙虚にバランスのあるデザインや機能にしないと、乗る人に嫌がられてしまう。そういう意味で違和感がまったくありませんでした。造形に破綻がありませんし、内装のクオリティもすごくよかったです。アクを感じさせないのに非常に力強く、それでいて静か。バランスが取れていると感じました。

前田:「違和感がない」というのは最大の褒め言葉ですね。われわれは「引き算」と言っていますが、要素を引いてシンプルにしながら、違和感のあるところを排していくことを目指しています。ただ、下手をすると個性も特徴も、味わい深さもないものになってしまうこともあるので、そうならないよう、絶対に訴えなければいけない部分は研ぎ澄ませ、そこが浮き彫りになるほど周りを削ぎ落としていく。その作業の積み重ねによって「MAZDA 3」にたどり着きました。
藤野:「研ぎ澄ます」という言葉は、今日のふたつ目のテーマ「日本的」にもつながる気がします。深澤さんも「研ぎ澄ます」という代名詞が付くデザインをたくさん手掛けておられますが、深澤さんの考える「日本的」とは何でしょう?
深澤:海外で仕事をしていると日本をどのように表すかをよく聞かれますが、そのたびに「きちっとしている」と答えています。日本は良いも悪いも、誰が教えたわけでもないのにすべてが隅々までちゃんとしているんです。海外と日本のメーカーを比べると、きちっとしているレベルの単位がゼロ1つ分くらい違う。たとえば、サーフェイス(表面)がスムースで、若干テクスチャーがありながらピカピカになるのはなぜなのかを、マルニ木工の職人さんたちに聞いても明かしてくれない。隠しているというよりむしろ、表現しているつもりはないのに、無意識にそうつくってしまっているところがあるのかもしれません。
藤野:あえてそうしようと思っていないけれども、そうなっている?
深澤:海外のものと比べると精緻さや触り心地がまったく違うんですが、職人さんたちはそれを特別褒められるに値すると感じておらず、当たり前のことのように思っている。それが日本という国を成している暗黙の合意のようなものだと感じていますし、これこそが日本らしさだと思います。統制を取るのでなく、自分が参画していることに対して「ちゃんと」それをしようという概念のなかで働いているということです。
藤野:なるほど。以前、マルニ木工さんのイベントで山中社長が「アームチェアの木目をそろえてくれと言わなくても、左右きれいにそろったものを職人が仕上げてくれる」とおっしゃっていました。
山中:そうですね。でもそのことは、深澤さんに言われるまで気付きませんでした。たしかにうちの工場の職人たちは、日本人の心に刻み込まれている「甲斐性」というものを持っていると思います。
藤野:前田さんの『デザインが日本を変える』という本にも「マツダには『変態』とでも形容すべき匠がいる」と書かれており、いまの話と共通点があると思ったのですが。
前田:大変共感しますね。われわれも「きちんとつくる」のさらにうえの「精密につくる」ということに力を入れています。車のデザインは工業用粘土で形をつくって造形を決めていくんですが、なかなか簡単にはつくれません。通常の粘土は、40度くらいに温めると柔らかくなりますが、うちでは55度まで温めないと柔らかくならない、業界一硬い粘土を使用しています。あえて削りにくい硬い粘土を削ることで、精密な形に仕上げていく。マツダ車のような繊細なリフレクションをつくることは一筋縄ではいかず、相当細かなチューニングを重ねてつくらなければならない。それくらい、精緻であるということに気を遣っています。
もうひとつ、海外のデザイナーと話をすると「何をやったらこうなるのかわからない」と言われるんです。特に、ドイツ人にとってはまったくない文脈らしく、「こんなに手間をかけてフォルムをつくっていく行為自体が理解できない。なぜ1点でバシッとつくってしまわないのか」と。そこが先ほどおふたりが言われていたような日本らしさ、日本のものづくりらしさだと思っています。

藤野:家具といえば北欧を思い出しますが、北欧の家具に精緻さは当てはまるのでしょうか。
山中:北欧でも、とても素晴らしい家具がつくられています。ついこのあいだも深澤さんと一緒に北欧のある工房に行ってきたんですが、そこでは、ノスタルジーな感性が駆り立てられたり、一人ひとりの職人技が生きていたりしてすごく素敵だと感じた一方、「うちだったらもっと細かくきちっとやるだろうな」と思う面もありました。どちらがよいというわけではないのですが、つくり方の文化の違いは感じました。
藤野:「マルニ木工の家具は日本的だ」という感想をいただくことはありますか?
山中:そう言われることももちろんありますが、「日本的」を求めてものづくりをしている感覚はあまりないかもしれません。たとえば、漆を塗って西陣織のファブリックを張ればいわゆる「日本的」になるかもしれませんが、それをやりたいとは思っていません。深澤さんとわれわれが全力でつくったものが社会に出て、結果的にお客さまから「やっぱり日本人はいいものをつくるね」と言われることが一番気持ちいいと思っています。
藤野:マツダ車の「日本的」とはどういうことでしょうか?
前田:先ほどの話にも通じますが、あるひとつの目標に対して、どこまで丁寧に精密につくり上げられるかだと思います。「人馬一体」という哲学のもと、人と馬のように人間と車が親密な関係となれるよう形に命を与えていますが、車は鉄の箱なので実際はいくら走らせても形が変化することはない。ですが、街中や自然の中を走ったときに、生き物が動いているような見せ方をすることはできるのではないかと考えたんです。
そこから光に着目し、光の動きから生命を感じてもらえればと考え、われわれは「光の移ろい」をテーマにしました。刻々と変わっていく光の位置や周りの環境に対してどれだけ車のボディが反応できるか。それには、非常に精密な光のコントロールが必要になってきます。そのときに必要とされる精緻さが「日本的」なのではないかと考えています。

藤野:3つ目のテーマは「工芸と工業」です。マルニ木工さんが「工芸の工業化」を創業時からテーマとして掲げられていることと、マツダさんも工業を工芸的な視点で考えられていらっしゃるところが興味深く、両方の視点からお話を伺いたいと思います。まずは山中さん、「工芸の工業化」というのは創業者の言葉で、ずっと語り継がれていらっしゃるものなのでしょうか。
山中:先ほどのプレゼンのとおり、当時の日本の住宅には床と畳しかありませんでした。家具は権威の象徴であり、非常に高価なものだったんですね。マルニ木工創業の約60年前に、ドイツのトーネット社が初めて椅子の量産に成功して、ヨーロッパの人々はダイニングでご飯を食べてリビングでくつろぐという生活になりました。創業者は、そんな生活に憧れたんだと思います。それを成し遂げようと思ったら、一脚一脚職人がつくっていたのでは間に合わず、お客さまに行き届かない。そこで彼は独学でドイツ語を学び、ドイツの家具づくりを学びました。
昔はそうした想いが引き継がれていましたが、バブル時代に薄れ、ものづくりの努力よりも販売やマーケティング努力ばかりになってしまった。そんな時期に銀行員を経て入社した私は、ものづくりもデザインも知らず、当時は木にも興味が持てませんでした。でも「工芸の工業化」という言葉は当時から刺さっていたんです。
藤野:「HIROSHIMA」のアームチェアは、当初よりも生産数が増えていると伺いました。
山中:職人たちは最初「月に40脚以上はつくれません」と言っていました。しかしアップル・パークのような数千脚という案件が来るようになり、いまでは多いときで月に700〜800脚つくっています。たしかに手のかかるものづくりですが、そこはまさに工業化のプロがいて、CNC機のプログラミングもいまはver.67という数字になっています。

藤野:前田さんのお仕事のなかには「工業の工芸化」的な側面があると思うのですが、いかがでしょう。
前田:なかなか難しいです。われわれの場合、年間160万台つくって全世界に展開しているので、工業といってもほぼ重工業に近い。1台つくるのに約300億円の投資が必要になる重たいプロダクトなので、工芸にはなりきれないという気持ちが正直あります。
企業の命題は効率化ですよね。いかに効率よくつくり、投資を減らして利益を増やすか。これはどんな企業でも同じです。ただその一方で、短期的で効率的なものづくりをしていると、失うものがたくさんあるとも感じています。われわれはよく、デザイナーや生産技術エンジニアに「正解を求めてはいない」と伝えます。正解は1か0で割り切れるクリーンなものだけれど、人間の手でつくった場合、そこまで割り切れるものではなく、もっとファジーで中間的なものがたくさんでき上がる。それを整理して1と0に置き換えないでほしいと言っています。
車は鉄をプレスして形をつくっていきますが、最後に手で仕上げるようにしています。それはすごくリスキーな作業で、ここでひとつ間違えば莫大な損害が出てしまう。何が違うのかと聞かれたら何も違わないかもしれないし、単なる気持ちの問題かもしれない。しかしそういったところが、われわれができる最大の工芸化だと思っています。
藤野:深澤さん、前田さんの話に深くうなずいていらっしゃいましたね。マルニ木工の椅子も最後に手仕事が入るわけですが、工芸のキーワードとして「手仕事」についてはいかがでしょうか。

深澤:たとえばこの椅子は「Roundish」というんですが、背の手前のカーブを縫いこんでいくとき、普通は餃子のようなシワが寄りますが、マルニ木工はシワができないようにしています。一方でイタリア人の場合は、そのシワをシワのままにする。シワも格好よく見せるんですね。両方ともすごい技術ですしどちらがいいということでなく、こういうところに人間性が表れるというか。「人間性によって生まれる形」が工芸なのだと思います。それは工業製品にも当てはまることで、工芸と工業、両方が有しているものだとも思います。
藤野:今回は業界トップのお三方を迎え、日本的であるとはどういうことか、また工芸と工業のバランスについて貴重なお話を聞くことができました。前田さん、深澤さん、山中さん、本日はありがとうございました。
トークセッションを共同企画した「プレミアムジャパン」による、マツダ・前田さんの「美意識」のDNAを追求した連載『MAZDA~デザインで世界を変える』でも今回の鼎談が掲載中です!
「MAZDA~デザインで世界を変える(特別編) MAZDA×マルニ木工 広島から世界へ発信する日本デザインのプレミアム」
![]()