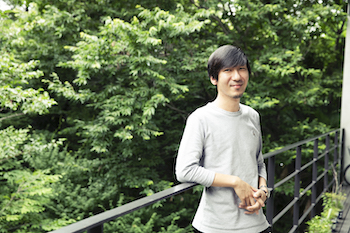
享保元年の創業から300年。日本の工芸の栄枯盛衰の中、数々の改革を経て、大木がその根をじっくりと伸ばすように独自のブランドを磨き続けた企業がある。
奈良県に暖簾を掲げ、日本の工芸をベースにした生活雑貨を企画製造・販売する「中川政七商店」だ。
全国に50以上の直営店を展開する同社は、自社製品の企画製造・販売だけでなく、長年の経験から培った「ブランディング」に関するノウハウを元にコンサルティングや教育事業も実施。「日本の工芸を元気にする!」というビジョンのもと工芸産地の活性事業にも取り組むなど、その活動は多岐に渡る。
売上は、2019年2月期に62億6千万円を記録し、名実ともに日本の工芸業界を代表する企業の一つとなった。その背景には、中川政七商店に惚れ込んだ、熱狂的なファンの存在がある。事実、同社の目玉商品である「花ふきん」は、再購入率が80%に上るなど、リピーターが多い。
バブルの崩壊以来、「工芸品が売れない」と嘆かれて久しい日本で、中川政七商店はどのように熱量の高いファンコミュニティを生み出したのか? 同社の取締役であり、コミュニケーション本部 本部長を務める緒方恵氏に話を伺った。

中川政七商店が、ここまでブランドの知名度を上げ、ファンの心を掴んだ理由——その原点は、確固たるビジョンを定めたことだった。
創業当初は明確なビジョンを持っていなかった同社も、2007年に「日本の工芸を元気にする!」というビジョンを新たに打ち出したことが、唯一無二のブランド、そして熱狂的なファンコミュニティを生み出すための大きな一歩になった。
緒方さん:「私たちのビジョンには、2つの意味があります。一つは、工芸業界の利益や流通金額をアップすること。日本の職人が高給で働けるよう、流通金額の増加を狙っています。二つ目は、職人が自分たちの仕事に誇りを持てる環境を作り出すこと。結局、私たちのビジネスは作り手ありきなので、ビジネスと職人の成長バランスを取りながら、どちらも倒れないギリギリを攻めながらグロースしていく必要があるんですよね。だから、私たちは自社製品の企画製造・販売だけでなく、工芸業界の教育や育成にも力を入れているんです。中川政七商店を元気にするのではなく、日本の工芸を元気にする。自社だけでなく、日本の工芸業界そのものが元気になって初めて私たちのビジョンは達成されます」
ビジョンを定めた2007年以降、それまで横ばいだった売上高は10年で3倍以上に増えた。直営店舗数は14店舗から50店舗近くまで増加。2年後には日本の工芸事業者に向けた「経営コンサルティング」、4年後には流通プラットフォーム「大日本市」を開くなど、驚異的なスピードで工芸業界を席巻した。

だが、ビジョンを立てたからと言って、すぐにファンが増えるわけではない。一人ひとりの顧客とコミュニケーションをする中で、ビジョンの背景にある思いやストーリーに共感してもらうことが、根強いファンを生み、熱量の高いコミュニティを作るには欠かせない。
緒方氏は、この文脈における「ブランディング」の重要性を指摘する上で、その定義を見つめ直す。
緒方さん:「『ブランディング』は、お客様の頭の中にあるぼんやりとしたブランドイメージの解像度を上げてもらうために、ブランドの世界観を統一し、その中で相手とコミュニケーションをし続けることだと考えています。例えば、初回は『ちょっとオシャレな生活雑貨店』という抽象的なイメージからお店に入り、たまたまそこで購入したふきんがすごく良かったとする。すると、お客様の頭の中でブランドイメージは『質の良いふきんを売っている、ちょっとオシャレな生活雑貨店』にアップデートされる。もう一度、同じふきんを買いに行こうと再来店し、店員に勧められて他の商品を購入した後に『ふきん以外にも素敵な商品があるんだ』と思ってもらえたら、ブランドの信頼度はさらにアップしますよね。この信頼度をアップデートし続けることが、ブランドを磨くことにもつながるんです」
例えば、中川政七商店の商品を初めて手に取る顧客に、いきなり「日本の工芸を元気にする!」というビジョンを訴えても響くものは少ない。ブランディングで築かれた信頼関係があって初めて、顧客はブランドが発信するメッセージを受け入れ、ビジョンに共感することができる。
緒方さん:「私たちはセレクトショップではなく、自分たちで作ったものを販売しているので、商品一つひとつのこだわりについて、お客様にお話しできることがたくさんあります。ただ、誰彼構わずにその話を聞いてもらえるわけではありません。快適な店舗空間やスタッフの真摯な接客、製品のクオリティ、工芸品へのこだわり、ものづくりに対する思い……といった総合体験があって初めて、お客様にブランドの価値を受け入れてもらえる扉が開く。そこでやっと、私たちはストーリーテリングができるんです」
時間や場所を選ばずにネットで買い物ができる現代では、「モノ」の良さだけを求めても顧客の心を開くことはできない。モノが手に入るまでの過程において、接客や店舗の雰囲気など、「コト」の面までこだわることで、熱狂的なファンは生まれる。「モノ」と「コト」を連動させ、ブランド全体の統一感を図ることは、コミュニティを作る上でも重要なのだろう。

では、全体の統一感を重視しながら、「モノ」と「コト」の両軸でブランドを磨くには、具体的にどうすればいいのだろうか? 中川政七商店の実践から、そのヒントを探りたい。
創業から300年近く、商品を作って卸す「メーカー卸」だった中川政七商店は、工芸業界で初めて製造から販売までを一貫して自社で行う「製造小売(SPA)」の業態を確立した。この背景には、「老舗ブランド」の看板に甘んじない、同社の「モノ」に対するこだわりが光る。
緒方さん:「取引先が問屋に限定される状況下で、ユーザーがうちの製品を使ってどういう体験をしているのか、うちの製品がユーザーからどんな評価を受けているのかが分かりづらかったんです。お客様からの声を直接取りに行き、自分たちでビジネスを作る、この2つの軸を突き詰めていった末に『SPA』の業態に辿りつきました。自分たちで作った商品を、自分たちの空間とコミュニケーションで直接お客様に届けることで、ブランドを磨き続けています。」
「コト」の面でも、中川政七商店は細心の注意を払う。なかでも、店舗接客は、お店によって体験の差が生まれないようにスタッフに共有する「言葉」に工夫を凝らしている。
緒方さん:「第一前提として、みんなが少しでも疑問に思う単語は使わず、全体共有する言葉の定義は全員で握るようにしています。言葉に対する認識がズレると、それを元にした行動にもズレが生じてしまうからです。例えば、「接客」という単語一つ取っても、店舗スタッフに『“接客”を頑張ろう!』と伝えたところで、Aさんはとにかく商品を売ることに専念するかもしれないし、Bさんは自分が好きな鯖江の漆器の話を伝えようと注力するかもしれない。一方、Cさんはお客様のステータスをヒアリングして適切なコンサルティングセールスをしようと務めるかもしれない。スタッフ全体の方向性がブレないためにも、私たちは『接客』を『接心好感』という言葉に置き換えたんです。『お客様の心に接して好感を得る店舗活動をしましょう』と。こうすることで、全スタッフの方向性はバシッと決まります。少なくとも、売りに走る行為は、この言葉からは生まれません」
自社で独自の「言葉」を行動規範に掲げ、その全体認識をすり合わせることが、中川政七商店らしい店舗体験を形作る。その過程でブランドは磨かれ、多くのファンの心を魅了するのだろう。
中川政七商店のビジョンの元にファンコミュニティが生まれた背景には、ブランディングの徹底した考え方と戦略があった。老舗企業としての自負は持ちつつ、それに甘んじてブランドの価値を上げるための努力を惜しむことはない。その姿勢があるからこそ、多くのファンは感嘆の声を漏らし、熱量の高いコミュニティは生まれたのではないか。
また、中川政七商店のブランド軸にあるビジョン「日本の工芸を元気にする!」に共感し集まったのは顧客だけではなかった。同社が抱える“もう一つのコミュニティ”についても言及し、そこから見えてきた「コミュニティが上手く機能する」条件についても迫る。
後編はこちら