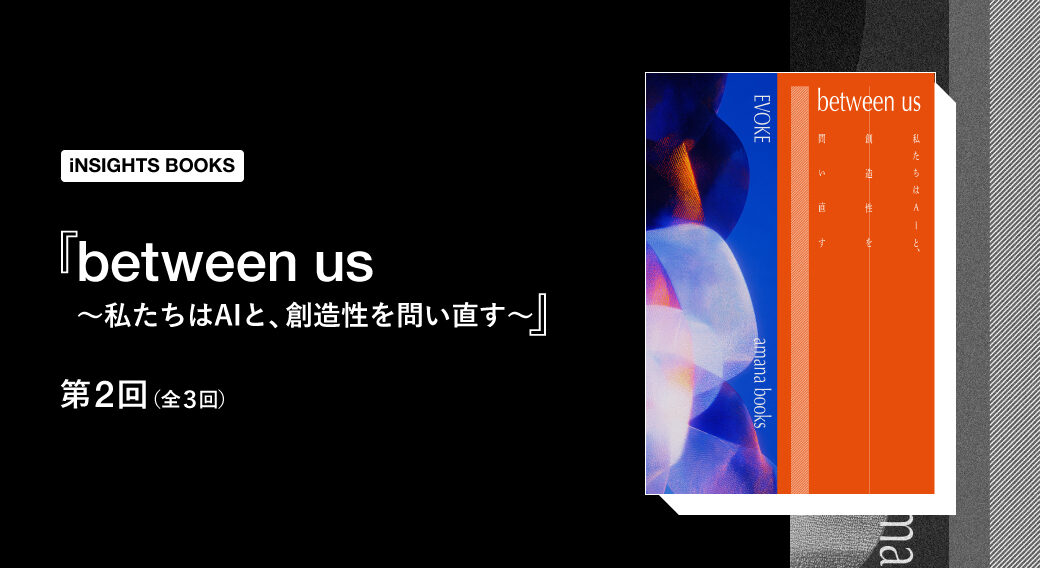
本記事は企業の広告・ブランド担当者に役立つ本から、気になる一節を数回に分けてご紹介する連載です。
読みながら、その本の“考え方”に少しずつ触れていただけます。
AIから期待したアウトプットが得られない場合、原因は日本語と英語における「文化や価値観の違い」が伝わっていないからかもしれません。英語圏で開発されたAIを使いこなすための、プロンプト設計のヒントとなる例を紹介します。
~本コンテンツは、書籍『between us〜 私たちはAIと、創造性を問い直す』(アマナの社内クリエイティブチーム「EVOKE」著)に掲載されている、生成AIと共創する現場で活躍するイメージディレクター/プロンプトアーキテクト、コンスタンス・リカによるコラム記事を一部抜粋・編集したものです(この記事は第2回/全3回)。
プロンプトエンジニアリングにおいて、私が日々意識しているのは「翻訳者としての感覚」です。ここで言う翻訳とは、単なる言語の変換ではありません。文化的背景、価値観、社会的文脈、さらには感情や空気感までをも含んだ、より包括的な「意味の変換」を指します。 AIの多くは英語圏のデータを中心にトレーニングされており、その背後にある文化や価値観が出力に影響を与えています。
つまり、日本語でプロンプトを書くとき、言葉そのものの意味は通じていても、共有されていない前提のズレによって、期待するような応答が返ってこないということが少なくありません。 日本語は“ハイコンテクスト”な言語であり、「余白」「余裕」「間」といった日本語特有の概念は、英語では一対一で対応する言葉が存在しません。これらは単なる時間や空間の話ではなく、「そこに流れる感覚」まで含んでいるのです。
こうした言葉をAIに伝えるためには、翻訳を補うような具体的な描写、感覚的な表現、あるいは比喩の挿入が必要になります。
もうひとつの例が「椅子」です。日本語では「椅子」という一語で、ダイニングチェアも、ソファも、ベンチも、スツールも指します。文脈に依存しながら、意味を“察する”文化です。一方、英語では armchair, sofa, bench, stoolといったように、用途や形状に応じて言葉が明確に分かれています。言語構造としても、英語は出来事や対象を細かく区別する傾向があり、文法的に明示的な表現が多い。
日本語では「椅子」の一言で表現できる対象は幅広いが、英語では用途や形状によって言葉を使い分けている。
日本語が「文脈から意味をにじませる言語」だとすれば、英語は「明示によって意味を切り出す言語」なのかもしれません。
この違いは、AIにおける出力の傾向にも表れます。英語圏で訓練されたモデルは、「似ているが異なるもの」を区別しようとする志向が強く、「意味の細分化(semantic granularity)」が前提となっている。たとえば「椅子」とだけ書いた場合、AIはその語が何を指しているのかを推測するしかありません。その推測は、学習時に取り込まれた英語圏の文脈や分類の枠組みに依存することになります。
だからこそ、私はプロンプトを書くとき、自分を翻訳者と同時に「文化間通訳者」として捉えています。単語を変換するだけでなく、その背後にある世界の切り取り方や価値の置き方ごと理解し直すこと──それが、異なる文化的前提を持つAIとの対話において、意図を正確に伝えるための鍵になるのです。
私がプロンプトを書く際、まずその言葉がAIにどう解釈され得るかをシミュレーションします。「この言葉は英語圏でどう翻訳されるだろうか」「このニュアンスは、AIの知識体系の中でどのように表現可能だろうか」という問いを立てながら、言葉を精緻に整えていくのです。
そして、もうひとつ大切なのは「共感の設計」です。共感とは、単に相手の気持ちを理解することではなく、「どんな前提に立っているのか」「どんな制約の中で動いているのか」を理解しようとする姿勢のこと。
AIは万能ではありません。特定の文脈や言語構造に強く、他方では大きく誤解してしまうこともある。そうした特性を理解した上でプロンプトを設計することが、いいアウトプットを引き出すための基本なのです。
(この記事は第2回/全3回)
▼書籍紹介
アマナの社内クリエイティブチームEVOKEが、生成AIとの実践と対話を通じて創造性を問い直した書籍『between us ~私たちはAIと、創造性を問い直す~』を刊行。創造の現場から生まれた実践知と多様な視点が交差する一冊です。
▼書籍情報
書名:between us 私たちはAIと、創造性を問い直す
著者:EVOKE(アマナ)
出版社:アマナ
発売日:2025年7月7日
Amazonリンク:https://www.amazon.co.jp/dp/B0FFSGFZBK
関連記事
プロンプト時代の言葉と創造性 〜EVOKE書籍出版イベント ゲストセッションレポート
「誰でも使える」時代のその先へ。Creative with AIで「自分たちらしさ」の文化を創る
AIと共進化するデザインの未来|人間の創造性が持つ唯一無二の価値とは
EVOKE制作事例記事
アサヒグループジャパン|企画段階の新商品の世界観をPoCで可視化
AQI|10年後の未来を可視化する「未来シナリオ」
生成AIとクリエイターの共存:プロ向けマインドセット【日光メープルシロップ制作事例】
人気のダウンロードコンテンツ
ブランド表現を強化する生成AI活用術:事例&実践ガイド[FREE DOWNLOAD]
文・編集:桑原勲
![]()

EVOKE
EVOKE
CO-CREATING FUTURES.
amana inc.のクリエイティブチームEVOKE。
クリエイティブコラボレーションを通じて、目指す未来を描き出す。
最近は、AIを活用したクリエイティビティの拡張に力を入れている。