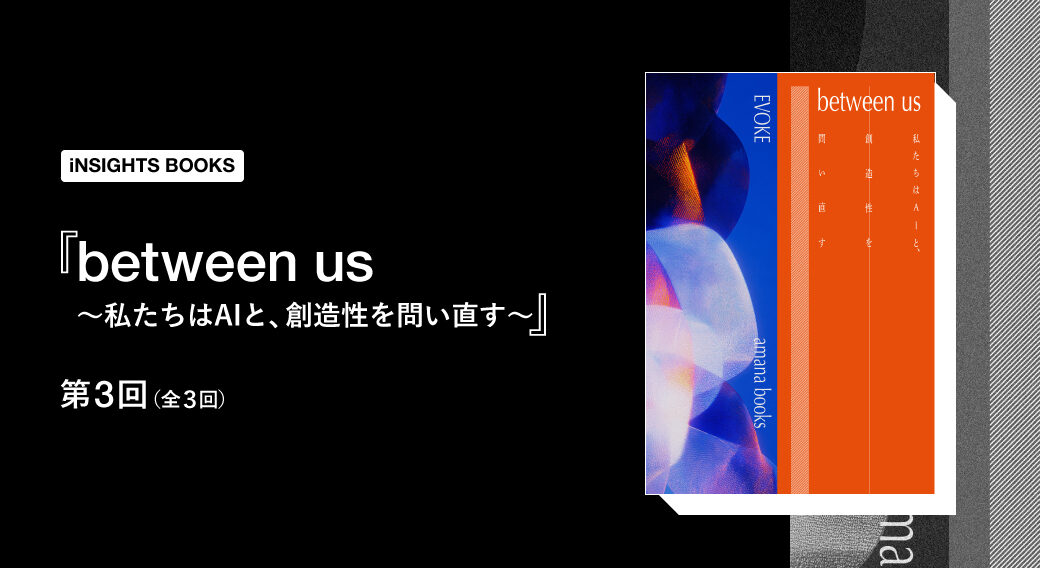
本記事は企業の広告・ブランド担当者に役立つ本から、気になる一節を数回に分けてご紹介する連載です。
読みながら、その本の“考え方”に少しずつ触れていただけます。
AIにどこまで任せ、どこから人が決めるべきでしょう?使いこなす鍵は、AIを活用するフェーズを“Fast Creative”と“Slow Creative”に分け、役割と期待する生成物を整理することです。“Fast”と“Slow”の使い分けとAI、人間の役割について解説します。
~本コンテンツは、書籍『between us〜 私たちはAIと、創造性を問い直す』(アマナの社内クリエイティブチーム「EVOKE」著)に掲載されている、生成AIと共創する現場で活躍するイメージディレクター/プロンプトアーキテクト、コンスタンス・リカによるコラム記事を一部抜粋・編集したものです(この記事は第3回/全3回)。
AIが日常的にクリエイティブプロセスに取り入れられるようになった今、よく言われるのは「創造において、どこまでAIに任せ、どこから人間が担うべきか」という問いです。単にスピードや量を競うのではなく、人間の感性や判断をどのように介在させるか、そしてそれをどう深い創造性へと結びつけるか。それこそが、AIを使うことにおいてもっとも本質的なテーマのひとつです。
私はこの協働のプロセスを、“Fast Creative”と“Slow Creative”という2つの時間軸で捉えています。Fast Creativeとは、情報収集やアイデア生成といった、速度と量が求められる初期フェーズです。ここではAIの力を最大限活用し、曖昧なままのアイデアを投げかけることで、ぼんやりとした思考の輪郭を可視化していくことが目的になります。「こんな雰囲気のブランド名ってどんな言葉がある?」「〇〇な写真の参考イメージってある?」といった未整理な問いでも、AIは数十の可能性を即座に返してくれる。それらの出力が思考の起点になり、次の問いへの導線になります。
たとえば、ブランド開発の初期段階では、AIにネーミング案やビジュアルのトーンを大量に出してもらい、チーム全体の思考の起点にすることができます。まだ言語化されていない感覚や、形になっていないインスピレーションも、AIとのやりとりを通じて少しずつ輪郭を帯びてくる。Fast Creativeとは、まず「バリエーションを出す」ことに価値を置くフェーズです。質を問う前に、とにかく量を出す。その荒削りの中に、人間の思考では辿り着けない意外な視点が紛れていることがある。それが次の問いを引き出し、プロジェクトに新しい視点を与えてくれます。
このプロセスは個人の作業効率を高めるだけでなく、チームでの思考共有にも力を発揮します。AIを通じて生成された多様な出力を共有することで、各メンバーが異なる視点を持ち寄り可視化されていく。つまり、AIは「答え」を与える存在であると同時に、「会話」を促す媒介でもあるのです。この段階では、完璧を求めない勇気も必要です。まずは出力してみる。そして出力から学び、次のプロンプトへとつなげていく。Fast Creativeは、創造の地図を描く前の、自由で奔放なスケッチのようなもの。そこに人間の想像力とAIの計算力が交差する、最初の対話の場です。
スピードだけではなく、質を見極めるための時間も設計すること。AIと人間のバランスは、フェーズごとに変わっていい。
一方で、Slow Creativeとは、生成された素材を選び取り、意味づけ、文脈に沿って編集し、精緻に仕上げていくフェーズです。ここでは、視覚的・感覚的な判断、倫理的な配慮、そして感情との接続が求められます。私はこのSlowCreativeの段階こそ、人間の知性と感性が最も活かされる場だと考えています。Fastの段階では、AIが8割、人間が2割ほどの役割分担で構いません。しかしSlowの段階では、人間の比重が一気に増し、8割を占めるようになります。つまり、AIは加速装置ではあっても、最終的な価値判断を下すのはあくまで人間ということです。
Slow Creativeとは、AIが生み出した提案や素材を、選び取り、意味づけ、文脈に沿って再構築するフェーズです。出力をただ受け取るのではなく、その背後にある意図や空気感を読み取り、自分の言葉や感覚で“編み直す”。それは表層を整える作業ではなく、本質的な響きを探る繊細な編集行為に近いと感じています。
(この記事は第3回/全3回)
▼書籍紹介
アマナの社内クリエイティブチームEVOKEが、生成AIとの実践と対話を通じて創造性を問い直した書籍『between us ~私たちはAIと、創造性を問い直す~』を刊行。創造の現場から生まれた実践知と多様な視点が交差する一冊です。
▼書籍情報
書名:between us 私たちはAIと、創造性を問い直す
著者:EVOKE(アマナ)
出版社:アマナ
発売日:2025年7月7日
Amazonリンク:https://www.amazon.co.jp/dp/B0FFSGFZBK
関連記事
プロンプト時代の言葉と創造性 〜EVOKE書籍出版イベント ゲストセッションレポート
「誰でも使える」時代のその先へ。Creative with AIで「自分たちらしさ」の文化を創る
AIと共進化するデザインの未来|人間の創造性が持つ唯一無二の価値とは
EVOKE制作事例記事
アサヒグループジャパン|企画段階の新商品の世界観をPoCで可視化
AQI|10年後の未来を可視化する「未来シナリオ」
生成AIとクリエイターの共存:プロ向けマインドセット【日光メープルシロップ制作事例】
人気のダウンロードコンテンツ
ブランド表現を強化する生成AI活用術:事例&実践ガイド[FREE DOWNLOAD]
文・編集:桑原勲
![]()

EVOKE
EVOKE
CO-CREATING FUTURES.
amana inc.のクリエイティブチームEVOKE。
クリエイティブコラボレーションを通じて、目指す未来を描き出す。
最近は、AIを活用したクリエイティビティの拡張に力を入れている。