
2025年、大阪・夢洲で開催中の「大阪・関西万博」は、160を超える国と地域、企業が参加する大規模イベントです。「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに掲げるこの万博は、各国や企業が独自のビジョンを提示する“未来のショーケース”とも言える場です。
今回は、アマナのクリエイティブディレクター/プランナーの鈴木陸がナビゲーターとなり、実際に万博会場を訪れて感じた「秀逸なブランドコミュニケーション」や「印象的だった空間演出・コンテンツ」をご紹介します。
「みなさん、こんにちは。私は日々、企業のブランディングやマーケティングを支援する仕事をしています。先日、大阪・関西万博を視察してきたのですが、企業の広告・宣伝担当者にとって、今後プロモーションやブランド体験設計に活かせる学びが随所にあると感じました。そこで今回はブランディングや空間演出の視点で注目すべき施設や、現場で得た気づきをレポートしたいと思います」
私が最初に訪れたのがフランス館です。外観からして美しく、白を基調とした建物にピンクゴールドの螺旋階段が映えるデザインは、まるで劇場のような佇まいであり、ハイブランドのジュエリーのように輝いています。また等身大の彫刻には赤い糸が結ばれていて、フランスのテーマである「愛の賛歌」を入場前から感じ取ることができます。
フランス館。
「愛の賛歌」をテーマに、赤い糸で結ばれた等身大の彫刻。
万博には終日滞在しても、すべての施設を見学できたわけではありませんが、このフランス館がブランディング観点で最も印象的なパビリオンでした。空間全体において「モダンとクラシック」「明と暗」「広さと狭さ」といったギャップが巧みに演出されていて、ゾーンを移動するたびに「次は何が待っているのだろう…?」という期待が自然と高まる設計がなされていました。
入口から入ると、暗がりの空間にネオンが光り「モダンな雰囲気が続くのかな…」と思いきや、突如、ルイ・ヴィトン(LOUIS VUITTON)のトランクが壁いっぱいにズラリと並ぶ圧巻のエリアへと移行します。私自身、ルイ・ヴィトンの展覧会にも足を運んだことがありますが、展示物は似通っていても、万博という場でこうしたラグジュアリーブランドが、アートやクラフトを通じて「人間の創造力」を祝福するような空間を作り上げたことは感動的でした。トランクに刻まれた「MADE IN FRANCE」の文字が、ここでは誇りそのものとして輝いていました。
フランス館の入り口は、ネオンの光が印象的なモダンで都会的な空間。これから始まる体験への期待感が高まります。
ルイ・ヴィトンのトランクが囲む空間。トランクに刻まれた「MADE IN FRANCE」の文字 。
館内にはロダンの彫刻が複数展示されているのですが、そのどれもが「手」の彫刻です。「人間の可能性」というメタファーとしての“手”が「職人技」「創造性」といったブランドメッセージとも共鳴しているように感じられました。
館内のロダンの彫刻。
全体を通じて、最新技術によるデジタル表現が施されていますが、それを目的化せず、メッセージを「伝える手段」として的確に活用されている点も好印象でした。映像表現ひとつを取っても、演出はクラシカルで手触り感があり、アナログとデジタルが非常にバランスよく用いられていました。
展示映像より。
さらに進んでいくと、突然屋外に連れ出され、緑豊かな「ミラクルガーデン」が現れます。人工池のほとりに立つオリーブの木は樹齢千年を超えていながら、新芽が生えていて自然の生命力を感じさせます。このエリアだけでもゆったりと過ごしたくなるほど魅力的でした。
樹齢千年を超えるオリーブ「若さの樹 (Tree of Youth)」が公開されているミラクルガーデン。
フランス館は、ブランドのストーリー性と空間体験をどう融合させるかという点で、非常に示唆に富んでいました。ブランディングや空間演出を考える仕事に携わる方には、ぜひとも足を運んでみてほしい施設です。
イタリア館は、フランス館とはまた異なる方向性での圧倒的な体験を提供してくれました。まず外観ですが、サステナビリティと循環型建築の理念に基づき、主要な建築素材として木材が多用されています。日本の伝統工法を意識した楔(くさび)も印象的で、日伊の文化交流を感じせますし、万博の象徴「大屋根リング」とリンクするような造形です。
イタリア館。
日本の伝統工法を意識した楔(くさび)。
館内に入りまず圧倒されたのは、古代ローマ時代の大理石の彫刻「ファルネーゼのアトラス」。この巨大なアトラス像をはるばる日本まで運んできたこと自体がすごいですが、ガラス張りや柵もなく、間近で鑑賞できる設計にも驚きました。触れられるほどの距離でこそ見てほしいという展示の姿勢に、イタリアの「本物の力」への自信、信頼を感じました。
日本初公開の古代ローマ時代の大理石の彫刻「ファルネーゼのアトラス」。
その後に続くのは、カラヴァッジョの絵画やダ・ヴィンチの直筆スケッチなど、まさに「人類の財産」ともいえる作品の数々。こうした展示が一貫して「芸術は生命を再生する」というテーマのもとに構成されていて、見る側としても一つひとつがストーリーの断片として心に響きます。
カラヴァッジョの「キリストの埋葬」。
レオナルド・ダ・ヴィンチの「アトランティック・ コード」。
一方で後半のテクノロジーゾーンに関しては、やや構成上の冗長さを感じました。フェラーリに搭載される製品や航空技術など、一つひとつの展示は魅力的なのですが、前半の展示があまりに圧倒的だったこともあり、テーマの連続性という点では少し散漫な印象を受けました。このあたりは、展示の構成やテーマ設計における難しさといえるかもしれません。
フェラーリのブレーキの展示。
航空宇宙産業の展示。
会場内を歩いていると、白い小さなロボットが静かに巡回しているのを見かけました。これはセコムが提供する自律巡回警備ロボット「cocobo(ココボ)」です。警備ロボットでありながら、その存在感はとてもやさしく、子どもが興味を持って追いかけている姿を見かけました。
セコムが提供する自律巡回警備ロボット「cocobo」。
こちらはダイハツが提供している電動カート「e-SNEAKER(イー・スニーカー)」。観察してみると、細部にまで配慮が行き届いたデザインが施されていました。タイヤ部分にはミャクミャクの目玉があしらわれており、機能性と遊び心を兼ね備えた仕様になっています。
ダイハツが提供している電動カート「e-SNEAKER」。
このように、企業ロゴやメッセージを強く打ち出すのではなく、あくまでイベント空間の一部となる製品やサービスを提供するという企業姿勢には好感が持てます。来場者との自然な関係性が生まれ、結果として各企業のブランドの信頼性を高めているように感じました。
デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデンの5カ国が合同で出展している北欧館ですが、ここでは展示物などではなく、あるアイテムを紹介したいと思います。
それは「日傘」。私が視察した日は4月とは思えないほどの日差しでしたが、入場待ちをしている来場者にオリジナルの日傘を貸し出していたのです。入場待ちの列がひと固まりとなることで、遠くからも「あそこはなんだろう?」と興味を引く存在になっていました。これもある種の“デザイン”だと感じます。実際にメディアでも、万博の暑さを伝えるニュース素材として、北欧館の行列の写真が使われていました。屋外イベントを企画する際は、来場者への気遣いとして機能しつつ、思わず写真や動画を撮りたくなるような仕掛けをしてみるのも面白いなと思います。
来場者に日傘を貸し出している北欧館。
アメリカ館は、ある意味で最も“予想通り”でありながら、そのスケール感と没入演出で圧倒されました。入場の際には、巨大モニターに映し出された星条旗が出迎えてくれます。まさに「THE U.S.A!」という直球の表現です。
アメリカ館。
館内は映像コンテンツを中心とした構成で、特に印象的だったのが、NASAの協力による「ロケット打ち上げ体験」です。来場者がまるでロケットの真下にいるかのような臨場感を味わえる没入型の映像演出で、轟音や振動も加わり、まるで自分が宇宙へ飛び立つかのような感覚を味わえました。
来場者がまるでロケットの真下にいるかのような臨場感を味わえる没入型の映像演出。
展示物として目新しさがあるわけではありませんが、誰もが抱く「アメリカ」のイメージを、そのまま空間体験として具現化していた点において、とてもわかりやすく、かつ強いブランド印象を残すものでした。「へぇ〜」という知的な驚きではなく、「やっぱりすごい!」という感嘆。この感情の演出こそ、強いブランドが大衆と接点を持つときに、大きな武器になると再認識しました。
右側に映っているアメリカ館の公式キャラクター「スパーク」がいろいろと紹介をしてくれます。
展示映像より。
null2館は、万博の中でも特にアート性の強い空間として刺激的でした。外観は夜になると光を反射し、どこか近寄りがたい不気味な雰囲気を漂わせています。
内部にはロボットアームや巨大なモニター、そしてプロジェクションマッピングを駆使したインスタレーションが展開されており、その空間はまるで異世界。音もまた強烈で、ただのBGMではなく、空間そのものの“感情”を表現しているかのような役割を果たしていました。
鏡を利用して、床、壁、天井をすべて映像で取り囲んだ空間。
観客の映像も映像に混ざり、リアルタイムで変化します。
デジタル空間とのインタラクション。
「美しさと恐怖」「秩序と混沌」といった両極の感覚が共存する空間で、どこか不安になるのに目が離せないような体験。それはまさに、アートが本来持っている力だと思います。明快な意味や説明はありませんが、むしろ“感じ取ってください”というメッセージが満ちていました。ブランドもまた“感情”に訴える表現です。感じさせる、考えさせる、心を動かす──それができる空間こそが、強く印象に残るのだと思います。
シグネチャーパビリオン「null2(ヌルヌル)」の外観。
今回の万博を通じてあらためて思ったのは、「リアルな体験」にこそ、ブランドの真価が問われるということです。コロナ禍を経てリアルイベントが盛況ですが、お金と時間をかけてきた来場者の期待値は無意識のうちに高くなっています。それに応えられなければ、ブランドの信頼は一気に下がってしまう──そんな“覚悟”が必要な時代に入ったのだと強く感じました。
SNS時代の今、私たちは“切り抜き”や“一瞬の映え”に目を奪われがちです。しかし、表面的な演出だけで勝負すると、「実物は大したことなかった」と思われ、ブランドにとっては逆効果になりかねません。本質的に楽しかった、美しかった、感動した、という体験を徹底してつくり込めるかが、ブランドにとって最大の分かれ道になると思います。
私は企業のブランディングをお手伝いするとき、まず“らしさ”にとことん向き合います。内向きの視点で顧客やサービスの“らしさ”を深く掘り下げつつ、同時に外向きの視点も忘れずに「でもそれって消費者視点だと魅力だろうか?」「グローバルでも通用するだろうか?」と批判的にもなれるか。「徹底的な自問と徹底的な客観視」。この二つが強いブランドづくりには欠かせません。
もちろんそれは昔からそうなのですが、形式的なだけではなく“徹底的な”というのがミソです。形式だけのブランディングでは、いざという時に「なぜそれが必要なのか?」という問いに答えられません。徹底的に向き合い、自分たちの価値を深く掘り下げること。それが、ブランドを強くする唯一の方法だと信じています。
なんでもAIでつくれる時代だからこそ、人間にできることは「本質をより自分で自分事にできるか」に尽きると思います。社内的に誰かに気を遣ったり、忖度したりして折れてしまうのがブランディングにはつきもの。そこで客観的な視点を持ちながら、やり抜くことは簡単ではありません。だからこそ、私たちアマナのブランディング支援サービスには介在価値があると考えています。
もし、展示会やイベント、あるいはブランド体験のアップデートを検討されている方がいらっしゃいましたら、ぜひ私たちにご相談ください。アマナのクリエイティブチームが、「本質」と「表現」の両輪で、貴社のブランド価値を未来へとつなぐお手伝いをいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
取材・撮影:鈴木陸(アマナ)
編集:小林拓美
アマナのサービスはこちら
ブランディング
プロモーション制作
イベント制作
こちらの記事も読まれています
実例と共に徹底解説!周年事業のプロフェッショナルは、周年をどのように盛り上げるのか?
BtoBは共感の時代へ、スペックよりも伝わる情緒的な表現とは
「Immersive Museum TOKYO」の大迫力の没入(イマーシブ)体験を生み出す、アマナのCG制作を解剖
![]()

株式会社アマナ
鈴木 陸
株式会社アマナ
鈴木 陸
プランナー・ディレクター。BtoB / BtoC企業の社内コミュニケーション施策から、ブランドコンセプト開発、企画・制作ディレクションまで手がける。どんなモノ・コトにも背景には必ず人の想いがある。そうした本質を見いだして、ストーリーを紡ぐことを大切にしている。

amana BRANDING
amana BRANDING
共感や信頼を通して顧客にとっての価値を高めていく「企業ブランディング」、時代に合わせてブランドを見直していく「リブランディング」、組織力をあげるための「インナーブランディング」、ブランドの魅力をショップや展示会で演出する「空間ブランディング」、地域の魅力を引き出し継続的に成長をサポートする「地域ブランディング」など、幅広いブランディングに対応しています。

amana PROMOTION
amana PROMOTION
お客様の目的や課題を深く理解した上で、最適な媒体やツールを選択。オーダーメイドによるプロモーションの企画を提案いたします。マス広告から、Webサイトやアプリケーションなどのデジタル領域、雑誌メデイア、リアルな空間でのイベントまで、アマナのさまざまなサービスを組み合わせて展開するプロモーションプランニングを得意としています。
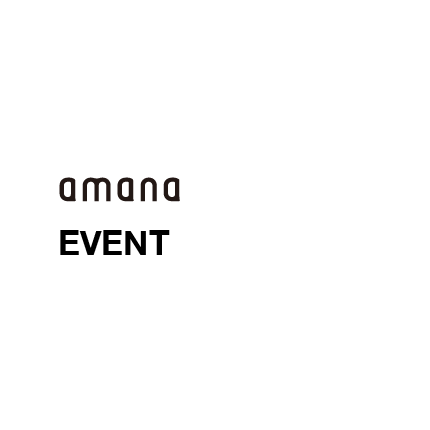
amana EVENT
amana EVENT
魅力的な体験をもたらすイベントを企画・運営
展示会や商品発表、店舗やホールでの特別な催しなど、各種イベントの企画から設営・運営まで、幅広く対応しています。ブランドや商品価値の理解のもとに会場を設計・デザイン。ビジュアルを活かした空間づくりや、AR・VR技術を駆使した今までにない体験型のエキシビションなど、ビジュアル・コミュニケーションを活用したイベントを提案いたします。