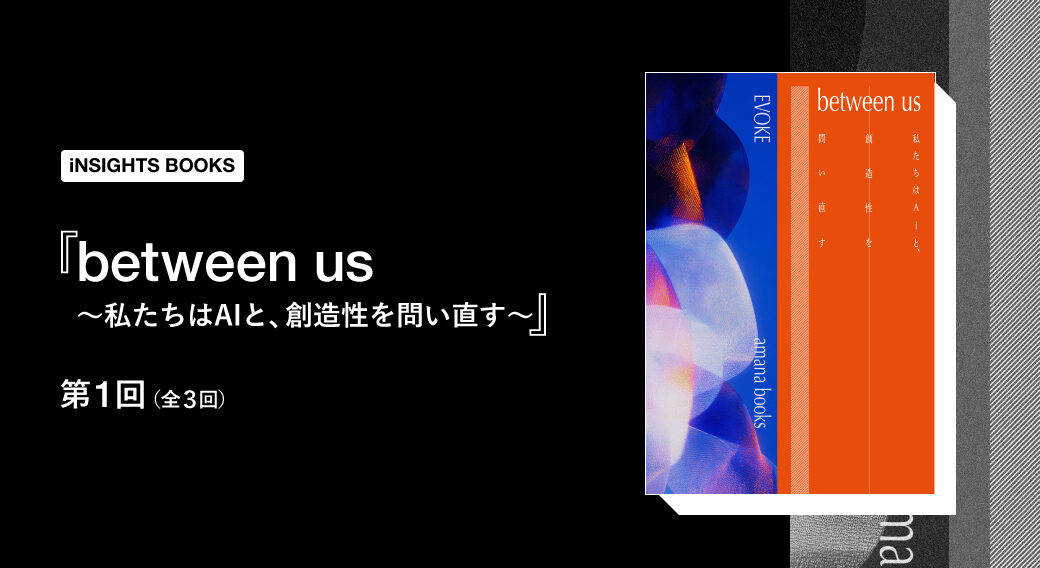
本記事は企業の広告・ブランド担当者に役立つ本から、気になる一節を数回に分けてご紹介する連載です。
読みながら、その本の“考え方”に少しずつ触れていただけます。
何度プロンプトを書き直しても、AIが意図したアウトプットを出してくれない……。生成AIを使いこなすポイントは、AIが理解できるように“感性”を言語化することです。ここでは、アウトプットの質を左右するプロンプト作成の具体的な思考方法を紹介します。
~本コンテンツは、書籍『between us〜 私たちはAIと、創造性を問い直す』(アマナの社内クリエイティブチーム「EVOKE」著)に掲載されている、生成AIと共創する現場で活躍するイメージディレクター/プロンプトアーキテクト、コンスタンス・リカによるコラム記事を一部抜粋・編集したものです(この記事は第1回/全3回)。
たとえば「秋の風景」を描写する場合、日本語の「紅葉」という言葉をそのまま使っても、英語では “autumn foliage”や”fall colors”といった表現に訳されるのが一般的です。しかし、これらの訳語では「紅葉」が持つ情緒や文化的合意を十分に伝えきれません。「紅葉」は単なる自然現象としての葉の色づきにとどまらず、特に楓の赤を愛でる美意識や、季節を味わう心のあり方、さらには「もののあはれ」と結びついた感受性までをも含んだ言葉です。英語ではこうした意味を一語で包含することが難しく、たいていは説明的に解釈するしかありません。
このように、日本語特有の感性をAIに伝えようとするとき、単語ひとつで済ませるのではなく、その背後にある情景や感情を具体的なイメージに分解して翻訳する必要があります。たとえば、「乾いた落ち葉を踏みしめる音」や「肌寒さが頬をかすめる午後」といった情緒的な表現には、音・温度・身体感覚といった複数の感覚的レイヤーがあり、人間の想像力を喚起します。
しかし、AIモデルの中にはこうした表現を字義通りにしか捉えられないものもあり、特に日本語で書いたままでは意味が正確に伝わらないことがあります。一部のモデル(たとえばChatGPTやClaude)は英語の情緒表現にある程度対応できますが、日本語の詩的・抽象的な言い回しはしばしば無視されたり、誤って解釈されたりするのです。私はAIとのやりとりにおいて、次のような翻訳戦略を取っています。
Prompt: a cold breeze touches the face of a young Japanese woman on a late autumn afternoon, evoking a sense of stillness. (Midjourney)
Prompt: a chilly afternoon breeze brushing the cheeks of a young Japanese woman (Midjourney)
1.視覚的要素が明確に記述されている
А quiet park path with dry, crunchy leaves underfoot
・静かな公園の小道(quiet park path)
・乾いた葉っぱ(dry leaves)
・足元にある(underfoot)
・踏んだときの音や感覚(crunchy)
「視覚+聴覚+質感」の情報が含まれ、AIが「何をどう描けばよいか」を明確に理解できます。一方、日本語から直訳した「The sound of stepping on dry leaves」は音にしか言及していなく、画像生成AIにとっては視覚的な手がかりがほとんどありません。
2.文の構造が「シーン」を形成している
A cold breeze touches the face on a late autumn afternoon, evoking a sense of stillness
・時間軸(late autumn afternoon)
・行為(breeze touches the face)
・感情的効果(evoking a sense of stillness)
「物理的現象+時間+感情的ムード」がセットで含まれ、AIが「どんな雰囲気のシーンにすべきか」を判断しやすくなります。一方で、直訳の「A chilly afternoon breeze brushing the cheeks」は意味としては正確ですが、AIが解釈できる視覚構造が薄く、「何を描けばいいのか」が曖昧になります。
こうした構造的な工夫が有効なのは、単に言葉を翻訳するためだけではありません。AIに伝わる“雰囲気”や“空気感”を生み出すには、私たち自身の観察力や感性が不可欠なのです。
(この記事は第1回/全3回)
▼書籍紹介
アマナの社内クリエイティブチームEVOKEが、生成AIとの実践と対話を通じて創造性を問い直した書籍『between us ~私たちはAIと、創造性を問い直す~』を刊行。創造の現場から生まれた実践知と多様な視点が交差する一冊です。
▼書籍情報
書名:between us 私たちはAIと、創造性を問い直す
著者:EVOKE(アマナ)
出版社:アマナ
発売日:2025年7月7日
Amazonリンク:https://www.amazon.co.jp/dp/B0FFSGFZBK
関連記事
プロンプト時代の言葉と創造性 〜EVOKE書籍出版イベント ゲストセッションレポート
「誰でも使える」時代のその先へ。Creative with AIで「自分たちらしさ」の文化を創る
AIと共進化するデザインの未来|人間の創造性が持つ唯一無二の価値とは
EVOKE制作事例記事
アサヒグループジャパン|企画段階の新商品の世界観をPoCで可視化
AQI|10年後の未来を可視化する「未来シナリオ」
生成AIとクリエイターの共存:プロ向けマインドセット【日光メープルシロップ制作事例】
人気のダウンロードコンテンツ
ブランド表現を強化する生成AI活用術:事例&実践ガイド[FREE DOWNLOAD]
文・編集:桑原勲
![]()

株式会社アマナ
コンスタンス・リカ
株式会社アマナ
コンスタンス・リカ
イメージングディレクター・ビジュアルコラボレーター。ダイナミックなビジュアルデザインスキルとグローバルな感性で、インパクトと意味のある体験を生み出す。既成概念に新しい視点と変化を与える事で、新たな価値を創造することを目指し、デジタルブランディングとビジュアルプロトタイピングを中心に様々なプロジェクトに取り組んでいるクリエイティブ錬金術師。

EVOKE
EVOKE
CO-CREATING FUTURES.
amana inc.のクリエイティブチームEVOKE。
クリエイティブコラボレーションを通じて、目指す未来を描き出す。
最近は、AIを活用したクリエイティビティの拡張に力を入れている。