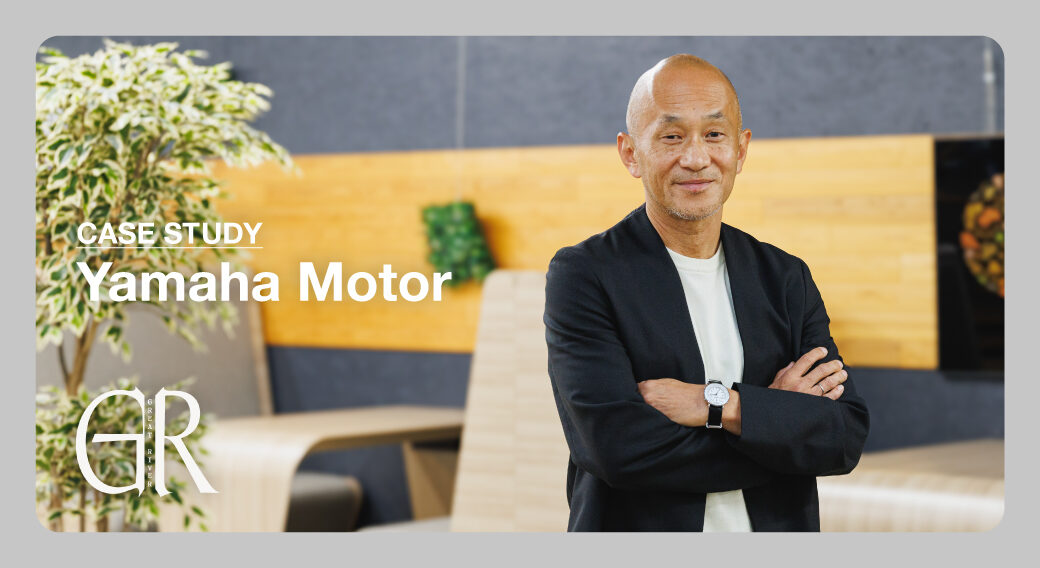
アマナが提供する「GreatRIVER」は、クリエイティブ人材の参画によって社内の課題を解決する創造性人材サービスです。定型業務の遂行ではなく、課題解決に必要なあらゆる業務を企業の内部から実行する本サービスは、企業が自らにおいて創造性を高めることを狙っています。
GreatRIVERを利用するヤマハ発動機株式会社(以下ヤマハ発動機)クリエイティブ本部は一般的なデザイン開発業務だけに留まらず「会社全体の創造性を強化する」という役割も担っています。その中で「GreatRIVER」がどのように利用されているのか、ヤマハ発動機執行役員、クリエイティブ本部長の木下拓也さんにお話を伺いました。
ヤマハ発動機が創業された1955年、日本には140ほどのオートバイブランドがありました。最後発のブランドであったため、創業時から先行する他社とは違うことをやらなくてはならないことが宿命づけられた会社でありました。現在は180カ国に陸海空のヒューマンサイズの乗り物を、加えてロボティクスソリューション事業なども展開するまでに成長しましたが、違うことをやりつづけることで市場でのプレゼンスを上げてきた結果と言えます。戦略的でなく、やりたいことを創造的にやってきた結果であるということです。
ヤマハ発動機が創造性を発揮して社会に貢献する、つまりクリエイティブ本部だけが創造的であるということだけでなく、「会社全体がクリエイティブになるには」を検討することが私たちのミッションです。その結果、事業競争力やブランド価値の向上に繋がると考えています。
ヤマハ発動機株式会社/執行役員 クリエイティブ本部長 木下拓也さん
「やりたいことを創造的に」というのは、ボトムアップで活動してきたと言い換えられます。元来ヤマハ発動機は社員が「こういうことをやりたい」と言いだしたら、自分で仕事にすることができる風土でした。とはいえ、会社の規模が現在まで大きくなると、当然機能、役割は分化します。そうなることで一人一人のモチベーションや、インキュベーション型の生む力は削がれてしまうかもしれません。それはやむを得ない側面です。とはいえ、創造性の発揮が宿命であるヤマハ発動機にとって、社員がやりたいことができる環境は非常に重要です。だから、我々のような組織がどれだけサポートできるかが肝なのです。
クリエイティブ本部では、今まで自然発生的に存在していたボトムアップの創造性というものを意図的に会社の強みにするにはどうしたらよいか、ということに取り組んでいます。まずは量を求めよう、何回創造的な活動ができたのか、他部門に対して何回サポートができたのかを指標としています。事業のビジョンメイキング、戦略メイキング、もしくは合宿がしたい時にクリエイティブ本部に手伝ってもらいたいということが何回できたかを問う。私たちが社内に対して「こういうことができます」と営業しているのですが、そういったサポートのクオリティも量が作ると考えています。イノベーションは1000回の活動の中から3つしか生まれない、それであれば、1000回活動しないといけない、つまり量をこなす必要があるのです。
サポートをしていく中で、自分たちの創造性も高まり、場の設計、進め方を設計する上で、デザイナー自らがどう機能しなくてはいけないのかを考えるようになってきています。現在、YDT〜ヤマハデザインシンキング~という「ヤマハらしい」デザイン手法論を作ろうとしています。ヤマハらしいデザインシンキングとはを問い続けていくことが重要です。デザインシンキングを使って答えを見つける人になるのではなく、問いを立てられる人になる、サポートの中でデザイナーが「問う人」を演じられるようになることは、創造性を発揮し、実装していく点で大事だと考えています。
会社の創造性を自ら高めよう、やり方自体を内製で生み出そう、事業の競争力を上げる活動をしていこうと考えたときに、社内のデザイナーはほとんどがプロダクトデザイナーなので、専門領域が違います。ブランド価値を上げるためのコミュニケーションデザインとか、ブランドアイデンティティ、ビジュアルコミュニケーションという面においては、社内人材だけ賄うには経験が足りない。だから外部の「創造的専門人材」には、会社全体のブランド価値を高めるためのデザイン機能を補ってくれるという意味があります。
そして、このデザイン機能は、外に頼めばいいよねという話ではなくて、やはり中に入ってもらわないと分からないことが沢山あります。ヤマハ発動機は会社としては70歳になります。良し悪しはありますが、70年間積み重ねたやり方、考え方の癖があります。その癖をどう強みに活かすか。GreatRIVERスタッフは、新しさのみならず、社内のクリエイティビティ、デザイン能力を拡大する存在であるとも捉えています。
現在アートディレクター1名、クリエイティブディレクター1名と2名のGreatRIVERのスタッフに参画してもらっています。彼らには70周年の動画や、ビジュアルコンセプトづくりなど、制作や検討議論などで力を発揮してもらっています。彼らの視点によって、内部の人間が改めて自覚できることが沢山ありました。無自覚に悪いことや「それは言わない約束」となってしまうことが今までは内部の視点だけであるが故にありました。そのような習慣や考え方を違った角度、視点から指摘してもらえるのは一つの効果といえます。
最近の消費者は、会社の方針や価値観、哲学を知るときに、プロのモデルによる「これいいでしょ」という表現だと「そもそも嘘だよね」と受け取る傾向が強くなってきています。70周年の動画は、社員ががんばっている姿や実際のレースシーンなどを取り入れたリアルな映像を用いています。そういった視点をもって実際の動画を作成できたのも、中に入ってくれたGreatRIVERによる力だったのではないかと思います。
伴走によって内製化を支援してもらってはいるものの、GreatRIVERを利用すれば、全てが内製化できるということではないと考えています。ヤマハ発動機の場合、インハウスのデザイン組織を作ってまだ13年程度ですし、今も外部にデザイン業務を依頼するという状態をキープしています。コミュニケーションデザインなど、内製の力を強めたいという狙いはあるとはいえ、インハウスデザインがなかった時代から「ヤマハはデザインがいいよね」と評価されてきたのは、デザインする力が外部にもあったからこそなのではないかと考えています。外部から「ヤマハのデザインの哲学というのはこういうものだ」と関わってくれたことで、製品設計と、デザインとを戦わせることができて、結果良いものが生まれてきたとも考えられます。
すべてを内製化してしまうと、デザインのロジックは、事業や開発、営業のロジックに勝てなくなるかもしれません。それぞれの部門の正義、ロジックが戦うことで良いものが生まれるというのは、歴史的にヤマハ発動機が選択してきた創造性を高める手法の一つと捉えることができます。そういう意味で「中の人」になりきらず、外から刺激を与える存在であってほしいですね。
GreatRIVERによって、コミュニケーションデザイン、UXデザイン機能を向上させる必要があるというだけではなく、社内のリテラシーが上がり、仕事のやり方がアップデートされていく必要があると捉えています。その時に、GreatRIVERのスタッフが、ベンチマークになっているというのも重要なことです。以前の外部に発注していた体制では、できたものを評価するだけにとどまっていました。けれどもGreatRIVERを利用することで、自分たちでやってみるという体制を得て、何を判断して、どう作り直していくかというプロセスを考えることや、今どんなパフォーマンスを出せるのかということを自覚できるようになりました。
まだスタートラインに立った程度ですが、それでも、どのようなスタートラインに立っているのかがわかるようになったのは非常に重要なことです。
GreatRIVERを通して、継続的に、アマナさんのクリエイティビティという外からの刺激を受けられるということが、ヤマハ発動機のデザイナーの創造性と、会社の創造性の向上につながることを期待しています。
取材・文:秋山龍(合同会社ありおり)
取材撮影:大久保歩(アマナ)
関連記事:
ヤマハ発動機の次なる「感動」が伝わるために。クリエイティビティを磨く、amana Creative Camp
創造性人材が未来の構想力を注ぎ込む―GreatRIVERが提案する創造的企業変革
![]()

GreatRIVER
GreatRIVER
澱みなき大河が、創造性を呼び起こす
Great RIVERは、目標を達成するための創造的な組織を共に創り上げるサービスです。各分野のプロフェッショナルである創造性人材が企業と一体となり、社内だけでは補えない視点や専門性、新たな視点や発想を持ち込みながらプロジェクトの基盤を支えます。