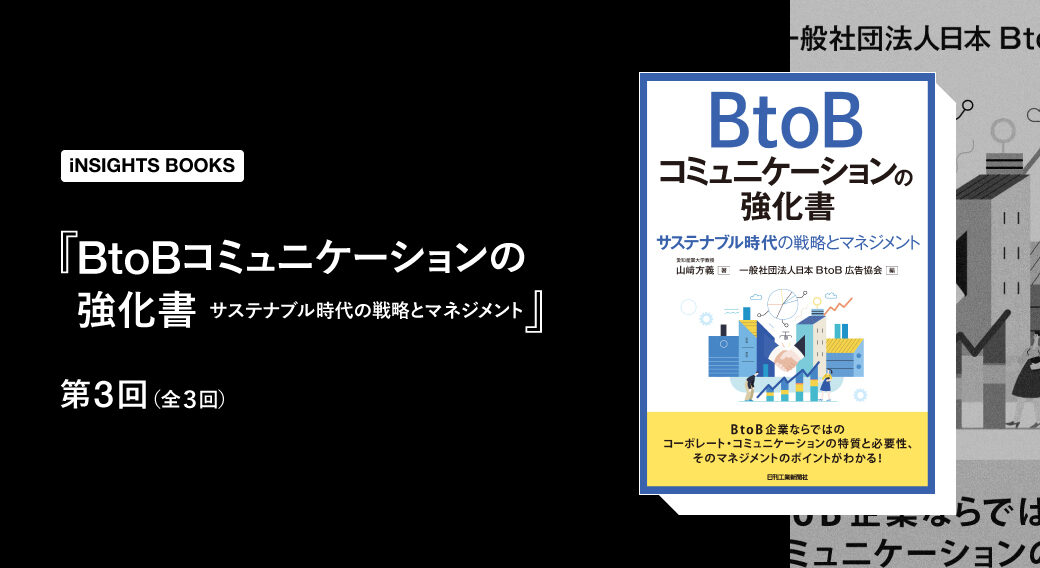
本記事は企業の広告・ブランド担当者に役立つ本から、気になる一節を数回に分けてご紹介する連載です。読みながら、その本の“考え方”に少しずつ触れていただけます。
BtoBブランドは何を訴求するべきか。技術や素材をもつ企業はもちろん、独自サービスやノウハウを持つ企業が参考にしたい考え方を紹介します。
~本コンテンツは、書籍『BtoBコミュニケーションの強化書』(山﨑方義著・一般社団法人日本BtoB広告協会編・日刊工業新聞社刊)に掲載されている、BtoB企業におけるコーポレート・コミュニケーションの必要性、マネジメントの重要性について解説した内容を一部抜粋・編集したものです(この記事は第3回/全3回)。
岡本智『技術のブランディング“衝突安全技術”のブランドマネジメント』〈1.※〉では、最終的なユーザーである消費者にとっての商品あるいはサービスにおいて、その商品、サービスを構成する要素として成り立つ技術を対象としたブランドを要素技術ブランドとして扱う、と述べています。
その上で「一般消費者が消費する商品またはサービスについて、それを構成する要素として、ある一定の機能、便益をもたらす、物質、手順、仕組み、機構などに対して、業種内で一般的に用いられる名称とは別に、固有の名称をつけた場合の名称」と定義しています。
本書では、必ずしも上記の定義とは一致しない部分もありますが、部品や素材等をブランド化したフレームの呼称がいくつかある中で “要素技術ブランド”を使用します。その理由は次の通りです。“成分ブランド”は化合物や合成物に含有される物質を連想させ、部品やサービスに適用するには誤解が生じる可能性があります。
“インブランド”は総括的な解釈は可能ですが、後で論じる概念の拡張性と整合しづらい面があります。構成要素を必ずしも“in”に限定せず、製品の外に附随する技術サービスも含めて考えた方が実務的に有効だと判断しており、内部に組み込まれることを強調した用語は避けたいと考えます。
また“技術ブランド”や“テクノロジー・ブランド”では、用語から連想できる領域が広く、製品やサービスの内部または付属要素としての意味が希薄化する可能性があります。そこで日本語として連想される概念として最も適合する“要素技術ブランド”を選択したわけです。
要素技術ブランドは高付加価値の部品や素材を完成品メーカーに提供することでプレミアムを形成するものです。しかし製品に要素として織り込まれる技術的成果はサプライヤーからの提供に限定されず、自社開発の技術をブランド化するケースも見受けられます。さらにICTの進展により、要素技術による付加価値がシステムやサービスとして提供されるケースも議論に加えるべき状況となっています。
ブランド化の対象となる要素技術を構成する概念を整理すると以下の5点に集約できます。
① 技術に裏付けられている。
② 製品(完成品)やサービスの構成要素として組み込まれているが、内部に限定せず、附随ないしは情報システム等、外部から製品やサービスに働きかける要素も含む。
③ 製品(完成品)とは別に個別のブランディングが図られている。
④ 構成要素の領域は技術、部品、素材、サービス等である。
⑤ 構成要素はサプライヤーから提供される場合と自社開発の場合がある。
私が捉える要素技術ブランドの特質は、既存のフレームでは対象とならない上記の②を包含する点です。すなわち完成品の内部に留まるのではなく、概念を拡張して外部から働きかける付加機能を含めて考えます。
要素技術ブランドの概念/出典;〈2.※〉
ここで述べている枠組みの原語にあたる“Ingredient Brand”は、例として「Intel Inside」が挙げられるように、もともと製品やサービスの内部に組み込まれるという前提に基づく概念です。
しかし今日では上記要件の⑤で述べたように、自社開発技術をブランド化して構成要素とするケースが一般化しています。例えば、パナソニックのナノイー、シャープのプラズマクラスターなどです。そうなるとBtoBtoCのBtoB領域を外し、BtoC領域で製品メーカーと最終ユーザーとのリレーションシップだけが対象となることが成立します。
また完成品メーカーとエンドユーザーとの関係性が中心になると、BtoB取引における要素技術ブランドの位置づけはユーザーの認識として低くなると考えられます。
ヒートテックやエアリズムと聞くとユニクロを真っ先に連想しますが、素材メーカーである東レとのコラボレーションで開発されていることまで知る人が少ないのはこのためです。
1.※岡本 智(2003)技術のブランディング“衝突安全技術”のブランドマネジメント.法政大学産業情報センター・小川 孔輔(編).ブランド・リレーションシップ(pp.3-26)同文舘出版
2.※山﨑 方義(2024).サステナブル時代のBtoBコミュニケーション 第12回 要素技術ブランドとグローバリゼーション BtoBコミュニケーション,56(12),22-28.
(この記事は第3回/全3回)
▼書籍紹介
BtoB企業は、人々の生活を支える社会基盤を提供する不可欠な存在です。ビジネス規模も大きく産業界において重要な役割を果たしています。本書は、BtoB企業ならではのコーポレート・コミュニケーションの特質と必要性、そのマネジメントのポイントなどを解説し、実務にも役立つように様々な視点からBtoBコミュニケーションを取り上げています。
▼書籍情報
書名:BtoBコミュニケーションの強化書
著者:山﨑方義著・一般社団法人日本BtoB広告協会編
出版社:日刊工業新聞社
発売日:2025年6月12日
リンク:https://pub.nikkan.co.jp/book/b10135293.html
この記事もよく読まれています
BtoB商材向け|市場を育てるマーケティングの手順と組織設計
BtoB企業のYouTube活用最前線。映像と設計で伝える10事例
第46回日本BtoB広告賞から読み解くヒント「自社の想いをどう形にするか?」
文・編集:桑原勲
![]()

amana BRANDING
amana BRANDING
共感や信頼を通して顧客にとっての価値を高めていく「企業ブランディング」、時代に合わせてブランドを見直していく「リブランディング」、組織力をあげるための「インナーブランディング」、ブランドの魅力をショップや展示会で演出する「空間ブランディング」、地域の魅力を引き出し継続的に成長をサポートする「地域ブランディング」など、幅広いブランディングに対応しています。