
画像・動画生成AIの進化により、企業のブランド戦略はいま、ひとつの転換期を迎えています。短時間で高品質なビジュアルが作れるという魅力がある一方で、著作権や倫理、クオリティ管理といった懸念もあり、導入に慎重な企業も少なくありません。こうした状況の中で、生成AIを上手に取り入れていくためには、正しく理解し、安心して活用するためのポイントを押さえておくことが大切です。
今回は、クリエイティブ制作における生成AIの活用例やそのメリット、課題などを詳しく解説します。
近年、生成AIはクリエイティブ分野において欠かせないツールとなりつつあります。デザインや映像、テキストといった幅広い領域で、従来の制作フローを効率化しながら新しい表現の可能性を広げています。
ここでは、具体的な活用例を分野ごとに解説します。
画像生成AIを用いることで、短時間で多様なイメージ案を生み出すことが可能です。ロゴデザインやUIデザインのアイデア出しを効率化したり、質感豊かなテクスチャを自動生成してデザイナーの作業をサポートしたりする活用が進んでいます。
人間の感性とAIの高速な生成力を組み合わせることで、より独創的で訴求力のあるデザインが実現しています。
映像制作の現場でも生成AIの導入が広がっています。実写映像やテキストから自動で映像を生成できる技術は、これまで時間とコストがかかっていた工程の最適化が進んでいます。
特にアニメーション制作では、背景画やモーション、キャラクターの表情差分など、細かい作業をAIが担うことで、クリエイターは物語性や演出の工夫といったより本質的な部分に注力できるようになります。
生成AIを活用すれば、簡単な指示で多様な文体のテキストを生み出すことが可能です。広告コピーやキャッチフレーズのアイデア出しはもちろん、SEOを意識したライティングやブログ記事、さらにはSNS投稿文まで自動で生成できます。
人間がゼロから考えると時間のかかる作業も、AIを活用すれば複数案を瞬時に提示できるため、効率と創造性を両立したコンテンツ制作が実現可能です。質の高い文章をスピーディに展開できる分、企画や戦略に時間を割けるようになります。
生成AIをクリエイティブ制作フローに取り入れることで、従来の制作プロセスでは難しかった表現が可能になり、効率性やコスト面でも大きな変化が生まれています。
ここでは、具体的なメリットや効果について解説します。
生成AIは人間の発想を補完し、従来のデザインや撮影手法では実現困難だったビジュアルを短時間で創出できます。現実には存在しない風景や素材もAIで生成でき、これまでにない独創的な表現も可能となるのです。
その結果、企画の幅が広がり、オリジナリティの高いコンテンツ制作につながります。
デザイナーの手作業では時間を要する作業も、AIを活用すれば短期間で多様なパターンを提示可能です。大量のビジュアルや試作案を短時間で生成できるため、チーム内でのアイデア共有やクライアントとの認識合わせがスムーズになります。
また、サンプル動画やムードボードを即座に用意できることから、全体のプロジェクト進行がスピードアップし、企画立案や仕上げといったコア業務に集中する余裕も生まれます。
生成AIの導入はコスト削減にもつながります。ビジュアル制作を効率化することで、外部への発注や大規模な撮影の必要性が減り、制作費用を抑えられます。
さらに動画制作においても、専門的なスキルや高度な機材がなくともAIが一定のクオリティを担保するため、コスト面での負担軽減につながります。
生成AIは特定のターゲットに合わせたコンテンツを柔軟に生成できるため、顧客の関心を引きやすくなります。
例えば同じ商品写真を活用しつつ、背景やインテリアをターゲット層ごとに最適化すれば、ユーザーごとに異なる印象を与えられます。
そのため、エンゲージメントの向上や購買意欲の刺激が容易になり、よりパーソナライズされたマーケティング戦略の実現が可能になります。
生成AIを導入する企業や組織は増加傾向にありますが、その効果を最大化するには事前の準備と計画が欠かせません。以下では、生成AIの導入検討時に押さえておくべきポイントを解説します。
「何のために生成AIを導入するのか」を整理することが大切です。
業務効率化やコスト削減、新規事業の創出など、企業によって目的は異なります。目的が曖昧なままでは、導入しても期待する効果が得られない可能性があります。
また、効果測定を容易にするためには、KPIや数値化できる目標を設定することが重要です。例えば「制作工数を30%削減する」「事務作業をAIに20%移行する」といった具体的な指標を設けることで、導入の成果を客観的に判断しやすくなります。
導入目的を整理した後は、生成AIを活用する範囲を検討しましょう。特に効率化が求められる業務や、AIで代替可能な作業を洗い出すことが大切です。例えば、デザインの初期案出しや文章の下書き作成、動画の素材生成などはAIが得意とする分野です。
この際、単に効率化できるかどうかだけでなく、ビジネス全体に与えるインパクトの大きさも考慮すると良いでしょう。小規模な業務効率化にとどめるのか、それとも新しい事業モデルの創出まで見据えるのかによって、投資規模や導入方法も変わってきます。
課題と活用範囲を検討したら、最適な生成AIツールを選定します。その際は、以下のような観点にもとづいて、自社に合ったツールかを検討すると良いでしょう。
・機能:自社が求める用途に対応しているか
・精度:生成されるコンテンツの品質が十分か
・使いやすさ:従業員が直感的に操作できるか
・セキュリティ:情報漏洩リスクに対する対策があるか
・コスト:導入費用や運用費用が予算に見合っているか
・サポート体制:導入後の運用支援が整っているか
✔️関連記事:AIで解決する企画提案の壁:リサーチから伝わるビジュアル表現まで
選定したツールは、いきなり全面導入するのではなく、まずPoC(概念実証)として限定的に試験導入することが効果的とされています。実際の業務環境に近い条件でツールを活用し、費用対効果や技術的な課題を検証しましょう。
PoCで得られた知見をもとに、本格導入する範囲を見極めれば、リスクを抑えつつ効率的にAI導入を進められます。
生成AIの運用にはリスクも伴うため、ガバナンス体制を整備することが不可欠です。具体的には、データセキュリティや著作権、倫理的な課題に対応するためのガイドラインや利用ルールを策定する必要があります。
従業員に対する教育も実施し、誤用やリスクの発生を防ぐ仕組みを構築しましょう。また、AI導入プロジェクトリーダーやデータ責任者といった役割を明確にすることで、意思決定や運用がスムーズに進む場合もあります。
生成AIは導入して終わりではなく、継続的な運用・評価・改善が求められます。定期的にKPIをチェックし、導入時に設定した目標とのギャップを確認しましょう。
さらに、使用者からのフィードバックを収集し、ツールの適用範囲を広げたり、運用ルールを改善したりすることも重要です。従業員のAIリテラシー向上を図ることで、より効果的にツールを活用できるようになります。
生成AIはクリエイティブ制作の効率化や表現の幅を広げる一方で、導入や活用に際していくつかのリスクや課題も存在します。
著作権や倫理的な問題、コンテンツ品質のばらつき、社会的な影響などを軽視すると、思わぬトラブルや企業ブランドの毀損につながりかねません。
ここでは、クリエイティブ制作に生成AIを活用する際に注意すべき代表的な課題を整理します。
✔️関連記事:
・画像生成AI時代のクリエイティブ最前線 第1回:テクノロジーがもたらすクリエイティブ革命と法的リスク
・知っておきたい法的知識と、想定すべきトラブルリスク:実際にはどう活用できる?画像生成AI③
・安心・安全に、AIをクリエイティブプロセスに組み込むには:実際にはどう活用できる?画像生成AI④
生成AIの活用で課題の一つとなるのが著作権侵害です。生成された画像や映像が既存の著作物に類似している場合、「依拠性」と「類似性」が認められれば著作権侵害に該当する可能性があります。特に、既存の作品に似せるようなプロンプトを入力して、元の作品を思わせるコンテンツが生成されたような場合はリスクが高まります。
また、意図せず生成物が特定の作品と酷似した場合、偶然の一致であると証明することは難しく、商用利用におけるトラブルにつながるおそれがあります。安全に利用するためには、著作権侵害の事例や注意点などを正しく理解し、生成AIツール使用者のリテラシーを高めることが求められます。
生成AIの作品に対しては「人間が生み出したものではない」という違和感を抱く人も少なくありません。また、AIを活用するビジネスモデルに対して、社会から批判的な意見や反発が起こることもあります。
そのため、透明性を確保し、どのようにAIを利用したかを明示することが、時に重要となります。AIを利用していることを隠すと、炎上や信頼低下につながるリスクが高まる場合があります。法的リスクだけでなく、倫理的な問題も踏まえた利用姿勢が企業に求められています。
生成AIは、実在する人物や出来事をもとにした偽の画像や動画を簡単に作り出すことができます。この特性は、悪意を持って利用されると社会的混乱を引き起こします。特にディープフェイク技術は、フェイクニュースや政治的プロパガンダの拡散に利用されるケースが懸念されています。
さらに、なりすましや詐欺といった犯罪に悪用される危険性もあります。信頼性の高い情報と偽情報を見分けるのはますます難しくなっており、生成AIを使う側には責任ある活用が求められます。企業はフェイク情報拡散の加担者とならないよう、生成物の用途や発信方法に十分な注意を払う必要があります。
生成AIによるコンテンツは、常に高品質とは限りません。人物の手の形が不自然であったり、建築物の形状が現実の構造と合わなかったりするなど、細部に違和感が生じるケースは少なくありません。
また、現実世界との整合性が取れていない表現がそのまま公開されると、企業やブランドの信頼を損なう可能性があります。そのため、生成結果をそのまま使うのではなく、人間による確認や修正を必ず経ることが重要です。AIはあくまで発想や効率化を補助する存在であり、品質管理を人間が担う体制が必要です。
生成AIを利用する際には、入力データが学習に利用される可能性を意識する必要があります。入力した情報に個人情報や機密情報が含まれる場合、それが意図せず生成結果に反映されるリスクがあります。
万が一、生成物に疑わしい個人情報が含まれると、プライバシー侵害や情報漏洩の問題に発展しかねません。安全な活用のためには、入力データの扱いに慎重さが求められ、特に外部サービスを利用する際にはプライバシーポリシーや利用規約の確認が欠かせません。
生成AIは学習データをもとにアウトプットを行うため、データに含まれるバイアスや偏見が結果に反映されることがあります。例えば、性別や人種に偏った人物像を生成する、差別的な表現を含んだテキストを出力するなどの問題が発生する可能性があります。
これらは誤ったまま公開すると大きな炎上につながるリスクがあります。そのため、生成されたコンテンツを精査し、公平でバランスの取れた内容になっているかを確認することが重要です。企業はチェック体制を整備し、リスク管理の一環としてAIの偏りを補正する取り組みを行う必要があります。
大規模なAIモデルの学習や運用には膨大な電力が必要であり、環境への負荷が問題視されています。特にグローバル企業では、サステナビリティへの取り組みが求められており、AIの利用に伴うエネルギー消費についても無視できません。
生成AIを活用する企業は、利用目的と環境コストのバランスを意識し、持続可能な形でAIを導入する姿勢が求められています。
今回アマナは、ブランドやマーケティング業務に携わる方々に向けた特別版ホワイトペーパー「画像・動画生成AIのブランディング活用:ブランドの世界観を強化するAI活用 ― 事例と実践ガイド(全35ページ)」 を公開。これまでの生成AIを活用したクリエイティブ制作の経験をもとに、実務に役立つ最新のトレンドやリスク対策、活用ノウハウをわかりやすくまとめています。
・画像・動画生成AIの基本概念、市場動向、利活用の最新トレンド
・主要な画像・動画生成AIツールとその特徴
・ビジネスへの導入メリットと活用事例
・著作権や倫理面でのリスクと対応策
・ブランド表現に活用する際の実践ポイント
・生成AIの可能性とリスクを体系的に理解したい方
・ブランディングや企画業務に生成AIを取り入れたい方
・生産性とクオリティの両立を求めるブランド・マーケティング責任者の方
「EVOKE」は、アマナが展開するビジュアライゼーションに特化した専門チームです。ブランドの抽象的なイメージを深く掘り下げ、具体的なビジュアルへと変換する役割を担っています。従来の制作プロセスに生成AIをいち早く導入し、ムードボードやラフイメージ制作の効率化と精度向上を実現しています。
サービスの詳細については、以下の資料で詳しくまとめております。無料でダウンロードできるので、AIを取り入れたビジュアル制作に関心のある方はぜひご覧ください。
✔️関連記事:
・生成AIを活用したクリエイティブ事例とガイドライン策定のススメ
・AIと共進化するデザインの未来|人間の創造性が持つ唯一無二の価値とは
![]()

EVOKE
EVOKE
CO-CREATING FUTURES.
amana inc.のクリエイティブチームEVOKE。
クリエイティブコラボレーションを通じて、目指す未来を描き出す。
最近は、AIを活用したクリエイティビティの拡張に力を入れている。
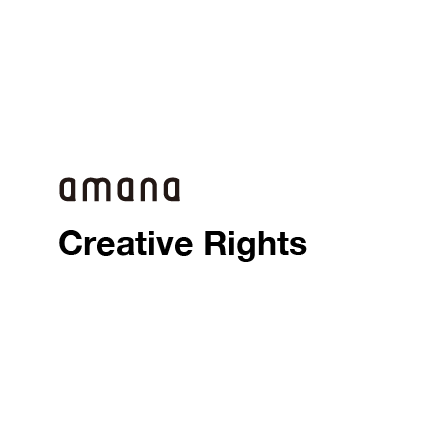
amana著作権勉強会
amana著作権勉強会
昨今、SNSやオウンドメディアなどでさまざまな情報コンテンツの発信が増えている中、それに比例してコンテンツにかかる権利トラブルのリスクも高まっています。アマナでは長年のクリエイティブ制作の中で培った著作権に関するナレッジを、セミナーコンテンツ『amana著作権勉強会』としてご提供。 さまざまなトラブル事例をもとに、情報発信を行う際、注意しなければならないポイントを解説します。

amana BRANDING
amana BRANDING
共感や信頼を通して顧客にとっての価値を高めていく「企業ブランディング」、時代に合わせてブランドを見直していく「リブランディング」、組織力をあげるための「インナーブランディング」、ブランドの魅力をショップや展示会で演出する「空間ブランディング」、地域の魅力を引き出し継続的に成長をサポートする「地域ブランディング」など、幅広いブランディングに対応しています。