vol.48
多様化する時代をサバイブする“非”王道クリエイターの新しい働き方

Photographs by Rui Ozawa
Text by Yuka Sato
いま、若手のデザイナーやクリエイターの価値観は、少し前のクリエイティブ業界では考えられなかったものになりつつあります。大手広告代理店や制作プロダクションに入社してキャリアを積む。大御所のアーティストの元で厳しい下積みを積む。これらは、これまでそして現在も「王道」と言われるキャリアでしょう。
しかしSNSやウェブの力によって、キャリアを何年も積まないと会えなかったような大御所と若手が繋がったり、権威的な世界とは全く異なるシーンで活躍するクリエイターも生まれています。
今回は、そんな新しいクリエイター像の先駆者として活動する、写真家兼アートディレクターのワタナベアニさんと株式会社れもんらいふ代表の千原徹也さん、REP ONEマネージャーの坂田大作を迎え、その是非や今後の動きについて業界の本音を語ります。
タジリケイスケ(「H」編集長/以下、タジリ):本日の「H(エイチ)」は、アマナグループREP ONEとの共同企画です。REP ONEは主にフォトグラファーのネットワークを活かしたクリエイティブ制作のサポートやプロデュース提供を行っています。今日はREP ONEマネージャーの坂田とゲストのおふたりを招いて、トークを展開していきたいと思います。

坂田大作(REP ONEマネージャー/以下、坂田):今日はお越しいただきありがとうございます。もともと私は写真の専門誌で編集者をしていました。その後、2011年に独立し、クリエイティブ・ウェブ・マガジン「SHOOTING」を立ち上げて編集長になりました。それから2014年秋にアマナでREP ONEを立ち上げて、5年くらい経ちます。
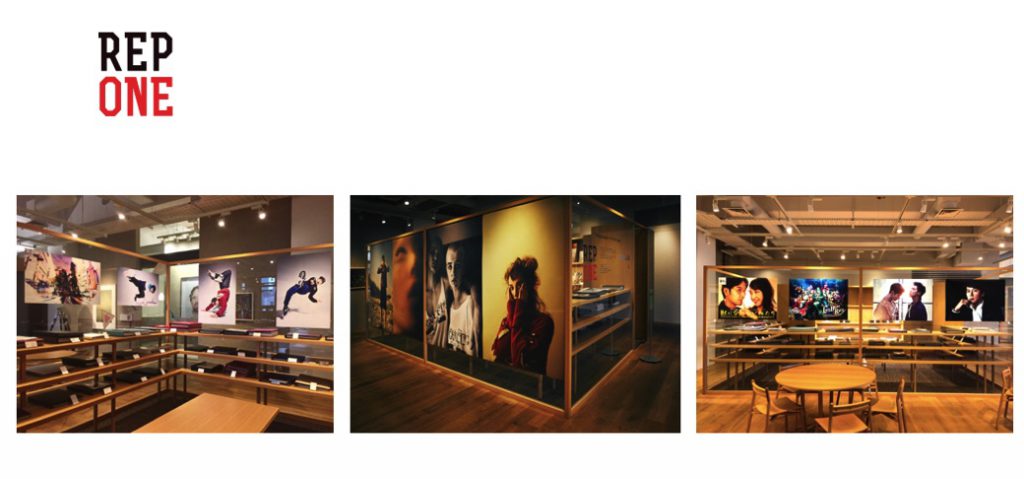
REP ONEはフォトグラファーやプロデューサーなどアマナ以外のクリエイターの方々のネットワークが強みで、社内外を繋ぐ仕事をしています。

実は千原くんとアニさんは今日が初対面だそうなんですが、今回の「“非”王道クリエイター」の企画を考えたときパッと思い浮かんだのがおふたりだったんです。おふたりのお話がみなさんの働き方のヒントになるのではないかと。
ワタナベアニ(写真家/アートディレクター/以下、ワタナベ):僕の最初のキャリアは、デザイナーとして入社した広告プロダクションです。途中からグラフィック・CM連動の企画に携わるようになり、その後CMディレクターとして独立しています。

もともと僕は高校生くらいからカメラが好きで、写真を撮っていました。ただ、会社に入ってからは「プロのカメラマンの邪魔をしてはいけない」と、カメラを全く持たない時代が20年間くらいあったんです。ところがCMからグラフィックに戻って、写真家のホンマタカシさんとヨーロッパロケに行ったときに「カメラ持って来てないの?」と言われました。邪魔になると思っていたので、「写真ってそんなに不自由なものじゃないから、好きなものを撮れば良いじゃん」って言ってくれたことがきっかけで、また写真を始めたんです。ちょうどデジタルカメラが出始めたころでしたね。
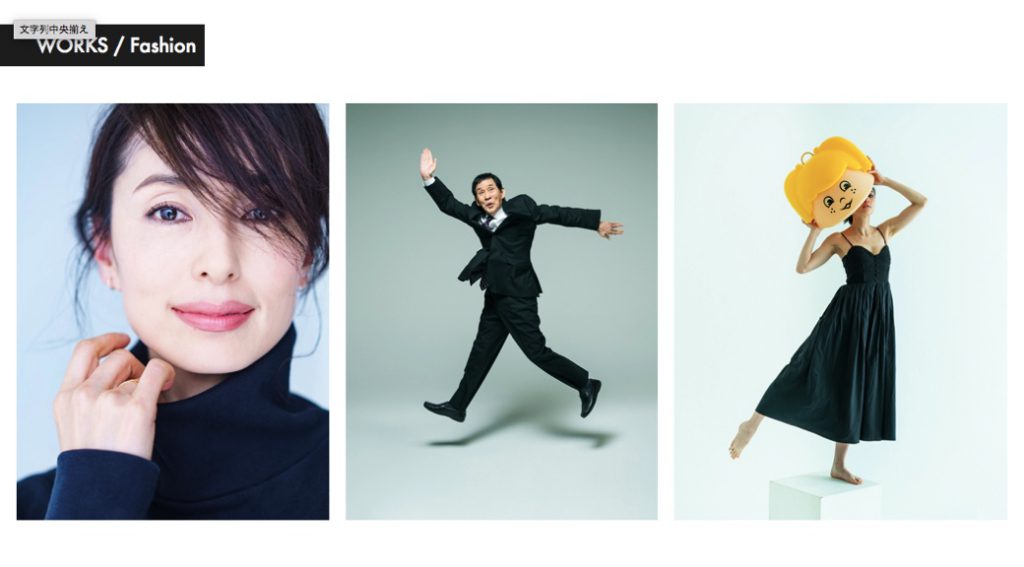
アートディレクターをしつつ、予算が少ない仕事などで少しずつ自分の写真を紛れ込ませていく。そうすると徐々に写真の仕事が来るようになりました。いまはSNSで発信をしているので、知らない人から直接依頼が来るようにもなっています。その辺のアプローチが、正統派のカメラマンやデザイナーと違うところだと思いますね。
千原徹也(アートディレクター/株式会社れもんらいふ代表/以下、千原):僕は8年前に、れもんらいふというデザイン会社を立ち上げて代表をしています。独立後、最初の仕事が女優の菊地凛子さんのウェブサイトでした。このとき凛子さんはニューヨーク在住で、ハリウッドに進出するため、海外向けのサイトが欲しいと。当時ニューヨークのクリエイターと付き合っていて、彼もチェックするから気合い入れてつくってくださいという感じでした(笑)。

相談された時点ではまだ会社員だったので固定給なわけですが、彼氏さんにそのことを話したら、「自分の仕事がそのまま金額に跳ね返ってこないのに“クリエイター”って名乗るの?」と、結構グサっと来ること言われたんです。冗談めいた感じでしたけどね(笑)。
それで、すぐに独立しようと会社を辞めて起業しました。いまはグラフィック制作でクライアントワークをやりながら、「KISS, TOKYO(キストーキョー)」というプロジェクトやサザンオールスターズファンのアーティストを集めたイベントなど、自発的な企画をひとつのアイデンティティとしてやっています。

タジリ:ではここから本題に移っていきたいと思います。はじめのテーマは「ひとつの肩書きに縛られないキャリア」。アニさんも千原さんも、特定の肩書に縛られずいろんな領域で活動していますよね。どんな背景でいまのような働き方になったのでしょうか。
千原:クライアントワークをやっていると、相当気を張っていないと平気で周りに流されちゃう面があります。好きじゃないものを「好き」って言ってしまったり、本当はニューヨークに全く興味ないのに「ニューヨークにオフィスをつくろうと思ってるんです」とか(笑)。だからいかに「好きなこと」に忠実にいるかを大切にしています。
ワタナベ:外から見ても「千原さん、サザン好きなんだね」と見え方がはっきりしてくると良い面がありますよね。興味ないバンドのイベントをやってくれって言われても、嫌でしょう?
千原:そうですね。世間的には、いまどきのアーティストのイベントをやったほうが格好良いかもしれない。でもそうじゃなくて、「サザンが好きなんだよ」ってところをぶらさない。その辺が意外と難しいんですけどね。
ワタナベ:大きいクライアントの仕事をして目立つ、みたいなことは一側面として意味があるかもしれない。でも同時に、パラレルキャリアでも、完全にフリーでなくても良いから、自分のなかの「好き」に嘘つかずに何かをやることが重要だと思うんですよね。
坂田:グラフィック業界の王道というか理想は、例えばグローバル展開する大規模な広告を手掛けるみたいなものがありますが、千原さんはデザイン塾の塾長をやったり、イベントをやったり、どんどん肩書きが広がっているというか、外れていっている気がします。なぜそうした道に進んでいるんでしょうか?

千原:僕にはアートディレクションという軸がしっかりあるからこそ、DJやったり、イベントを仕掛けたり、いろいろなジャンルに手を出せるんだと思います。
ワタナベ:あと、千原さんはなんか楽しそうに見えるよね。この業界は“ブラック”と言われてしまうような働き方だけれども、嫌だったら辞めればいいし、好きだからやっている、というのが前提かなと。
僕も夜、ロケから帰ってきてデータを確認した後、クラブに行ってまた写真を撮ったりしているんです。「あー今日の仕事疲れた」とか思いながら。写真を撮ることが苦行じゃないから仕事にしているわけで、そもそも写真を「仕事」と思ってしまうとできない部分があるかもしれません。
タジリ:おふたりとも、いまでは「やりたいこと」に注力できていると思いますが、活動を始められた当時はそんなことも言っていられなかったかと思います。でも最終的には、自分のやりたい仕事をできている。どうやったら好きなことが仕事になり、やりたい案件を手掛けられるようになるのでしょうか?
千原:ひとつは、自分のやっていることを発表することです。依頼をもらうには、その人の「個性」が分からないといけません。僕自身、凛子さんのウェブサイトの仕事をやったときは自分の個性をはっきりと把握できていませんでした。でも、分からないながらも「自分の感性を100パーセント出してやろう」とだけ決めた。モードな写真なのに絵を描いたり、手書きで文字を書いたりしたんです。
それが当時の『VOGUE JAPAN』の編集長の目に留まって、「こういう写真に絵を描くデザインやってよ」と依頼が来たんです。だんだんそれが「千原くんっぽい」「れもんらいふ感ってこういうことだよね」と言われるようになっていきました。

ワタナベ:個性は自分で決めるより、人に言われて分かることも多いですよね。
千原:そうですね。だから個展をやったり、発信したり「見てもらう場」をつくることが重要です。クライアント業務のなかで「自分」を発表できればそれが良いですが、なかなかそれは難しいと思うので。
ワタナベ:僕は「note」というコンテンツプラットフォームで発信をしています。写真もあればダジャレもある。それまでFacebookで自分の感じたこととかを書いていたけれど、それってある意味、無理やり読んでもらっている状態。だけどnoteは、お金を払ってまで読んでくれる人がいる。それは僕のなかでは発見でしたね。
発信するメリットは、仕事を頼まれるときにブレがなくなってくること。仕事を頼む側は事前に僕のnoteを読んで「こういう仕事はやってくれないだろうな」というのをカットできるし、「こういうことを考えているんだ」って事前に知ってもらうことができる。なので、条件の良い仕事が来るようになりました。

坂田:自ら発信して見てもらうことで、“前提条件”を絞っていくことができるんですね。
坂田:今日のテーマには「“非”王道」というキーワードが入っています。これまでは、東京アートディレクターズクラブのADC賞というような、広告や写真の世界における大きな賞を取ってキャリアアップしていくというある種の「王道」がありました。いまもそういった賞の権威性はありますが、既存のルートから入らないタイプのキャリアについて、どう考えていますか?
ワタナベ:いまの若手クリエイターはキャリアを築くスピード感がこれまでとは全く違うと思います。「寿司職人が10年修行するなんて馬鹿馬鹿しい」という人もいるけど、それと同じ感覚かもしれない。「手っ取り早くYouTuberになって年間1億稼げないかな」とか思っている若い人がいますが、案外その方が健全なのかもしれないと思うときも。
千原:この前、22歳のデザイナー志望の子が面接に来たんです。好きなデザイナーを聞くと「吉田ユニが好きです」と。いまや吉田ユニさんの作品は『装苑』の表紙になっていたり、星野源さんのCDジャケットになっていたりして、デザイナーで知らない人はいないでしょう。ただ彼女が獲ったADC賞について聞いてみると、「それは知らない」って言うんです(笑)。つまり吉田ユニさんまでは興味を持つけど、そこから先のデザイン業界についてはあまり知らない。そういうことが起きています。

ワタナベ:知らないというか興味がない、ということなのかもしれませんね。これまでは序列がはっきりしていました。巨匠がいて、下っ端は口を聞くことも、会うこともできないのが普通。でもいまはネットで簡単に繋がれるので、「おもしろいおじさんと会ったー」みたいなノリで、平気ですごい人と飲んでいたりする。びっくりしますが、出会いもショートカットできるのがいまの時代です。
千原:いまは、昔のやり方と新しいやり方がちょうど交差しているタイミングだと思うんです。広告・デザイン業界の古い部分が、分かりやすく浮き彫りになったのはオリンピックのロゴ問題だと思っています。デザイン業界の古い体制ややり方が一般の人たちに刺さらず、批判された部分もあると思います。
タジリ:次はおふたりの作品を紹介いただきながら「表現の本質」について考えていきたいと思いますが、千原さんはまさに、オリンピックのロゴ問題がきっかけで始めたプロジェクトがあると聞いています。
千原:そうですね。「KISS, TOKYO」というプロジェクトです。僕はあの問題が起きたとき「佐野研二郎さんほどデザイナーとして有名な人が、こんなに叩かれて良いのか?」と思ったんです。デザインの仕事をしていて、デザインが重要視されてないなと感じていたタイミングだったということも相まって、グラフィックデザイン業界の将来に漠然と不安を覚えました。
そこで、「I♥NY」のようにみんなの気持ちがひとつになるようなグラフィックデザインをつくれないかと思ったんです。80年代のニューヨークは不況で、スラム街が存在するような状態でした。そんなときにニューヨーク市民がまず自分たちの街を好きにならないとダメだよね、ということで「I♥NY」のキャンペーンが始まったと言われています。
「I♥NY」のハートマークのところって、「LOVE」とは書いてないけど「LOVE」って読めますよね。それをキスマークにしたのが「KISS, TOKYO」です。

日本にはもうすぐ東京オリンピックがやってくるので、市民が一体になるシンボルを「民間で」つくらないといけないと思ったんです。まずは、有名な方から無名な方まで「KISS, TOKYO」のTシャツを着てもらって撮影することから始めました。あくまで個人のプロジェクトだから、「千原が広めたいものに賛同してくれたら出てね」という形です。これまでに各業界の有名人の方々80人くらいが撮影に協力してしました。それもギャラはキストーキョーのTシャツだけです。

撮影した写真は自費出版でフリーペーパーにして、渋谷をはじめとした都内のカフェなど約70カ所に置いています。いまは有名人の方を多く撮っていますが、もっと一般の人が出演するようなものにしたいんです。そうすると、「あいつのお母さん出てるよ」とかってコミュニティで話題になる。そんな、一体感が生まれる活動にしたいと思っています。
タジリ:ロゴというのは企業やブランドを象徴するものとして生まれるものですが、今回は思想から派生した概念ですよね。
千原:例えばキャラクターはライセンスで広げることができるけれども、そうではなくてグラフィックデザインでどれだけ企業に求められるか勝負したかったんです。最近ではFrancfrancとコラボ商品をつくったり、スキマスイッチさんの新曲のタイトルが「東京」ということでコラボしたりと、いろいろなビジネス的な展開も起きています。

ワタナベ:これがさ、すごい予算で「大手百貨店からの仕事です」とかってなると、それは「仕事」になる。また形が違ってきますよね。共感した人が参加して、それを撮ることにとても意味があると思うんです。デザイナーやアートディレクターは、こういったコンセプトからつくる・関わる何かを持つことが大切だと思います。
ワタナベ:僕は「KISS, TOKYO」と同じような感じで、「頼まれたから」ではなく「俺がやりたいから」という理由で純粋に好きなことだけをやれるのであれば、世界中で訪れた国一つひとつの写真集をつくりたいと思ったんです。それで始めたものが『GtA』です。

写真集はトートバックに入れて1〜3号セットで写真展で販売したんです。この安っぽいトートバックも写真展に来た思い出として残る。人の心にグサッと届くものがないとデジタルデータの時代では弱いと思いますし、僕は手に取るものにすることを大切にしています。
坂田:印刷物や物体としてアウトプットしたものを売って広めるという点で、千原さんと似ていますね。
ワタナベ:そうですね。クライアントワークで「印刷物を何かつくってくれ」と頼まれることとは全く別で、「コミュニケーションのために、何か印刷物をつくる」というところが共通点だと思います。
でも実際につくってみて、自分でメディアを持つことは言い訳ができなくなることなんだと感じました。ダメなとこがあったら人格攻撃されるくらいダメって言われるし、褒められたら全部僕が褒められる。クライアントワークばかりしていると、ある意味“筋力”が衰えると考えているので、自分の活動は大切にしていきたいです。

タジリ:盛り上がってきたところですが、最後に「これからあるべきクリエイター像」を考えていきたいと思います。おふたりは、自分のアイデンティティの表現として、広告案件ではないものも積極的に発信しています。そういった流れが加速していく時流のなかで、今後どのようなクリエイターが生まれていくとお考えですか。
ワタナベ:僕はね「ある“べき”」じゃなくて良いと思うんです。SNSなどによって、クリエイターが人に知られる裾野は広がってきました。でも、そこからピックアップされる人の割合は全く昔から変わっていないと思っているんですよね。
今回のテーマは“非”王道でしたが、一方で王道なキャリア、つまり老舗のプロダクションや広告代理店に入った人はある程度足切りされたことで質を担保している部分もあって、能力が高い人は多いと思います。情報もあるし、知識もあるし、経験もある。僕らは“非”王道と言いつつ、王道の重要性も知っている。そこがちょっとズルいよね(笑)。
でも僕らのような生き方やキャリアがあっても良いとか、会社を辞めて途中で転職しても良いとか、「我慢しなくても良い時代」にはなっていると思います。

タジリ:その反面、これまでは王道を通ることでデザインの世界で言われる「1mmの違い」を追求する宮大工みたいな側面があったと思います。王道を通らないまま文化が進んでいくことによるデザイン力低下などの懸念はないでしょうか?
千原:王道、“非”王道、どちらの局面に対しても寄り添わなくてはいけないと思います。王道でデザインをやっている人たちって、権威や旧来的なデザインの美しさを良しとしてつくっている部分があるから、そこは少し考え方を変える必要がありますし、“非”王道な人たちも、名作とかこれが素晴らしいんだというものをしっかり見ていくべきだと思います。
ワタナベ:いまの世界はもう、答えがひとつじゃなくなったんだと思います。例えて言うなら料亭みたいな世界と、ファミレスみたいな世界。両者は交わらないですが、どちらも正解です。昔は「日本人全員が長嶋茂雄を目指していた」時代があったけど、いまは好きなものがそれぞれ違う。それぞれの領域でプロフェッショナルがいて、クオリティの高いデザイナーがいれば良いと思います。例えば僕は、服部一成くんの優秀なデザインを見て、デザインでいくら頑張っても彼を抜けないと思っています。そういう見本がいることはとても大事です。
タジリ:今回は、それぞれのレイヤーでマルチに活躍している3人の方からクリエイティブ業界の貴重な裏話を聞くことができました。これからも「王道」と「非王道」のバランスを取りながら、好きな仕事や表現が仕事にできるような社会が広がっていけば新たなクリエイティブの形ができるのではないでしょうか。ワタナベさん、千原さん、本日はありがとうございました。
![]()