vol.12
テクノロジーで加速する、スポーツと身体拡張の未来
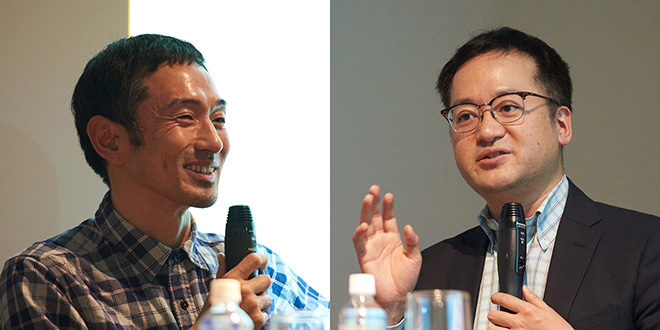
Text by Mitsuhiro Wakayama
2020年の東京オリンピックに向けてスポーツへの関心が高まる昨今、テクノロジーを導入した新たなムーブメントが企業や研究者によって推し進められています。身体拡張がもたらす次代の身体観、自動化と自在化、ビジネス展開への可能性。
最新のテクノロジーが変えつつある現代スポーツのイノベーティブな状況について、元陸上競技選手の為末大さんと人間拡張工学の第一人者である東京大学の稲見昌彦教授に語っていただきました。
世界最高峰の経験者と、世界最先端の知性はスポーツの未来をどのように描くのか。本イベントを企画した「NATURE & SCIENCE」の荒井正が聞き手役として、知的好奇心を刺激してやまないこのテーマについておふたりに伺いました。
為末大(DEPORTARE PARTNERS代表、元陸上競技選手/以下、為末):私は現在「Deportare Partners(デポルターレ・パートナーズ)」の代表を務めています。私たちの活動は、まさに今日のテーマである「スポーツ×テクノロジー」の領域でさまざまなプロジェクトを推進することです。
領域としては稲見先生のご関心ともかなり近いと思いますが、ひとつだけ違うところがあるとすれば、その先に「何を見たいのか」という点だと思います。私たちはスポーツやテクノロジーによって「いま当たり前だと思っていることが、まったく違って見える」という体験を実現したいと思っています。

江戸時代の思想家・三浦梅園は「枯れ木に花咲くを驚くより、生木に花咲くを驚け」という言葉を遺しています。意外なことに驚くよりも、そもそも私たちの日常って不思議じゃないですか、という意味ですね。私はスポーツを続けてきたなかで、「これってもしかすると不思議なことなんじゃないかな」と思うことに何度も出会いました。
そもそも「人間がある事柄を理解できる」こと自体が不思議で、関心の対象になっていきました。さらに今後はテクノロジーの発達によって、人間というものが分解され、より多角的に理解され直していくわけで、そんなことに日々ワクワクしています。
自己紹介はこれくらいにして、ここからは今日の本題に関わることをお話ししたいと思います。スポーツ業界が長く抱える問題として、「運動嫌いをどう克服させるか」というテーマがあります。「スポーツをすれば健康になれる」「継続的に運動しましょう」と呼びかけたところで一向にスポーツ人口は増えない。正論を展開しても、みんなのインセンティブにはならないわけです。
ところが、2年前に「ポケモンGO」というゲームが配信された途端、いままで歩かなかった人たちが歩き出しました。なぜ「正しい」は「楽しい」に負けるのか。これが、いまのスポーツ界が抱える大きな課題のひとつです。ある社会課題を解決するアイデアとして、すでに「正しい答え」は出ていることが多い。しかし「楽しい答え」は出ていません。
以前、松竹芸能さんから「落語を聴きにきた高齢者の人たちに、運動を促すようなプログラムを考えてほしい」と頼まれたことがありました。そのなかで運動の継続率などの統計を取りました。継続した人の特徴は「他の参加者と仲良くおしゃべりをしていた」というものでした。ここではまさに、運動の継続率が「楽しい」ことと有意に相関していたわけです。
為末:ここで観点を変えて、プロスポーツの世界を見てみましょう。平昌オリンピックでは、なかでもスピードスケートが成功したと言われています。メダル獲得につながった理由はもちろん選手が優れていたこともありますが、優秀な分析班を抱えていたからです。
水泳や自転車、スピードスケートなどの時速70〜80キロで選手が走行する競技は流体力学の応用が可能なので、世界記録が頻繁に更新されていきます。なぜかというと、まだ「最適な身体の動き」が判明していないから。逆に陸上競技のような時速30キロ程度の世界で展開するスポーツは、もうすでに解析が終わっていて動きの最適解がおおよそわかっています。
「陸上は世界記録が全然更新されない」「選手がサボっているからなんじゃないの?」なんて言われますが、そうではないんですよ(笑)。解析技術の発達によって人間のパフォーマンスの限界がほぼ明らかになった競技については、それほど頻繁に記録が更新されることはありません。
ここで問題になってくるのは、選手個人に投資するよりも、データを分析してフィードバックするシステムに投資する方が効率よく結果につながるのではないかという議論です。テクノロジーの発達でさまざまなデータが抽出可能になってきています。これによって選手の動きにおける最適解が導き出されるわけです。
しかし、それは同時に「選手個人の強化はもはやそこまで必要ないのではないか」「コーチやサイエンスチームに予算の多くを割くべきでは」という考えを一定程度正当化していきます。テクノロジーの導入によって、スポーツ界ではこのような議論も起こってきています。

パラリンピックの世界でも、テクノロジーの導入が新しいテーマを喚起しています。そのひとつに「ローテーション手術」があります。たとえば、膝の腫瘍を取り除くときに大腿部分から下を切除するケースがあります。大腿部分から下を切除すると、義足を着けたときに「膝が曲がらない」という問題が出てきます。そこで腫瘍を取り除く際、「膝だけ」を取り除いてしまって、大腿と足首を着ける方法を思いついた方がいました。その際、足首は前後ひっくり返された(ローテーションした)状態で大腿と接続します。
このローテーション手術によって、足首の関節が従来の膝関節の役割を果たします。とはいえ、患者にしてみれば太ももの先に足の裏が見える状態で着いているようにしか見えない。もともとの膝のようには動かせません。
しかしある患者の証言によると、毎日のリハビリのなかで、新しい「膝」を見つめて「動け、動け」と念じ続けると少しずつ動くようになったそうです。さらに不思議なんですが、動かせるようになった「膝」にタオルをかけて見えなくすると、途端に動かせなくなった。つまり、視覚と動作が関係していたことになります。
目の前の足首を見つめて念じることで「膝」として動かすことが可能という事実は、新しい可能性を開きます。もしかすると、VRゴーグルを装着した状態であれば、数十キロ先にある「自分の手」を動かすことも可能になるかもしれません。
見て、念じて、動かせることをもって「自分の身体」として良いのであれば、私たちの身体はいったいどこまで拡張可能になるのでしょうか。さらなるテクノロジーの発達によって「私の右手はメキシコに、左手はフランスにあって同時に動かすことができる」という状態が実現化されるかもしれません。そうなれば、私たちにとって当たり前だった「身体」のイメージが大きく覆されるでしょう。
稲見昌彦(東京大学先端科学技術研究センター教授/以下、稲見):私は東京大学の先端科学技術研究センターで、身体情報学という分野の研究を行っています。昨今は、IoTとかVRとか、世の中がどんどん情報化していくと言われています。では、自分の身体もこの情報システムの一部として捉えたときにどんな世界が開けるだろうか。このような視点で、新しい身体観や世界観を探っていくのが身体情報学という学問です。

情報化によって、私たちはどのように変わるのでしょうか。すべてが自動化してしまい、人間はただ座っているだけであらゆる物事が円滑に行われるようになっていくでしょう。でも、なんでもかんでも自動化すればいいというわけではないはずです。
たとえば、ドライビングを楽しみたい人が積極的に自動運転技術の普及を望むでしょうか? たぶん、望まないでしょう。自動運転技術は「未来のタクシー」であって、ドライビングを楽しみたい人に向けられた技術ではないわけです。同じように、自分の代わりに人型ロボットが遊園地で遊んでくれても楽しくないし、自律ロボットが自分の代わりにおいしいものを食べていても当人は嬉しくもなんともない。
つまり、自動化は「やりたくないこと」にのみ適応させられなければ、かえって悪い結果を招きます。逆に自分で楽しみたいこと、感動したいことは積極的に享受したいですよね。やりたくないことは自動化し、やりたいことだけを享受する。私たちはこれを「自在化」と呼んで、自動化と一緒に研究しています。
自在化を徹底させていくに当たり、まず人間の「できること」をどんどん拡張させていこうと考えています。さらに自在化の徹底は、言い換えれば「超人」という概念につながります。望んだことを部分的に可能にするという意味での「超人」です。

先ほど為末さんからローテーション手術のお話がありましたが、私たちは同じようなことをテクノロジーを用いてやっています。たとえば、足の指先と連動するロボットハンド「メタリム」を装着して操作するという実験で、これは「肩に足を着けた」状態です(上図)。
足の指というのは案外器用に動かせるもので、少し練習するとほとんどの被験者がロボットハンドを動かせるようになりました。これも為末さんの話とリンクするのですが、視覚と触覚の連動は身体運用において重要なファクターということもわかってきました。
私たちの身体は、手術などをしない限り改変できません。しかし「身体性=情報」は、テクノロジーによって改変可能です。つまり私たちの脳が、私たちの身体をどう捉えるかという問題については、まだまだ可能性にあふれているということです。リハビリテーションからトレーニングまで、この身体性をいかにデザインするかが重要になってきます。
この研究のポイントは、私たちがそのあたりを適切に設計しうるということです。これによって、超人的なことだけでなく、身体の遠隔操作や拡張も可能になってきます。「幽体離脱」や「合体」ということが身体性をデザインし直すことで可能になるかもしれないのです。

古くから行われてきた「みんなでおみこしを担ぐ」という行為は、言うなれば力学的な「合体」です。器からコンピューターまで人類がつくり上げてきた道具もある意味では身体の拡張です。つまり、身体性はその都度つくり変えられてきた。であれば、情報化する現在や未来のテクノロジーと人間の脳をつなぐための「新しい身体性」を設計することで、人間が新しい「身体」を獲得することも可能になると考えています。
この概念をスポーツにつなげるために、私たちは「人機一体」という言葉を使っています。人と機械が一体になる、テクノロジーを身にまとうということです。これによって新しい身体性を獲得すると同時に、やりたいことを自在に実現することが可能になります。こうした新しい身体性のうえに成り立つスポーツがあってもいいと考え、2015年に「超人スポーツ協会」を立ち上げました。

陸上競技においてランニングシューズを履くことは、いまは当たり前です。しかし、半世紀前は裸足のランナーだっていたわけです。見方によっては、ランニングシューズはある時期に登場して現在も進化している「テクノロジー」とも言えるわけです。
テクノロジーをスポーツに積極的に取り入れていくことで、ある種の障壁を乗り越え、スポーツ人口を増やすことも可能ではないかと考えています。厚生労働省の統計によれば、全人口の7割以上が「スポーツに興味がない、やらない」と回答しているそうです。こういった状況も、従来のようなアスリート的な身体を前提にしないスポーツを開発することで打破できるかもしれません。
超人スポーツ協会が取り組む新しいスポーツの開発について、いくつか事例を紹介します。まずは、岩手県発のご当地スポーツ「ロックハンドバトル」です。ロックとハンドで「岩手」という、非常にベタなネーミングなんですが(笑)。これは利き腕に巨大な「腕」を装着して戦うスポーツです。
その他にも、現在までさまざまな超人スポーツが考案されています。VRを使った「HADO(ハドー)」は最近徐々に知名度を上げてきていますし、「バブルジャンパー」はスタートアップにも成功しています。

「超人スポーツハッカソン」と題したスポーツクリエイションイベントでは、横浜DeNAベイスターズさんにも協力していただき、「超☆野球」という新しい野球の開発に取り組みました。人工筋肉を使って速くバットが振れないか、機械の「第三の腕」を使って速球が投げられないかなど、さまざまな試みがありました。

こういった既存のスポーツの拡張・リデザインがある一方で、種類を増やしていくこともしています。たとえば「スライドリフト」は、ドリフトができる電動車いすを使ったスポーツです。車いすは「足が悪い人の乗り物」と見られるのが一般的です。しかし、考え方によっては「格好いい二輪のパーソナルモビリティ」ですし、ドリフトなど操作性を上げれば使用の可能性が広がります。もし「格好いい乗り物」として市民権を得ると、車いすがより社会に普及するという現象も予想されます。スポーツをキーに新しい社会の常識が生まれることも十分にありえます。
タジリケイスケ(「H」編集長/以下、タジリ):為末さんは、テクノロジーと身体の融合である「超人スポーツ」の展開をどうご覧になっていますか?
為末:「超人スポーツ」のスポーツクリエイションには大きな可能性を感じています。しかし一方で、まったく新しいスポーツを創り出すのは難しいとも思えます。たとえば、既存のボールを使った競技の原理はほとんどの場合「陣取りゲーム」です。野球は例外的ですが、サッカーもラグビーもバスケットボールも、要領としては同じです。
スポーツクリエイションにおいて重要なことは、私たちが抱いてしまった固定観念、つまりスポーツが持つ原理をいかにテクノロジーで表現していくかということです。また、テクノロジーが入った「スポーツ」ってそもそも何なのか、それは果たして「スポーツ」と呼べるのか、という議論も活発になるでしょう。超人スポーツの普及は、このふたつの議論を深化させていくと思います。
超人スポーツは今後、eスポーツとも連動していくと思います。そうして生まれた新たなスポーツのなかから、スマッシュヒットする種目がいずれ出てくるのではないでしょうか。近現代のスポーツ業界が積み残した課題のひとつに「リーグがローカルから離れられなかった」という問題があります。サッカーのリーガ・エスパニョーラやセリエA、野球のMLBに至るまで、これらはすべて「ローカル」なものです。ある地域に移住して、リーグに加入しなければプレーできないわけです。
しかし、テクノロジーは「香港にいるプレーヤーとブラジルにいるプレーヤーが同じチームとして、同時にプレーする」という状況を可能にするかもしれません。本当の意味で「グローバルリーグ」ができ上がるかもしれないです。超人スポーツの展開にもっとも期待するのは、この部分です。

タジリ:テクノロジーがスポーツに導入されることで豊かな可能性が拓けることは確かですが、一方で「コンペティティブの減退・無効化」のようなネガティブな影響も指摘されます。
為末:スポーツにはまる人は、多くの場合「有能感」に嬉しさを覚えた経験が大きなインセンティブになっていると思います。有能感とは、「私はこれを上手にできている」という感覚です。しかし、テクノロジーがこの「上手にできている状態」をすぐに差し出してしまっては、スポーツのおもしろみは半減してしまう。
まさにこれは稲見先生の「自動化と自在化」の話で、自分が「成長している」「できるようになった」という実感をいかにもたせられるか。単なる自動化や簡易化では喜べないので、そのあたりをうまくデザインしていく必要があります。
稲見:テクノロジーが入ればそのスポーツは公平になるかと言えば、それも違います。たとえばeスポーツの選手たちもストイックなトレーニングを積んで試合に臨んでいます。選手個人の能力も依然としてゲームの結果を左右する重要な要素になっています。テクノロジーが導入されたスポーツであっても、そのなかでやはりコンペティティブは発生するわけで、決して醍醐味が失われるということはありません。
また、スポーツの設計段階で周到に仕組みをデザインすることでコンペティティブや有能感を実感させることもできます。従来のスポーツは物理世界に強く依存しているので、「ちょっと頑張れば自分より強い相手に勝てる」という仕掛けをゲームシステムに組み込むことが容易ではありませんでした。バーチャルな世界では比較的簡単に、そのあたりのさじ加減を調整できます。
任天堂さんの「マリオカート」では「順位が下位になるとマシンの加速度が自動的にアップする」というゲームデザインが施されています。トレーニングしている人が強いという原則は温存しつつ、チャンスをつかめば技量に関係なくいい勝負になる仕組みを実装できれば、おもしろいゲーム=スポーツになるでしょう。為末さんがおっしゃったように、一から新しいスポーツを創るのは難しいでしょう。しかし、既存のスポーツに学びながら、それを延長したり改良したりすることで次代のスポーツは生まれてくると思いますね。

タジリ:「スポーツ×テクノロジー」は、今後ビジネスとどのように関係していくのでしょうか?
為末:先ほどのゲームデザインの話は、大変示唆に富むものだったと思います。スポーツをどうゲームとして優れたものにしていくかという議論がある一方で、私たちの生活自体がすでに「スポーツ的=ゲーム的」な要素を含んでいるのではないか、という問いも可能です。
たとえばSNSのサービスは、言うなれば「いいね!」の数を競う一種のスポーツと化しています。IOC(国際オリンピック委員会)がつくったある種のゲームのうえでアスリートたちが「遊んで」いるように、FacebookやInstagramもある一定のルールに則って「遊んで」いる。日常がすでにゲーム化、スポーツ化されているわけです。
日常をゲーミフィケーションしていこうという視座がある一方で、日常がすでにゲーミフィケーションされているという視座もまたあり得ます。スポーツを拡大解釈すると、日常生活や社会のあり様も違って見えるし、人間同士のつながりや競争の仕方をデザインするヒントがあるような気がしています。
たとえば最近ドローンの大会が増えてきていますが、自分のトレーニングの成果を披露する場所は今後増えていくと思います。スポーツにまつわる既存のビッグビジネスがある一方で、その脇にスポーツを核にした小さな経済がある。特に後者はビジネスモデルが確立されていないぶん、さまざまな可能性に拓かれるのではないでしょうか。
稲見:スポーツ用品産業ができたように、超人スポーツ用品産業が興るとよいなと思っています。超人スポーツの開発をこれから行っていくなかで、ルールはオープンにする一方で運営の仕方や道具のレギュレーションなどはフレキシブルにしておくことが大事だと思っています。また、既存のスポーツ競技会には「1業種1スポンサー」という了解があります。そこから外れてはいるもののスポーツに関心のある企業の方々からの援助や協力を受けて超人スポーツも展開していけるといいです。

為末:最後に皆さんにお伝えしておきたいことは、「スポーツの世界はすごそうに見えて、実は全然すごくない」ということです(笑)。今日はテクノロジーに特化したスポーツの動向についてお話ししましたが、業界全体で見ればそれはあくまでごくごく小さなムーブメントにすぎません。数年前から日常生活に導入されているテクノロジーですら、スポーツの世界には未導入という状況はざらにあります。
かたや超人スポーツのような、スポーツとしてもビジネスとしても、まだまだ伸び代のある分野も生まれています。今日のお話でスポーツ界の可能性についてお伝えできたと思うので、ぜひ今後多くの方々に参入してもらえるとありがたいです。
![]()