vol.92
共感を生む、価値創造ストーリーの作り方
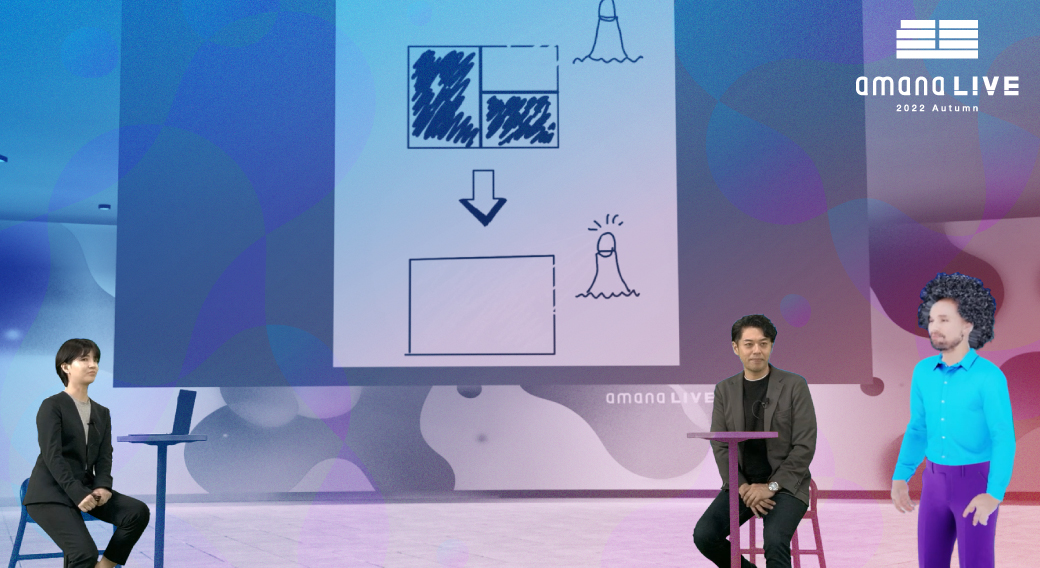
Text by Mitsuhiro Wakayama
Photo by Yushi Kaku
企業のあらゆるコミュニケーション課題に向き合い、その解決方法を探る、アマナ主催のイベント「amana LIVE 2022 Autumn」が2022年10月27日に開催されました。7つのテーマを切り口に、先進企業の方々をゲストに迎え、マーケットの今と未来をとらえたセミナーを実施。今回は、テーマ「共感を生む、価値創造ストーリーの作り方」の回を紹介します。
企業の社会的責任を果たしながら、「共感を生むストーリー」として社内外に伝播させるにはどのようなコミュニケーションが必要なのか。企業が社会貢献に取り組む意義と、グローバル視点でとらえた持続可能な企業について考えるトークセッションを開催。新聞、Webメディアなどに関わってきたPIVOTの竹下隆一郎さんを迎え、上海にてさまざまなコミュニケーション施策に関わるアマナの土井俊介が登壇、メディアプランニング、コンテンツマーケティングに携わる沼倉結菜がファシリテーターを務めました。
※本イベントはアマナの『deepLIVE™️』スタジオから配信を行いました。
(左から)PIVOTの竹下隆一郎さん、アマナの土井俊介。土井は上海からアバターとして出演しました。
竹下隆一郎(PIVOT/以下、竹下):共感という言葉はポジティブで優しくて、ふわっとしている。そんなイメージをみなさんお持ちなんじゃないでしょうか? しかし、じつは結構ハードな言葉です。まずは脱炭素にまつわるこちらの図をご覧ください。
竹下:企業の長期成長に必要な観点として「ESG(環境、社会、ガバナンス)」というものがあります。投資家・顧客・消費者・NGOがみなさんの会社のみならず、お互いに監視しあっている。これがESGの世界観です。昨今、脱炭素が叫ばれる中、消費者もこのポテトチップスのカロリーや値段、材料だけに注目しているわけではありません。その製造・供給過程でどれだけ脱炭素ができているかを気にしています。ですから自社のステークホルダーは、これまでのようにお客様や社員、株主だけというわけにはいかないんです。というより、ステークホルダーはあまりにも多岐にわたっていて、誰がステークホルダーかわからなくなっているのが現状なんです。
また、サプライチェーンの広がりも昨今の特徴だと言えます。自社が何かを調達するときに一次、二次、三次サプライヤーが存在し、しかもラディカル・トランスペアレンシー(徹底的な透明性)の時代と言われていますから、その過程の全てに責任を持たなければいけない。自社の商品を作っている海外の工場で児童労働が発覚した場合、自社がある国で不買運動が起こるということは普通にあり得ます。
竹下:みんながステークホルダーの時代に、お金やルールだけで結びつくのは不可能で、そこには「共感」が必要なんです。企業はステークホルダーを繋ぎ止めておくために、相当ちゃんとした発信をして信用を勝ち取らないといけない。そうしないと彼らは離れていきます。しかし、離れていくだけならまだマシで、場合によっては攻撃されてしまう。
そんな時代・世界観ですから、共感を呼ぶ「パーパス」や「ビジョン」という言葉が盛んに喧伝されるようになりました。一見、綺麗事のように見えますが、異なる人々を繋ぎ止めておくためにはやはり必要なんです。しかし「みんなで仲良くしましょう!」でもダメだし「金儲け大事!」でもダメ、人は離れていきます。綺麗事とリアリズムのあいだでパーパスやビジョンを作ることが肝要です。
社会や自然環境への影響を考慮すると企業の利益は減る、ゆえに「儲かった会社だけが木を植えましょう」という考え方はかつて広く共有されていました。これをオールド資本主義とするならば、現在はニュー資本主義の時代、つまり社会や環境への影響を考慮すると「利益は増す・儲かる」という時代にシフトしています。だからこそ、企業は自分たちは本気で社会問題・環境問題に取り組んでいるんだとアピールしていくべきなんです。
土井俊介(アマナ/以下、土井):たしかに、いまSDGsに本気で取り組んでいくのは大事なことですよね。しかし、社内のリソースも限られる中で、一体何から手をつけていいかわからないという企業も多いと思います。そういった企業はまず何から始めたらいいんでしょうか?
竹下:2つあります。1つは、自分たちがやっていることを掘り起こしてみること。もう1つは、不完全であることを恐れないということです。前者についていえば、企業は企業である以上、すでに何らかの社会課題を解決している・解決しようとしているはずなんですね。それは17個あるSDGsのどれかに必ず該当しているはずなんです。まずはそれを見つめ直しましょう。そして後者について。SDGsはなにも全てのゴールを1社で達成してくださいというメッセージではありません。むしろ不完全でいいのだと伝えているんです。
例えば、最近大手ファストフードチェーンはプラスチックのストローを廃止しました。それは良いことですが、それで雇用が失われている実態もあるわけです。環境保全と経済成長が両立していない。ここに矛盾が生じている。しかし、ここで重要なことは「矛盾を明らかにすること」であり、矛盾しているから不完全だと諦める必要は全くないんです。なぜなら、一企業が事業の不完全性・未達成の課題を明らかにすることで、その取り組みを別の企業が助けてくれるからです。ココからココまではできました、ココから先は助けてください、という役割分担の発想が必要なんです。
会場となった『deepLIVE™️』配信スタジオにて。
土井:日本企業は完璧主義体質というか、不完全なものは出したがらないですが、そういう考え方を変えていく必要があるということですね。不完全でも取り組んでみて、リアクションを受けて改善していくという姿勢が大事ですよね。
竹下:ブランドコミュニケーションを考えるうえで、3つの潮流を押さえておくことが大事だと思います。今日は特に「ウチが外化している」についてお話をします。PIVOTではプロダクト系の人材の募集をTwitterで行ったことがあります。しかも発信者は弊社所属のプロダクトマネージャーです。ふつうは求人サイトに広告を出して、人事部の人たちがそれを担ったりします。なぜ弊社がこのようなことをしたかと言えば、実際その企業で働いていると言うのがいちばんいいからです。つまり、社員が自社について発信する方が効果的かつ影響力が高い。また最近の調査によって、社員インフルエンサーのほうが芸能人よりも影響力が高い、ということが実証されています。会社公式の広告塔からではなく、社員が直接発信するという動向はいまグローバルに広がっています。
土井:これ、日本の企業にできるんですかね……。
竹下:難しいと思いますが、発想を変えた方がいいと思いますね。特に大企業ともなるとこの点には保守的です。しかし、いまや大企業とベンチャーの新卒給与は変わらない上に、後者には夢があります。ベンチャーの社員が楽しそうに自分の仕事についてツイートしている、給与も変わらないとなれば、新卒の人たちは大企業ではなくベンチャーを選ぶでしょう。ですから、業種や大小を問わず、企業は可能な限り社員に発信させたほうがいい。全員である必要はありません。社内に1人か2人でいいんです。社内にインフルエンサーを見つけてください。少なくとも採用の面では非常に効果的に機能するはずです。
会場となった『deepLIVE™️』配信スタジオにて。
沼倉結菜(アマナ/以下、沼倉):各国の文化のあいだでコミュニケーションに違いはあるのでしょうか?
竹下:かつては違いがあると言われていました。しかし、現在はユニバーサルな価値観が共有されていて、違いはなくなりつつあります。昨今、社会課題に対する立場を明確にした企業広告をたくさん目にします。これに対する日本のビジネスパーソンのよくある反応は「そういうのはグローバル企業がかっこつけてやっている、一過性のブームみたいなものでしょ?」というものです。しかしこの認識、全く間違っているんですよ。
若年層を対象にした意識調査によると、現代の若い世代も社会に対する危機感・改善したいという意思を持っていると言います。かつて60年代には、若年層の改革意欲は政治に向かいました。しかし、いまは企業に向かっているんです。政治では何も変わらないし、国や国際組織も弱体化してリーダーシップを取れずにいる。そんな中で、例えばスティーブ・ジョブズは「これは単なる携帯電話ではない。世界を変えるものだ」というメッセージを高らかに発信し、実際に世界のありようは大きく変わりました。また、日本におけるインターネットやSNSといったテクノロジーの普及は、阪神大震災やオウム真理教事件が起きた1995年や東日本大震災が起きた2011年を画期としています。つまり、社会の画期にテクノロジーが普及し、その後の社会を大きく変えているわけです。
要するに、社会を変える2つの要素ーー経済とテクノロジーをともに持っている企業という存在に期待や注目が集まるのは当然なんです。だからこそ、企業はそれに応えなくてはいけない。社会課題への応答は綺麗事でも何でもなく、世界や社会がターンアラウンドしている現在における必然なんです。
沼倉:これからの企業はどのようにして価値創造のストーリーを作っていけばいいんでしょうか? 明日からでも始められるメソッドがあればぜひ教えてください。
竹下:まずは、社会問題について社内で話すのが大事だと思いますね。例えば、Slackで時事問題を話題にしてみるとか。手段は何でもいいので、そういったことを話しやすい環境をつくるのはとても大切です。
土井:そうですよね。社内でも相当多様な価値観があるはずなので、まずはそれらを交流させ、その上で自社として発信していくべきことは何なのか考えるといいんじゃないでしょうか。
竹下:インナーコミュニケーションって社内報を作るようなイメージを持つ人がいますが、全く違いますからね。それに企業の広報は、もはや一部署が担うものではありません、現代は、社員の一人が社外の誰かにボソッとつぶやいたことがSNSを通じて拡散される時代です。それは言い換えれば、社員を取り巻くダークソーシャル(非公開なコミュニケーション)が非常に力を持つ時代であり、一人ひとりが社長であり広報担当であるとも言えます。社員が社外で何をどう発信するかわからないがゆえに、インナーコミュニケーションがとても大切になってくるわけです。
土井:日本には「飲み会で会社の愚痴を言うが、社内では不満を言わない」という文化があります。しかし、じつはその言いたいけど言いづらい不満のなかに、企業を成長させるものすごいヒントが隠されていたりする。社員が胸中をオープンにできる環境をつくり、その意見を社外向けのコミュニケーションに活用していくことが重要だと思いますね。
竹下:そしてメッセージを対外的にどう伝えるかと言えば、おすすめする形式は動画です。YouTubeやTikTokの平均視聴時間は年々増加傾向にあります。それは人々が活字ではなく、音や映像、手触り感などによって情報を得る時代にシフトしてきたことを意味しています。企業は今すぐにでもコミュニケーションを動画に切り替えるべきだと思いますね。カメラで撮ってもいいし、iPhoneでも撮ってもいい。もちろんアマナのようなビジュアルコミュニケーションのプロフェッショナルに相談するのもいいでしょう。また、動画を通して自社=自分たちとはどんな存在なのかも客観的に把握できるようになります。その上で動画に誰を出すのか、女性なのか男性なのか、アバターがいいのか、そういったさまざまな議論が生まれます。動画は単なるコミュニケーションの形式の一つではなく、自分たちを客観的に見つめ直し考える「きっかけ」でもあります。動画へのチャレンジをさまざまな企業におすすめしたいですね。
![]()
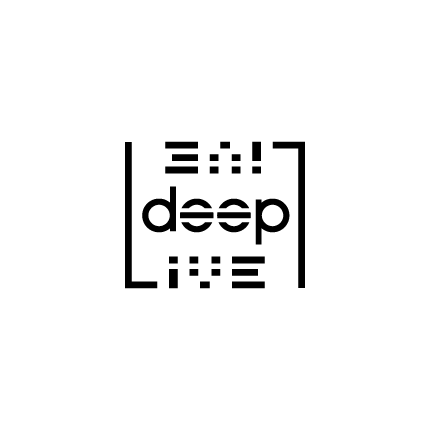
deepLIVE
deepLIVE
deepLIVEは、リアルタイムCGと最新鋭のバーチャル・プロダクションシステムを備えた自社スタジオの活⽤により、 企業やブランド固有のニーズに即した企画立案〜リアルとバーチャルの垣根を超え共感を生む深い(ディープな)体験構築が可能、新たな体験創出でデジタルコミュニケーションにおける様々な企業課題の解決をサポートします。