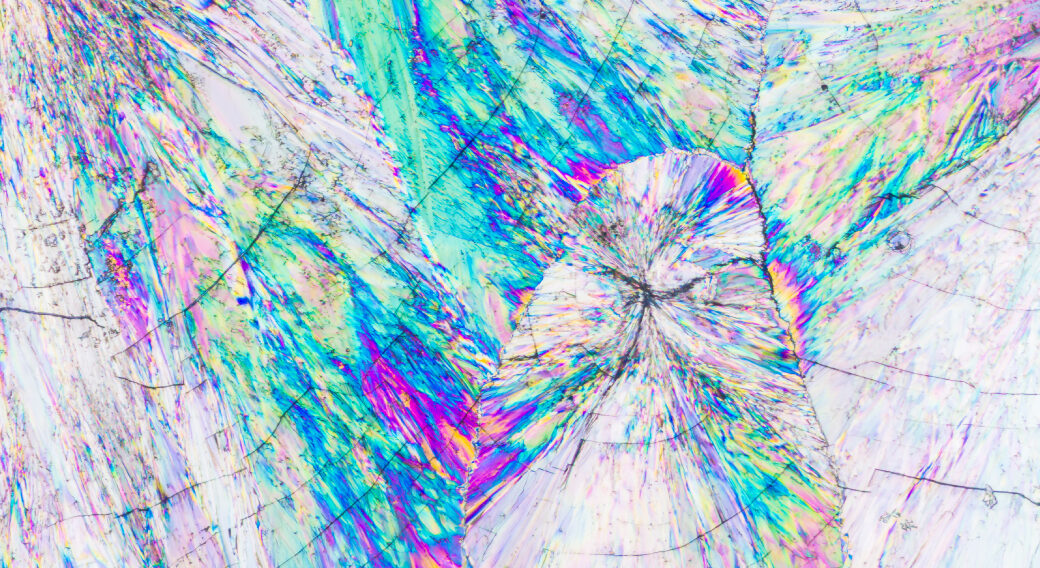
AI生成画像は、主なサービスの利用規約を読むと、提供側の企業が著作権を主張せず「利用者が自由に使って良い」というスタンスをとっているケースがほとんどです。しかし、それはあくまでも提供企業側の論理。法的あるいは実務的な観点からは、どのような捉え方が必要なのでしょうか。AI生成画像の権利に関する知見を持ち、株式会社アマナイメージズでAI機械学習向け素材提供サービスの開発にあたる望月逸平さんに、知っておきたい法的知識とトラブルリスクについて聞きました。
そもそもAI生成は、膨大なデータを収集・処理した学習用「データセット」をもとに、AIによる機械学習を経て、はじめて「AI生成モデル」として使用可能になります。したがって、そのモデルにより生成された画像の権利を考えるには、当該モデルが学習する「元になった素材」の権利までさかのぼって考える必要があるのです。
では、この「元になった素材」の権利はどう考えるべきなのでしょうか。
日本の著作権法では、著作物の種類や用途・利用方法などを考慮した上で、著作権者の利益を不当に害する場合を除いて、機械学習を含む情報解析に著作物を利用することができると明確に定められています。だからといって、「機械学習の目的であれば、許諾なしであらゆる著作物を利用できると考えるのは間違いです」と、望月さんは指摘します。
アマナイメージズの望月逸平さん。
というのは、著作権者の利益を不当に害する場合には利用が許されていないため。また、ストック素材サービスなど、データを提供する側の利用規約に反する利用方法も、契約違反となるためです。
例えば、有償で販売されているデータベースを無断で利用すれば、当然ながら著作権者の利益を害することになります。また、ストック素材も利用規約に同意して使うことが前提であり、想定されていない用途は契約違反に該当するわけです。
AIの学習のために、著作権者の利益を害する、あるいは利用規約に違反した素材が使われ、それが立証できた場合、現時点で罪に問われる可能性があるのは、その学習結果に基づくAI画像生成サービスを提供している企業ということになります。
「例えばアマナイメージズが提供している素材を無断でAIの学習に利用すれば、明らかな利用規約違反となり、そのサービス提供者への法的措置を検討するということは十分にありえます。
例えばアマナイメージズは、2015年に弊社の画像の不正利用に対する訴訟を起こしています。AI画像生成サービスに対しても、そのような不正が明らかとなれば、同じように法的責任を追求する可能性はあるわけです。今のところ、この分野での事例は幸いにありませんが」(望月さん)。
一方で、AI学習用の素材データが研究開発目的という名目で収集され、無償で公開されている場合、そのデータを収集した組織や機関の責任を追求することは難しい面があるといいます。実際に画像生成AI「Stable Diffusion」の開発元企業であるStability AIは、そのようなデータをAIの学習に利用しているとされており、先に大手ストックフォトサービスのGetty Imagesが著作権侵害で訴えを起こした際にも、その対象は素材データベースを無償提供している企業ではなく、Stability AIでした。
また、学習に使われた素材の著作権者である作家やクリエイターが、自分の作風やキャラクターそっくりのAI生成画像を商業目的で使用したユーザーを直接訴えることも考えられます。しかし、当該サービスを利用したエンドユーザーが、AIの学習素材が違法に収集されたものであると知りながら、生成された画像を悪意を持って使っているかどうかの立証は簡単ではありません。そのため、「現状では、差止請求は別として、損害賠償請求に至る対象はサービス提供企業側に留まるでしょう」というのが、望月さんの見解です。
では、サービス提供企業側の画像収集の詳細を知る術のないエンドユーザーにあたる一般企業は、どのようなAI生成画像でも安心して利用できるのでしょうか。AI生成画像をコミュニケーション活動に積極的に活用している企業はまだ限られていますが、法律的には問題なくとも、広告やPRで使用した場合にトラブルになる可能性があります。企業が無自覚に既知のイメージやキャラクターと似た画像を使った場合であっても、SNSが普及した現代ではすぐに特定され、炎上するリスクを常に抱えています。
最近では、AIの学習に使われた素材データの中に、自分の作品が含まれているかどうかをクリエイターがチェックできるようなサービスも出てきました。しかし、まだ確実な判定は難しい状況。今後の技術の進歩によって精度が上がっていく可能性はあるものの、それまではAI画像生成サービス提供企業の良識に依存する面が大きいのが事実です。
「きちんと法制度・ガイドラインなどで規制していくという動きが、ヨーロッパも含めて始まっています。日本の著作権法も、毎年改訂されて新たなトレンドに対応していますから、同じように進んで行くと期待しています」(望月さん)。
望月さんによれば、AI生成画像を企業が利用する場合に、想定されるトラブルは大きくわけて4つあるといいます。
1つ目は潜在的なリスクで、AIの学習段階で使われた画像の、肖像権、商標、キャラクターなど著作物の、利用許諾が得られている保証がないことです。現在のAI画像生成サービスに関する大きな法的論争の焦点にもなっているため、企業のコミュニケーション活動に使いにくい状況です。
2つ目は、AI生成画像が、いわゆる「トレパク」(※注1)にあたる可能性です。ランダムな画像が生成されたつもりでも、AIの学習に使われたイメージ素材とほぼ同じであったり、多少レタッチした程度のものが出力される事例がプリンストン大学などの研究者による論文で報告されており、その場合には肖像権やキャラクターの著作権に関して大きなトラブルの火種になりえます。
3つ目は、正確な描写ができないという問題。現状では、一般的なAIの学習素材データの中に手や歯のディテールまでをきちんと写したものが少ないため、画像生成AIはそういった部分の正確な描写が苦手です。生成画像の細部まで精査して、必要に応じた修正が必要となると、最初から写真を撮り下ろすほうが早くて正確ということにもなりかねません。今後の技術的なアップデートで解消されるとしても、現時点ではそういう問題もあるわけです。
そして、4つ目は、特許訴訟におけるパテント・トロール(※注2)の存在。あらかじめAIで大量の画像を生成しておき、それに似たAI生成画像をコミュニケーション活動に使用した企業に対して、賠償金を請求するというケースが起こりかねません。現在、AIで生成された画像自体には著作権が適用されない国・地域が多いですが、もしAI生成であることを隠して、あたかも自ら制作した画像だと主張された場合には、効果的に防ぐ手段がありません。一般公開されている汎用のAI画像生成サービスでは、このようなリスクも考えられるため、企業がコミュニケーション活動にAI生成画像を使う場合には、独自のものを整備するほうが安全です。
特に2つ目のトレパクは、AI生成画像に限らず、すでに現実に起こっているクリエイティブの根幹に関わる問題。それがAIによって加速してしまうことに懸念があるといいます。マンガのトレパクの例では、剽窃した側が、「幼い頃から読んでいたマンガのイメージが無意識に刷り込まれていて、似た構図やキャラクターを描いてしまった」と主張をすることがあります。それはAIが学習素材と似たイメージを生成した場合にも当てはまるため、仮にそのイメージを使用した企業に法的責任がなかったとしても、炎上トラブルによる社会的なダメージを受ける可能性は否定できません。
注1:トレパク・・・マンガやイラストなどの分野で、他の写真や作品をトレーシング(なぞり描きや模写)して、パクる(剽窃する)行為のこと。
注2:パテント・トロール・・・他者から買い取った特許権を行使して、ライセンス収益を狙う個人や団体。
すでに挙げたようなリスクがある一方、今後さらにAIの精度が高まっていけば、いつでも必要な画像を準備できたり、1テーマに対し複数の検討用バリエーションを揃えられるなど、効率的な企業コミュニケーションに不可欠な技術となっていくでしょう。そのときに備えるためには、リスクを理解したうえで、今のうちから実際に触れて研究しておくことも必要です。
そのときのポイントとして望月さんが指南するのは、「画像生成に用いたプロンプト(指示内容)や、その後の画像レタッチの履歴、作業内容などを、第三者に対して説明できるように記録・保存しておくこと」です。現状ではAIが生成した画像自体に著作権が適用されませんが、生成後に人が手を加えた程度によっては、著作物として認められる可能性があります。そのため、加工の履歴や内容を証拠として積み上げておくことで、最終的な成果物の権利に関するリスクを減らすことができるのです。
アメリカでは、AI生成された画像を用いて制作されたマンガ(グラフィックノベル)の著作権が、一度は認められたものの、画像がAI生成であることがわかり取り消されたという事例が直近にありました。しかし、その場合でも、テキストの内容・構成や画像配置は著作物として認められています。このことからも、AI生成画像を利用した制作物の権利保護には、仮に画像単体での保護が受けられないとしても、全体構成やレイアウトに関する人の関与が重要であると言えます。上記のような「作業の記録」に留意することが大切であるとわかるでしょう。
「すでにイギリスのスタートアップ企業が動画生成のAIを発表していますし、2023年は、こうしたサービスが大いに発展する年だと考えられます。
そもそも広告やPRなどの企業コミュニケーション活動は、消費者にはたらきかけたり、ブランドのファンを増やすための手段です。AI生成であるかどうかは関係なく、人の心を動かせるか、消費行動に結びつけられるかで成否を判断されるべきでしょう。受け手となる人たちが違和感を持つような使い方は避けるべきです。
一方で、すべての法的規制がクリアになってから活用を考えるのでは、他社に出遅れてしまうかもしれない。この観点から、リスクも踏まえながら、画像生成AIのアウトプットがどのようなものかという知見を今のうちに蓄えておくことが重要です。
厳密には、社内のディスカッション用資料であっても商業利用にあたるため、引用形式をとるか、画像生成AIの利用規定に抵触しないか、その他上記にあげたようなリスクを許容できるかの配慮や判断が求められます。企業として飲み込めるリスクであるか、そうでないかは、まず経営レベルで判断して社内に徹底させるべきでしょう。今後は、こうした経営レベルでのビジュアル権利の管理がますます重要になっていくと考えています」(望月さん)。
AI生成画像の活用を考える企業には、社員の著作権や肖像権に関するリテラシーを向上させ、身元不明の画像が一人歩きしてしまわないよう、ビジュアルデータの管理体制を整備することが求められていると言えるでしょう。
インタビュー・文:大谷和利
撮影:西浦乃安(amana)
AD:中村圭佑
編集:高橋沙織(amana)
【関連記事】
・画像生成AI、その主なサービスの特徴と使い方を解説:実務にはどう活用できる?画像生成AI①
・AIで作る画像をイメージに近付けるためのコツ:実務にはどう活用できる?画像生成AI②
・知っておきたい法的知識と、想定すべきトラブルリスク:実務にはどう活用できる?画像生成AI③
・安心・安全に、AIをクリエイティブプロセスに組み込むには:実務にはどう活用できる?画像生成AI④
![]()

amana著作権勉強会
amana著作権勉強会
昨今、SNSやオウンドメディアなどでさまざまな情報コンテンツの発信が増えている中、それに比例してコンテンツにかかる権利トラブルのリスクも高まっています。アマナでは長年のクリエイティブ制作の中で培った著作権に関するナレッジを、セミナーコンテンツ『amana著作権勉強会』としてご提供。 さまざまなトラブル事例をもとに、情報発信を行う際、注意しなければならないポイントを解説します。