vol.165

Text by 徳尾厚
広告などのビジュアルに使用される料理写真には、見る人が食べたくなる「シズル感」をいかに演出できるかどうかが重要です。2025年2月、アマナが玄光社から出版した撮影技法書『”おいしい瞬間”の撮影レシピ』は、アマナのシズル撮影専門チーム「hue(ヒュー)」による料理撮影のノウハウが詰め込まれています。
今回のウェビナーでは、玄光社の雑誌『コマーシャル・フォト』編集部から持田桂佑氏を招き、アマナのフォトグラファー・シズルディレクターの大手仁志と、フォトグラファーの森一樹が登壇。書籍作成の舞台裏に触れながらシズル感を引き出すポイントや、シズル表現の変遷と現在のトレンドについて解説しました。
大手仁志(アマナ/以下、大手):おいしそうな料理写真を撮るため、つまり写真にシズル感を出すために我々が日々重視しているポイントは、以下の5つです。
大手:それぞれのポイントを、本日は書籍『”おいしい瞬間”の撮影レシピ』の写真を参照しながら議論できればと。まず「立体感」は、具材が起き上がっているような演出をしたおでんの写真で見ていきましょう。
森さんもお鍋などの写真を撮ることが多くあると思いますが、立体感の演出のポイントはありますか。
撮影:鈴木孝彰(hue/フォトグラファー)
森一樹(アマナ/以下、森):お鍋やおでんを撮影すると、基本は平面になってしまうので、盛り付けで調整したのちに、ライティングで立体感を出しますね。盛り付けとライティングのどちらが欠けても、のっぺりしてしまう。
大手:盛り付けでいえば、上げ底を使って具材をお鍋の上の方に持ち上げるのが基本ですね。おいしさを表現しつつ、具材一つ一つを見せることで立体感を生み出せます。
森:全部の具材が主役ですからね。
大手:次は「ツヤ(ハイライト)」です。
撮影:加藤雅也(hue/フォトグラファー)
持田桂佑(玄光社/以下、持田):午後のティータイムを想起させるような、ほっこりとする写真ですね。
大手:カップに入っている液体だけで、ここまでドラマチックな表現をするのは、なかなか難しいですよね。僕はちょっと撮れないと思う。
森:ツヤ感というのは奥が深くて、ツヤを入れる面積や場所も、フォトグラファーそれぞれで違いがあります。
大手:作業的には、表面を揺らして、そこに上手くハイライトが入るようにして全体のトーンとかバランスを考えながら撮影している。非常に上手く入っていますね。液体を動かさないで、ハイライトをフラットな感じで入れると、こんなに魅力的じゃなくなりますよね。
森:はい。このゆらぎと湯気の関係性が、ビジュアルの肝になっていると思います。
持田:ハイライトだけでなく周囲のぼかしも効果的で、視線が液面のディテールに誘導されます。
大手:「彩り」も、料理写真では重要な要素のひとつです。
撮影:佐藤万智弥(hue/フォトグラファー)
見ていただいて分かる通り、料理に使われる食材の色だけでなく、食器や光、扱う照明も「彩り」に大きく影響します。「お弁当の三原色」などとも言いますが、茶色が多くなりがちなお弁当の中に赤、緑、黄色と鮮やかな色が入ると、よりおいしそうな画が撮れます。
「彩り」はフードスタイリスト(/フードコーディネーター)さんと話しながら決めていく要素ですが、森さんは、どう気を使っていますか。
森:差し色みたいに、どこかにポイントを感じさせるような色を入れますね。色を散りばめるのか、集めるのかなど、配置も大切です。その最適なバランスを探すために、撮影だけではなく盛り付けから気を使いますね。
大手:例えば広告であれば、商品が引き立つような差し色を入れますよね。料理だけでなく、器や背景のテーブルクロス、ランチョンマットなどで表現することもあります。
フードスタイリストやアートディレクターも含めて制作チームでコミュニケーションをとるだけではなく、クライアントにもヒアリングをしながら、色彩を決めていきます。商品をどのようなトーンで見せたいかなど、ターゲットにいかに魅力的に見せるかを意識しますね。
持田:彩りによって、写真から伝わる温度感みたいなものも変わったりしますね。
森:これは(下図)私が撮影した、火鍋の肉をスープにくぐらせている瞬間を切り取ったビジュアルです。重要なのは、「ライブ感がありつつ、かつ自然に見せる」ことです。ライブ感ばかりを重視すると画にまとまりがなくなるので、「どこにライブ感を持たせるのか」とポイントを絞ることがミソかなと思います。
撮影:森 一樹(hue/フォトグラファー)
持田:書籍のタイトルにもある「おいしい瞬間」はどこになるのか、というのがクリエイターの目線だと思います。「ライブ感」は、その瞬間を見極めるための経験や、演出するアイデアの引き出しを培ってきた人の成果なのかなと考えます。
大手:やはり経験値は必要ですよね。写真でおいしさを表現する時に、味を理解しているというのはすごく大切です。最初に試食をしたり、実際に店舗にうかがい食べてみたり、この料理のライブ感がどこにあるのかを事前に自分の身体の中に入れておきながら撮影します。
森:リアル感をどこで感じさせるかも計算してやらないと、ただただ汚くなってしまったりもします。
大手:汚いか綺麗か、その中間が狙い所ですよね。ちょっとしたことで跳ねてるスープが汚く見えたり、でもスープが跳ねる位置や量を少し調整するだけでおいしそうに見えたり。我々フォトグラファーは、そうした細かいところ、狭いところでの表現の勝負をしていますね。
大手仁志(アマナ/「hue」フォトグラファー、シズルディレクター)
大手:「空気感」は気持ちを伝える時や、食べている瞬間のおいしさとか心地よさを表現する時に、使うことが多いです。この写真を撮影したフォトグラファーの大野さんは、気持ちやイメージを乗せた「空気感」を演出するのがとても上手です。
撮影:大野咲子(hue/フォトグラファー)
森:空気感を演出する撮影技術としては、被写界深度を浅くして雰囲気をふわっとさせることが多いですね。
大手:明るめのブランチのようなイメージでもあるし、夜のしっとりとした、シチューと赤ワインを楽しむような空気感もある。まさに「おいしい瞬間」ですね。特に、鍋の縁にシチューがちらっと垂れているところ。
持田:いいポイントですね。気持ちいい汚し具合です。
大手:そうなんですよ。これは汚れではなく「シズル」になっていますね。
大手:ここからは最近のシズル写真や広告における料理写真のトレンドについて考えていきたいと思います。
持田:雑誌『コマーシャル・フォト』では様々なフォトグラファーさんの作品を掲載しているのですが、最近の料理写真では「空気感」が強調されてるものが多いですね。食べた時の気持ちだったり、食べるシチュエーションやロケーションを想像できるようなビジュアルで、消費者が身近に感じられるような写真といった印象です。
撮影:大野咲子(hue/フォトグラファー)
大手:料理写真以外でもトレンドみたいなものはありますか。
持田:他ジャンルでも同様で、いわゆるライフスタイルフォト風のビジュアルが増えています。Web媒体などは特に多い印象です。世間的に広告を邪魔者として扱うような風潮がある中で、消費者に嫌われない・寄り添うような広告が増えているのだと思います。ライティング的にも自然光で優しく撮った写真が増えましたね。
持田桂佑(玄光社/『コマーシャル・フォト』編集部)
大手:確かに、これからは「寄り添うシズル」をやらなくてはいけないのかもしれない。消費者にとって自分の世界から離れた写真であればあるほど、意図的な企業からのメッセージとして受け取られてしまいますから。
森:作り込まれた世界から、ナチュラル方向にというのは求められていますね。動きのあるシーンを再現するにも、本当に動画で撮影したものを切り出したような、作り込みを感じさせない「瞬間のシズル」がトレンドだと思います。
大手:時代によって求められる「シズル感」は変化しています。以下のハンバーグの写真は、自分が経験してきた当時のトレンドを思い返し、左から昭和、平成、令和というイメージで撮影したものです。
撮影:大手仁志(hue/フォトグラファー、シズルディレクター)
昭和の料理写真は、スタジオでしっかりとライティングし、カメラも「シノゴ」と呼ばれる大判フィルムカメラで、水平、垂直をしっかりと守って撮影していました。
平成になって、レシピ本の流行りもあり、コンパクトな35ミリフィルムカメラが主流で、アングルも比較的自由になりました。被写界深度の浅い写真も増えてきましたね。
一番右は、一昔前に流行った「映える(ばえる)」料理写真を意識しました。近年、スマートフォンの普及とともに増えたのが、俯瞰の撮影です。自然光での撮影も多くなりました。消費者が目の前にある食卓を、そのままスマホで撮ったようなイメージで撮影するのが最近のトレンドですね。
大手:例えばピザの写真。これは私自身のアーカイブから持ってきた写真を左から古い順に並べています。一番左がおおよそ20年前で、右が最近のものです。一番右はSNSを意識した実験的なカットですが、「リアルさ」を感じさせる仕上がりです。
撮影:大手仁志(hue/フォトグラファー、シズルディレクター)
油が染みた段ボールも、具材がこぼれ落ちているのも、昔はネガティブに受け止められましたが、今はリアルな表現としてポジティブに捉えられます。おそらく、消費者の感覚が変化し、トレンドが変わってきているのだと思います。
森:今は、バランスをとりすぎると消費者に寄り添っていない写真になりますね。よそ行きの姿を見せられても、消費者の共感を得ることができないのかもしれない。
森 一樹(アマナ/「hue」フォトグラファー)
大手:当時は良かった表現でも、今は消費者の気持ちにスイッチを入れることが大切なので、リアルさが求められる。それが「リアルさ」としてシズル感を生むか、汚く見えてしまうかは紙一重で、その難しい塩梅こそが昨今のトレンドといえそうです。
今後、消費者の食体験の変化とともに彼らが「リアル」と感じる要素が多様化すれば、我々はターゲットに合わせて表現を変えていくことになるでしょう。広告も万人向けから、ターゲットに合わせて配信を行うパーソナライズ型に変化しています。
私たちフォトグラファーも、Z世代とシニア世代で料理写真に求められるシズル表現の違いを語れるくらいになるよう、経験値や引き出しを増やしていくしかないと思います。
持田:2025年2月に刊行した『”おいしい瞬間”の撮影レシピ』は、雑誌『コマーシャル・フォト』で掲載した、アマナさんのシズル撮影専門チーム「hue」の協力による連載と特集に、新しいコンテンツを加えたものです。料理写真に携わる・興味を持つ方々に、テクニックや考え方、アイデアの引き出しを増やしてもらおうと作成しました。
表紙の卵かけご飯は森さんに撮っていただきました。食欲をそそる僕も大好きなビジュアルで、表紙としてもインパクトがあります。ぜひ、書店で見ていただきたいと思います。
森:本の出版にあたって表紙を撮り下ろすチャンスをいただきました。自分が好きなものを撮ろうと思って、お好み焼きと、オムライス、そして奇をてらった案として卵かけご飯の3案を出しました。卵かけご飯は私のソウルフードでもあるのですが、これは選ばれないだろうと思っていました。
撮影:森 一樹(hue/フォトグラファー)
持田:ご提案いただいた3案は、どれもよだれが出るような被写体や撮り方で、すごく迷いました。卵かけご飯は日本人にとってすごくなじみ深い料理ですし、用意しようと思えばご飯を炊いて卵を1個落とすだけ。あとは醤油をかけて作ることができる。書籍の読者が真似しやすいという点が選んだ理由の1つです。
あとは、シンプルな料理なのでシズルをどう見せるのかが個人的にも気になっていたので、ぜひ撮影で最大限のシズルを見せてくださいという形で挑戦していただきました。
森:15年くらい前、フォトグラファーになりたての頃に自分の作品として卵かけご飯を撮ったことがあるのですが、表紙を撮影するなら、15年前の自分の作品を超えようと決めたんです。1週間がかりで書店やWebで卵かけご飯のビジュアルを調べ続けました。自分の作品ですから、自ら「これのここがいいんです!」というポイントを定めて狙って写す必要がある。最終的な絵のゴール地点を見据えて、逆算してセッティングしていこうと。
撮影:森 一樹(hue/フォトグラファー)
森:撮影当日はいくつかバリエーションを撮り、持田さんも含めて「ここがおいしそうでは」とディスカッションしました。私としてはお醤油が好きなので、黄身と醤油が混ざった味感がするビジュアル(写真左)が一推しでしたが、ディスカッションの結果、黄身の濃厚さが感じられてそこに醤油がかかっているビジュアル(写真中央)に決まりました。
持田:一番左のビジュアルは、いわば卵かけご飯の完成した状態で「今から口に運ぶぞ」という気持ちが思い出される魅力的な写真でしたが、卵の黄身、ご飯つぶ、醤油という構成要素が全て際立っているビジュアルに惹かれ、中央のビジュアルを採用しました。
大手:持田さんの中では、書籍の表紙になってタイトルも乗って、店頭に並んだ時をイメージして判断されたのですね。
持田:そうですね。あとは、なるべく技術感が伝わるものにしたかったんです。書店に並び、パッと見た時に料理本だと勘違いされないようにもしたかった。
森:真ん中のビジュアルもゴールの1つとして考えていたので、フードさんには黄身が濃い卵や黄身が大きい卵を用意していただきました。味の濃厚さを感じ取れるものにしたかった。
大手:シズル撮影専門チーム「hue」を立ち上げてから、20年が経ちました。フォトグラファーは専門職であり、hueに所属するメンバーは各々が独自のトーンを持っています。彼らが自分たちの思いや積み上げてきた技術、磨いてきた感性を全部この本に詰め込みました。
同じような専門の方が見れば撮影技術が分かりますし、ともにお仕事をしてくださる方々には、撮影する私たちの思いやこだわりを感じていただける。ぜひ、皆さまにお手にとっていただければと思います。
✔️書籍の詳細はこちら:
アマナのシズル撮影専門チームhueより『“おいしい瞬間”の撮影レシピ』発売決定
✔️こちらの記事もおすすめです:
・#シズル関連記事
・シズルで企業の課題解決!シズルのすべてをお伝えするシズルチャンネル
・シズル撮影で瞬殺!ビジュアルで心を掴むプロの秘訣:シズルチャンネル
・シズル感で魅力倍増!プロが教える撮影テクニック
![]()
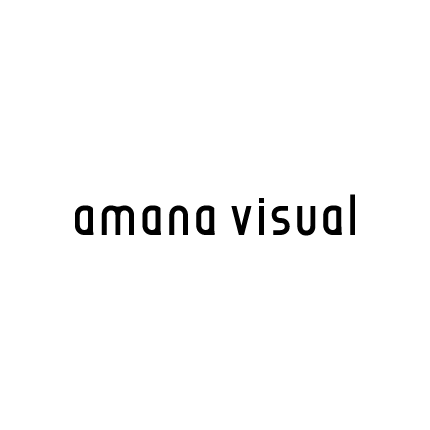
amana visual
amana visual
amana visualでは、フォトグラファー、レタッチャー、CGクリエイター、ムービーディレクターをはじめとしたビジュアル制作に携わるクリエイターのポートフォリオや、個性にフィーチャーしたコンテンツを発信中。最新事例等も更新していきます。