vol.173
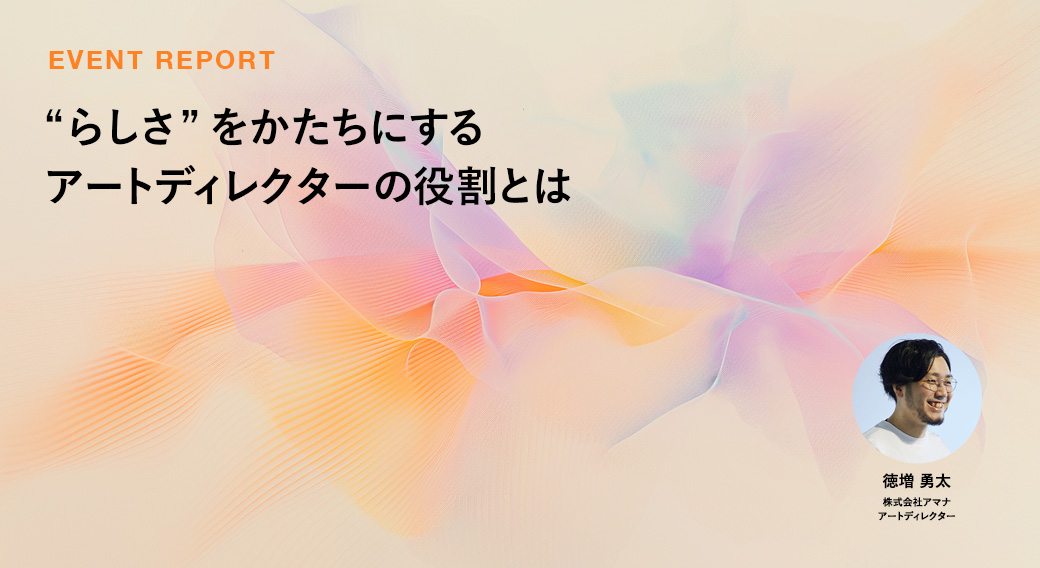
Text by 徳尾 厚
企業の価値や信念をユーザーに伝えるためのブランディングにおいて、アートディレクターはどのような役割を担うのでしょうか。背後にある企業の理念や文脈を視覚化するために、これまで積み上げてきたブランドの“らしさ”をかたちにすることも、アートディレクターの重要な仕事です。
今回のウェビナーでは、アマナのアートディレクター徳増優太が登壇。ブランドの内側にある思いや価値観をどう視覚表現に落とし込むかや、誰が扱ってもぶれないブランド運用を実現する仕組みづくりについて、事例を交えながら紹介しました。
モノやサービスがあふれる現代において、ユーザーは何を基準にブランドを選ぶのでしょうか。その判断軸となるのがブランドの「らしさ」です。見栄えの良いロゴや広告を作成するだけでなく、ビジュアルを通して、その企業・ブランドらしさを伝えていくことが大切です。
徳増はブランディングを「体験化された約束」とし、ユーザーの頭に残るブランドの印象を、どう意図的にデザインするのかがブランディングの本質だと言います。
機能的なスペックだけでは選ばれない現代、企業ブランディングでは「らしさ」をどれだけ体験としてユーザーに感じさせられるかが問われています。徳増は、企業が提供すべき価値には「機能的価値」と「心理的価値」があるとし、後者こそがファンを生む力になると語ります。
では、「らしさ」が深く体験として浸透しているブランドとは、どのようなあり方をしているのでしょうか。徳増は3つのブランドを挙げます。
たとえば無印良品は、「感じ良いくらし」を余白とともに提案するという理念を掲げ、商品から広告、空間設計、Webサイトに至るまで徹底した引き算のデザインで統一。その思想は社内にも共有され、美意識が表現に滲んでいます。
Appleでは、「人とテクノロジーの関係を創造で豊かにする」という理念が、プロダクトや店舗の空気感、操作感にまで落とし込まれています。ここでも「ユーザー中心」という軸が社員全体に徹底され、企業文化として根付いています。
スターバックスはさらに体験全体を重視し、「第三の場所」を目指す理念が、空間や音楽、照明、接客にまで表現されているブランドです。コーヒーの味ではなく、「その場所で過ごした時間そのもの」が記憶に残るという体験が、ブランドに人格を与え、選ばれる理由になっています。
成功事例に共通しているのは、「企業の思想を形にして届ける」「その思想が社内にも深く共有されていること」です。企業の内・外で一貫した世界観があるからこそ、どんな接点でも“そのブランドらしい”体験を提供できているといえます。
ブランドが持つ“らしさ”を見つけ出し、伝わるかたちに翻訳する重要な役割を果たすのが、アートディレクターです。
アートディレクターはまず、企業の現在地を丁寧に見極めた上で、「どんなブランドでありたいか」という未来像を具体的に描き出します。その理想像(ToBe)を起点に、ロゴや広告、Web、ツールなど、あらゆる接点における見え方を設計。すべての表現に一貫したトーンと意図をもたせることで、ブランドとしての世界観を築きます。
このプロセスをさらに深掘りすると、アートディレクターの仕事は大きく3つの視点に分けて捉えることができます。
・思想を見極める視点
・共有できる仕組みとして整える設計
・タッチポイントへと落とし込む実装
セミナーでは、それぞれの観点から具体的な手法や考え方が紹介されました。
徳増は「ブランドの構造は、魅力的な人の在り方にとてもよく似ている」と言います。企業の中にある思いや価値観が、やがて言葉や表現、立ち振る舞いにまで広がっていく。その内側から外側への一貫性こそが、ブランドの信頼やユーザーの記憶につながるのです。
アートディレクターは、企業やブランドが持つ価値観を外側ににじませ、視覚化する存在です。企業の中にある理念や感性を読み解き、それがどんな色で語られるべきか、どのような写真のトーンで届けるかといった判断に落とし込んでいきます。
例えば、情熱を伝えるなら赤のような力強い色合い、知性を伝えるなら青のようなクールな印象。視覚と言葉の整合性を整えることで、ブランドのらしさにはっきりとした輪郭が生まれてきます。
複数のキーワードが並ぶ場合は、それぞれの重みをどう設計するかが重要です。何を最も強く伝えるのか。どこを立たせ、どこを引き算するのか。視覚的な要素同士のバランスを調整することも、アートディレクターの役割です。
こうした翻訳の実例として徳増が紹介したのが、湖池屋のリブランディング事例です。新社長の思いを出発点に、「和の味わい」や「湖の象徴」といったコアの価値を丁寧に言語化しつつ、デザインは大胆に刷新。パッケージや広告に展開され、発売後すぐに品切れになるほどの反響を呼びました。徳増は「大胆に印象を刷新しつつも、湖の象徴や和の味わいといった“らしさ”の本質はしっかりと残されています」と評価します。
ブランドの“らしさ”を一貫して届けるには、表現だけでなくその背後にある思想までも設計されている必要があります。
徳増はその重要性を語る中で、楽天が公開しているブランドガイドラインを例に挙げ、「ロゴや色のルールだけでなく、その背景にある価値観や姿勢までが丁寧に整理されている」と話します。
楽天のガイドラインでは、ロゴの使い方や配色ルールに入る前に、企業のミッションやブランド方針といった思想の中核がまず明文化されています。なぜこのブランドが存在するのか、どのような価値を社会に届けようとしているのか。その意志が視覚的な表現にどのようにつながっているのかまでを、誰でも理解できるかたちで記述しているのです。
たとえばロゴのガイドラインでは、形や色に込めた意図を言語化した上で、その使用条件や組み合わせパターンまでが明確に示されています。トーン・オブ・ボイスや写真の方向性、ビジュアルの明度や構図など、細部に至るまで一貫性を保つための指針が徹底されているのも特徴です。
こうしたガイドラインの本質は、単なる表現ルール集ではありません。企業の思想を、誰もが扱えるかたちに整え、日々の業務やコンテンツ制作の中で迷いなく再現できるようにする「思想の運用装置」だといえます。
ブランドの思想を読み解き、目に見えるものへと翻訳するための設計・整備は、アートディレクターの仕事です。ロゴや色だけでなく、言葉、写真、トーン、空気感に至るまで“らしさ”が整っている状態は、こうした仕組みによって初めて実現されます。
ブランドの“らしさ”は、表層的なデザインだけでは成立しません。どのようなタッチポイントでも一貫した体験として伝わるように設計されていることが重要です。徳増はその実例として、Webサイト制作におけるブランド表現の落とし込み方を紹介しました。
まず出発点となるのが、ブランドのパーソナリティ設計です。ブランドをひとりの人間に見立てて、性格や価値観、空気感を言語化することで、チーム内でも共有できる人格の輪郭を描きます。
そこから導き出されるのが、表現の軸となるディレクションワードです。たとえば「誠実」「革新性」「知性」「温かみ」などの言葉を起点に、色、余白、動き、写真のトーンなどのビジュアル要素に落とし込んでいきます。これは感覚ではなく、再現性のあるデザインシステムとして設計されるものです。
たとえば「正確・信頼・構造的」といったキーワードには、整ったグリッドや均質なレイアウトを。「柔軟・受容・調整力」には、可変性のあるコンポーネントや柔らかな構造を。そして「感性・美意識」といった要素には、繊細な動きや余白、質感の表現を対応させます。
このように設計されたデザインシステムは、タッチポイントごとに表現のブレを防ぐだけでなく、誰が制作に関わっても同じ人格が語りかけてくるようなユーザー体験を叶えます。Webだけでなく、広告やツール、パッケージ、空間など、どの接点でも“らしさ”が貫かれることで、ブランドへの信頼と印象が自然に積み上がっていくのです。
広告やツール、空間、パッケージ、どのような接点でも基本的な考えは同じです。トーン、色、構造、動きなど、全てが”らしさ”を物語っているか。運用後もその印象が保たれるか。そのためには単なるルールでなく、らしさを軸にした設計思想が必要です。
アートディレクターが設計したブランドの“らしさ”が、組織全体の表現にきちんと浸透し、長く活用されるためには、個人の感覚や解釈に依存しない「再現性ある仕組み」が不可欠です。徳増はその実践例として、アマナ社内の「amana Creative Camp」のリブランディングプロジェクトを挙げます。
Creative Campは企業課題に応じてアマナグループ内のクリエイターが自発的に集まり表現の実験や学び合う、クリエイティブ人材育成プログラムです。リブランディングで制度名やビジュアル、トーン設計を見直すにあたって、「これからのアマナらしさ」をどう定義するかが大きな課題でした。徳増は、「今ある価値を守るだけではなく、これから加えていきたい姿勢や思想も含めて設計した」と振り返ります。
リブランディングではまず、「自分たちは何者で、どうありたいのか」という視点から、制度の本質を言語化。シンボルのアップデートにあたっては、活動の根幹にある「作家性」や「理念の体現」といった精神性を何よりも大切にしたといいます。Creative Campの持つ独自性や思想が視覚的にも象徴的にも伝わるように意識し、従来のトライアングルの形状もブランドの核として継承しました。
さらに、これからのCreative Campが挑戦し続ける場であるために、「既成概念を壊す」という新たな価値観を付け加えました。トライアングルの枠を超えて広がるビジュアルを用いることで、三角形に収まらない表現で越境する「創造性」を示します。また、横に添えたamana Creative Campのタイポグラフィにも独自の動きを加えることで、制度が持つ“らしさ”の幅を広げています。
そのほか、Creative Campは特定のデザイナーにしか扱えない表現に依存し、トーンのばらつきが課題でした。そこで、リブランディングでは属人性を排し、誰でも再現できるようVIを整備。ロゴのバリエーションや配色、フォント、レイヤー構造に至るまで細かくルール化し、Webサイトや資料、社内ツールなどあらゆる媒体で展開力と一貫性を両立させました。
また、ユーザーを「創造的な人材育成を課題に感じている企業の責任者」と定義し、出会いから参加、社内展開、導入・活用までの各フェーズでのタッチポイントを設計。価値の棚卸しによって導き出されたVIを、ユーザーストーリーに沿って展開したToBeイメージとして実装しています。
※「amana Creative Camp」のWebサイトは2025年8月頃のリニューアルを予定
アートディレクターは、ブランドの“らしさ”を言語とデザインの両面で可視化し、チーム全体で共有・運用できる仕組みに落とし込むことで、ブランドが迷わず未来に向かって歩めるよう旗を掲げる。思想に根ざしたVIや言語化を通じて、ユーザーとのあらゆる接点で一貫した体験を生み出すことが、アートディレクターの本質的な役割です。
そのためには、企業の内側にある理念や価値観を見極めて言語化し、言葉と視覚の両面で一貫した世界観へと翻訳することが求められます。さらに、「どのようなブランドでありたいか」というToBe像を描き、チーム全体で共有できる仕組みとして表現をシステム化することも大切です。
アマナは、ブランドの“らしさ”を出発点に、その価値を見つけ、育て、ユーザーに届けるプロセスを、企業に寄り添いながらクリエイティブとともに支えていきます。アートディレクターの役割や手法にご関心のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
こちらの記事も読まれています:
・沢井製薬|クリエイティブとメディアで企業イメージを更新
・ブランディングの視点を取り入れた機能するコーポレートサイトとは
・ビースタイルホールディングス|社内の共通言語を作るリブランディング
アマナのブランディング事例はこちらからもご覧いただけます:
アマナのブランディング事例
![]()
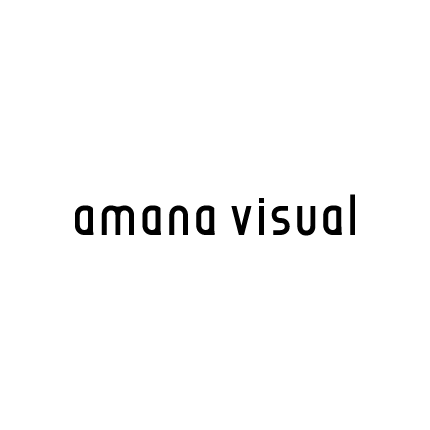
amana visual
amana visual
amana visualでは、フォトグラファー、レタッチャー、CGクリエイター、ムービーディレクターをはじめとしたビジュアル制作に携わるクリエイターのポートフォリオや、個性にフィーチャーしたコンテンツを発信中。最新事例等も更新していきます。