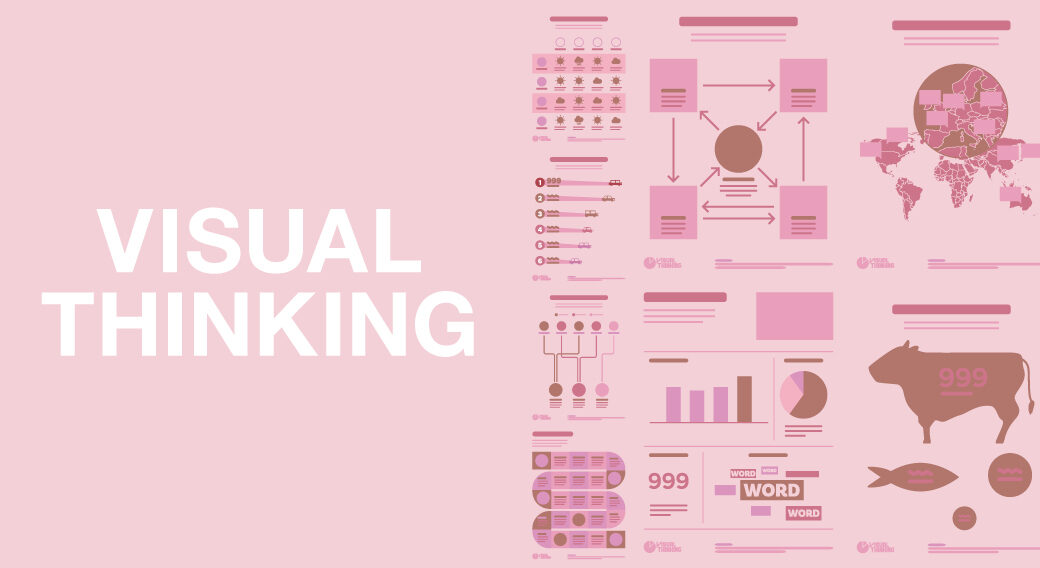
情報過多な現代において、効果的なブランドコミュニケーションを実現するためには、視覚的なプレゼンテーションの質を高めることが不可欠です。
本稿では、インフォグラフィックデザイナーの櫻田潤氏に、インフォグラフィックを活用したビジュアルコミュニケーションのノウハウとヒントについて寄稿いただきました。情報発信・コミュニケーションにおける課題を整理し、その解決策としてインフォグラフィックがどのように役立つのか、その本質に迫ります。
企業活動において、情報発信は目的ではなく手段です。社内向け、社外向け問わず、情報を発信することで、製品やサービスのことを知ってもらう、企業のスタンスや取り組みを知ってもらうなどして、購入する人が増えたり、いい人材を採用しやすくなったりすることを期待します。
でも人は、情報に触れたからとすぐにそうしたアクションに至るわけではなく、受信から行動までには段階があります。そこを意識して情報発信しないと、期待する成果につながりません。では具体的にどんなことを意識するといいのかと言うと、情報を発信する側と受け手との間にある「3つの壁」です。
1.興味の壁
2.理解の壁
3.行動の壁
情報発信において、最初の壁となるのが、興味を持ってもらえるか。目にとまるかという点です。
情報の受け手は、日々、膨大な量の情報に触れています。それだけでなく、テキスト、画像、動画、音声といろいろな形式の情報を目にし、それらと接す場所も、オンラインではSNS、メール、チャットツールなど、オフラインでも電車の中、街中など様々で、受け手はそこから気になった情報を選び取ります。これが「興味の壁」です。
次に、情報に注目してもらえたら、内容を理解してもらう必要があります。情報が届いたとしても、きちんと文脈を理解してもらえなかったら、間違った解釈が広まってしまうことになります。これが「理解の壁」です。
最後に、そこから何かしらのアクションを生むことで情報発信から成果を生みます。アクションと一口に言っても、製品の購入や採用への応募、株式の取得など大きいものもあれば、ブックマークやシェアのように長い目で成果をあげていくようなものもあります。いずれにせよ、情報発信を通じて、受け手に何かしらのアクションを求めます。これが「行動の壁」です。
このように3つの壁を乗り越えて、情報発信側が望むコミュニケーションが成立します。
ポイントは、情報を発する側が情報を投げかけるだけなのに対し、受け手側は、「興味」「理解」「行動」と3つのことを求められる点です。コミュニケーションは構造上、発信者よりも受信者の負担が大きくなります。
したがって、情報発信する際は、受け手の負担をどれだけ下げられるかが重要です。と言って、たとえば「興味」を持たれることを求めすぎると、極端な内容の情報を発信して、受け手の理解が追いつかないまま、予想外の大きな反応を生んでしまうことがあります。
また、一方でしっかりと「理解」してもらうために作り込んだものの、文字だらけだったり、堅苦しすぎたりするために、そもそもの「興味」を持ってもらえないなんてこともあります。
・興味の壁: 膨大な情報の中から、いかに興味を惹きつけ、注目を集められるか
・理解の壁: 情報を正しく理解してもらい、誤解を防ぐには
・行動の壁: 情報から具体的なアクションを促すには
こうした課題への打ち手のひとつになるのが、インフォグラフィックです。
みなさんがインフォグラフィックと聞いて、思い浮かべるのはどんなものでしょうか。情報をグラフィックでわかりやすく表現したものというイメージを持っている方が多いかと思います。ここでは、それをさらに掘り下げて見ていきます。
まず取っ掛かりとして、言葉に注目してみましょう。インフォグラフィックは、「Information」と「graphic」を組み合わせた言葉です。文字通りであれば、「情報」を「視覚的に表現」したものとなりますが、その定義だと他のグラフィック表現との違いがはっきりしません。
たとえば、ウェブ記事のバナー、プレゼン資料、飲食店のメニュー、電車内の広告なども、グラフィック要素を使って視覚的に情報を伝えています。さらに広げれば、漫画やイラスト、動画なども視覚的に情報を伝えています。身の回りに、情報をグラフィック表現で伝えるものはたくさん見つかるはずです。
したがって、情報を扱うグラフィック表現は、インフォグラフィック特有のものとは言えません。にも関わらず、インフォグラフィックだけが「情報」を強調して、頭に“インフォ”と付けるのはなぜでしょうか。
そこで今度は、一週間の天気予報を思い浮かべてみてください。月曜日は晴れ、火曜日は曇り、水曜日も曇り……といった具合に文字で並べられるよりも、週間カレンダーに天気のマークが並んでいる方がぱっと見で情報を把握できます。
同じ天気でも、東京は晴れ、千葉も晴れ、神奈川は雨……という情報を伝えるために地図上に天気マークを配置する方法もあります。
前者は一週間というタイムライン(時間軸)の中での推移を知らせるもの。後者は場所と天気の関係を知らせるものです。インフォグラフィックは、このように「時間軸」や「場所」のようになんらかの軸に基づいて、情報を整理し、それらの関係性を見てわかるようにします。
また、身近なインフォグラフィックの例として、路線図が挙げられますが、路線図も駅や路線の情報をただ並べるのではなく、ネットワークの見た目で再構築することによって、「どの路線に乗れば目的地に行けるのか」「どこで乗り換えたらいいのか」など情報の関係を把握できるグラフィックになっています。
つまり、インフォグラフィックの特徴は、情報を関係で捉え直して、提示するところにあります。
では、情報を関係で捉え直して伝えることにどんな意味があるのでしょうか。
情報を一連の流れで伝えたり、つながりを見えるようにしたり、比較できるようにして伝えたりすることで、情報の受け手にとって「理解」の負担を下げるところに大きな強みがあります。
さらには、「興味」という点においても、ビジュアルの魅力によって引っ掛かりをつくれますし、「行動」という点においても、十分な「理解」によって行動の意味づけを行った上でアクションを促せます。もっと単純に、画像としてブックマークしておきたい、シェアしたいという気持ちも掻き立てます。
・理解促進: 複雑な情報も視覚的に分かりやすく伝達
・興味喚起: 視覚的な魅力で注目を集める
・行動促進: 理解に基づくアクションを促す
インフォグラフィックは、「情報を関係で捉え直して、視覚的に伝える表現」で、わかりにくかった物事のつながりや構造をクリアにします。情報発信の中に取り入れることで、情報の受け手の負担を減らし、コミュニケーションを促進します。
今回は情報発信の視点から、インフォグラフィックがどんな課題を解決するものなのか、ひも解いていきました。今後のブランドコミュニケーションにおいて、ぜひ活用してみてください。
文:櫻田潤
こちらの記事も読まれています
・デザインは情報設計!見やすいプレゼン資料の作り方を解説
・非デザイナーでもOK!プレゼン資料を洗練させるPowerPointのデザインヒント
・ブランドを効果的に伝える!デザイナーが教えるPowerPointの技とデザインヒント
・コンテンツマーケティングに最適なビジュアルを考える
![]()

インフォグラフィック・デザイナー
櫻田 潤
インフォグラフィック・デザイナー
櫻田 潤
2010年、ウェブサイト「ビジュアルシンキング」を立ち上げ、インフォグラフィックに関する情報発信と制作を開始。2014年、NewsPicks編集部の立ち上げに参画。インフォグラフィックを用いた記事を多数、制作。2022年より、子ども新聞「NewsPicks for Kids」アートディレクター。著書に『たのしいインフォグラフィック入門』『インフォグラフィック制作ガイド』ほか。

プレゼンテーションサポートサービス
プレゼンテーションサポートサービス
プレゼンテーションサポートサービス「screen」は、展示会、商品紹介、会社説明会、営業ツール、さらに各種式典に至るまで、幅広いシーンに対応します。PowerPointにおける構成からデザイン制作、アニメーション設定、オーダーメイドの撮影や映像制作まで、ビジュアルプレゼンテーションをトータルサポートいたします。