vol.179

自分たちは何者なのか。「Visibility(可視性)」には、企業が自社を物語るナラティブも含まれます。独自のナラティブこそ企業の価値であり、競争力の源泉です。では、その企業独自のナラティブを紡ぐには、何が必要なのでしょうか。
優れたナラティブを打ち出し創造性を加速させるメソッドについて、博覧強記の独立研究者・山口周さんとアビームコンサルティング株式会社 小山元さん、アマナの山根尭がセッションしました。
小山 元(アビームコンサルティング株式会社/以下、小山):企業にイノベーションが求められる昨今ですが、多くの企業にとって、イノベーションを生む「創造性」をいかに育むかは依然として大きな課題になっています。企業と創造性の関係について、山口さんはどのようにお考えでしょうか。
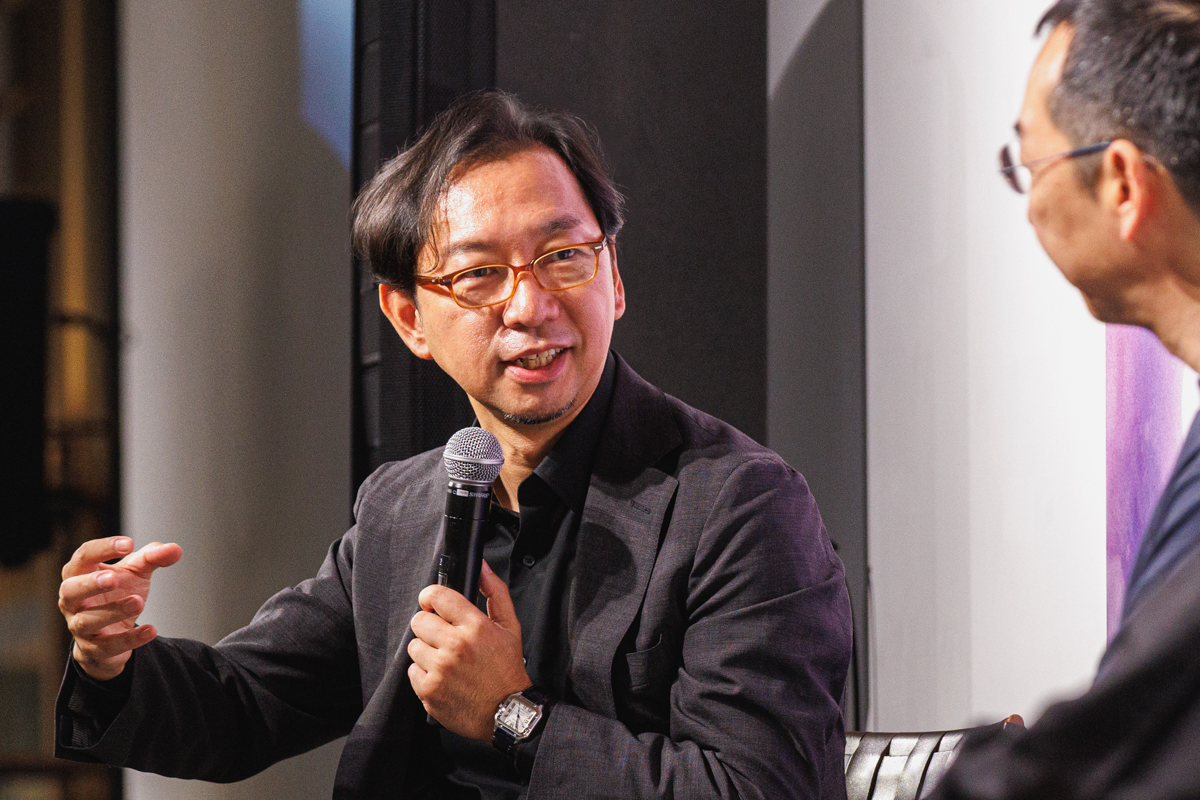
アビームコンサルティング株式会社/顧客価値戦略ユニット プリンシパル
山口 周(独立研究者/以下、山口):一人ではできないことをするのが、組織という社会集団です。であれば企業は、本来一人ではできないことが、できているはずですよね。しかし、いまの日本企業を見ると、残念ながらそうはなっていないようです。特にクリエイティビティにおいては真逆のことが起こっている。
「日本人に創造性はあると思いますか」と聞かれて、みなさんは何と答えるでしょうか。例えば、紫式部の『源氏物語』は世界最古の長編文学と知られ、清少納言の『枕草子』とともに、女性クリエイターによる古典文学の傑作と称賛されています。江戸時代までに活躍した日本のクリエイターは、挙げればキリがないほどいますし、明治から戦後にかけても、優れた才能による映画・マンガ・アニメ作品がたくさん創られた。そのように見ると、日本は、およそ千年にわたって、これほど豊かな芸術的・文化的遺産を残せた国だといえるわけです。この点においては、もっと自信を持っていい。
「個人を越えるのが組織」だというならば、このような個人による成果に匹敵するものを、果たして日本企業は生み出せているでしょうか。一人ひとりならば素晴らしいクリエイティビティを発揮する日本人は、組織になった途端、創造性をほとんど失ってしまう。なかには、素晴らしい企業もありますが、大概の会社はおよそ創造的とは言えないものしか作れない。
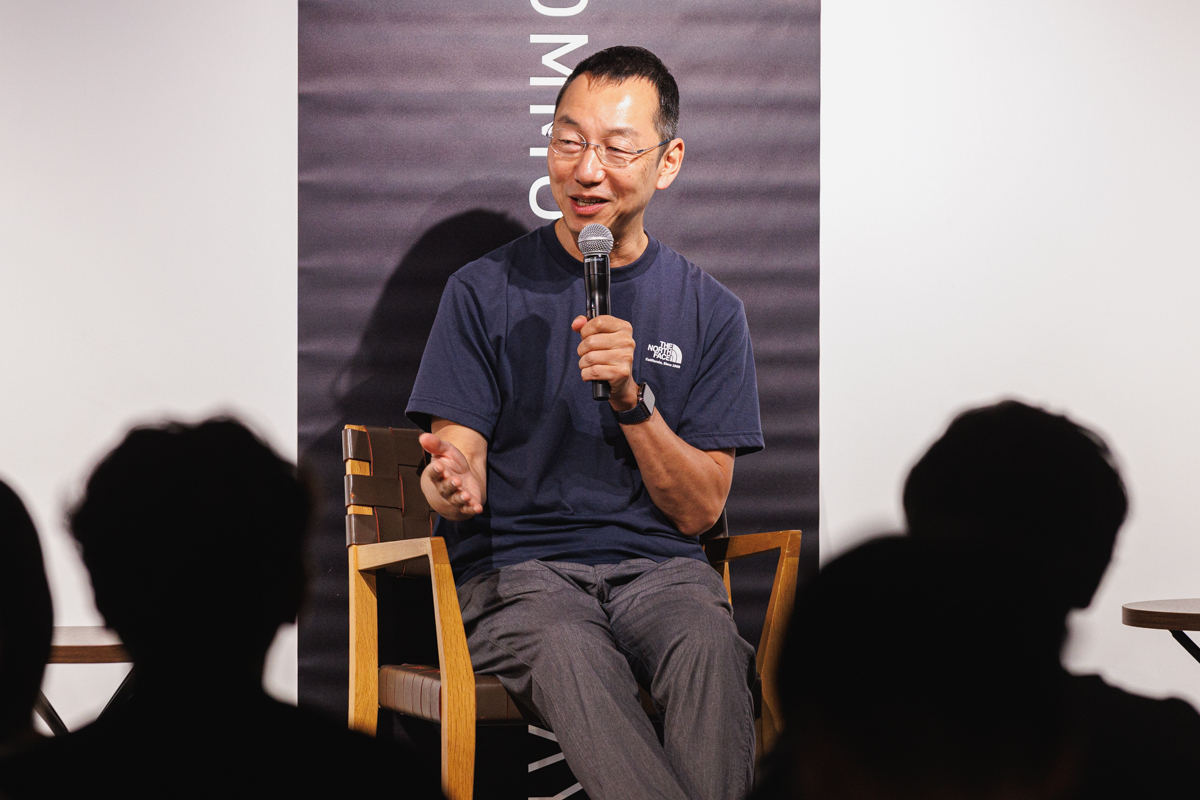
独立研究者/著作家/パブリックスピーカー
山根 尭(株式会社アマナ/以下、山根):いま山口さんがおっしゃったことは、日本企業と創造性をめぐる大きな課題の一つですね。単刀直入に伺いますが、どうすれば、企業に創造性をインストールできると思いますか?あるいは、個人の創造性を阻害しない組織づくりは、どうすれば可能になるでしょうか?
山根 尭
株式会社アマナ/クリエイティブエバンジェリスト
山口:組織は人と人が寄り集まっているわけですから、必ずコミュニケーションの様式が生まれます。社会秩序を守ろうとするモメンタムが生まれる。その秩序を作るのは、規範的な価値観(コード・オブ・コンタクト/CoC)です。その圧力・求心性がなければ、組織はまとまりを欠いてしまいます。
しかし一方、創造とは、その求心性をふりほどいて生まれた、一種の「外れ値」です。つまり、創造的な組織は、組織である以上内的秩序を守らなければ立ち行かないけれども、同時に秩序を乱す異分子も許容しなくてはいけない。もっと言えば、組織全体に変化を迫るような個人の創造性を、自ら育てなければならない。
要するに、企業が創造的であろうとすることには、大きなパラドクスがある。山根さんたち「GreatRIVER」の取り組みは、そういう意味では茨の道ですよね。
山根:たしかに、組織には、創造性のある人材を異分子として排除する力がはたらいています。それは不可避的なものかもしれません。しかし、そうであればこそ、異分子を組織の「中に迎え入れる」力があると健全だなと思ったんです。それが「GreatRIVER」の役割です。とくに、クリエイティブに携わっている人たちは、さまざまな業界業種の中にいて、彼らは多種多様な一次情報を持っているだけでなく、自分の業界を批判的に観察しています。そういう人たちを迎え入れることで、価値を発揮させられる企業は少なくないのではないかと思うんです。
関連記事:創造性人材が未来の構想力を注ぎ込む―GreatRIVERが提案する創造的企業変革
山口:クリエイティブに関わる人材が、異分子として企業の中に入り込み、長期間にわたり接点を持ち続けていく。その中で、その人独自の経験やノウハウがトランスファーされていく、ということですよね。
日本の働き方は極端で、正社員になるか、外部のコントラクターとして企業を手伝うか、実質的にはこの二つしか選択肢がありません。そして多くは前者です。社員がみんな組織の中に居続けるとCoCは揃ってきますが、新鮮な考え方は手に入りにくい。創造的であろうとするなら、社員に自社の文化に慣れ親しんでもらっては、逆に困るわけです。
その点「GreatRIVER」の取り組みは、よき攪拌作用になるのではと期待しています。
小山:個人の創造性が組織の中で活きることは、創造的企業の条件の一つですね。では、もう少しミクロな話になりますが、個人の創造性は「何」から生まれてくるのでしょうか?
山口:カリフォルニア大学の心理学者ディーン・キース・サイモントンが1999年に上梓した『Origins of Genius』(天才の起源)という本があります。彼は、モーツァルトやニュートン、エジソンといった天才たちを調べ上げ、創造性はどうやったら生まれるのか研究しました。その結論は、創造的な成果を生み出すには「大量のアウトプット」こそ最も重要である、というものでした。多くの場合、天才は多作です。例えば、バッハが生涯に作曲した楽曲の数は1,000を超えています。
ここで重要なことは、天才が生み出した大量のアウトプットの中には「大量の“駄作”が含まれている」ということです。
正規分布図を想像してみてください。横軸に作品の質の良し悪しを取り、縦軸には作品の数を取ります。アウトプットが多ければ、ベルカーブの「山」は大きくなりますね。で、この分布の右側の「外れ値」、これを我々は傑作と呼んでいます。企業活動ではイノベーションと呼ばれるでしょう。そして左側の外れ値は、埒外の駄作ということで無視しているんです。
天才とは一種の能力で、それが傑作を生み出すというナラティブを我々は想像しがちなんですが、じつはそうではない。サイモントンは「論理が逆立ちしている」と言っています。
まずアウトプットを大量に出す人がいる。すると、そのアウトプットの中から右方向に極端な外れ値が現出する。それを私たちは「才能による傑作」と再起的に理解しているんです。
エジソンもそうですね。彼は2,000ほど特許をとっていますが、その内まともなビジネスになったのは10ほどです。残りの1,990の特許は箸にも棒にもかからない、何の利益も生み出さないものでした。つまり、クリエイティビティは才能からではなく、ある種の行動様式から生まれるということです。
山根:よくわかります。一方、昨今はAIを活用することで、大量のアウトプットが生み出せますよね。アウトプット自体が大切なのか、それとも大量に経験する「プロセス」が大事なのか。そのあたりはどう思われますか。
山口:前者だと思います。アウトプットの数を確保するためにAIに頼ってもいいと思うんです。これは、「週刊少年ジャンプ」の黄金期を作った編集者の鳥嶋和彦さんの言葉ですが、編集者の成功法則は「下手な鉄砲、数打ちゃ当たる」だそうです。彼は、担当した「ドラゴンボール」の作者・鳥山明さんについて「絵はうまいが才能があったわけではない」といいます。ゆえに、大量にネームを描かせたと。プロットを書くのは鳥山さんにしかできないことですが、絵を描くのはAIでもできます。そういうふうにAIに頼るのはアリだと思いますね。
山口:天才の筆頭に上がるモーツァルトは、ケッヘル目録に登録されている曲だけでも、600を超える曲を書いています。彼は36歳で亡くなっていて、実質的な活動期間は20年くらいです。だとすれば、交響曲を含む楽曲を、年間に30曲以上書いていることになる。これは驚くべきことですよ。
彼はオーストリアの中北部にある都市ザルツブルクの生まれですが、音楽活動のために西北部の首都ウィーンに出ました。しかし、親から再三帰ってこいと言われても、彼は絶対にウィーンを離れようとはしませんでした。なぜなら、ウィーンでは最新の音楽が聴けたからです。
モーツァルトは、ウィーンを離れれば、自分の「音楽的才能」は枯渇するとしています。クリエイティブな人が大勢いて、大量のアウトプットがなされるウィーンに身を置き、パクれるものを大量に仕入れる。大量のアウトプットのための、大量のインプットの機会を彼は必要としていたんですね。
これは、AIであっても同じです。AIをいくら使っても、仮説(アジェンダ)がなければ何も生まれない。つまり、良いアウトプットを得るには、それを支える豊かなインプットの環境が必要です。
小山:アジェンダは「コンテクスト」や「ナラティブ」という言葉に置き換えることもできそうですね。そして、それらを設定する力を養うには、大量のインプットが必要だと。人を動かすナラティブとは、どのようなものだと思いますか?
山口:20世紀の大企業の多くは「優れたナラティブ」を設定することで社会をリードしてきました。
ロシアの民俗学者ウラジーミル・プロップは、民話/神話のナラティブは30の機能パーツから成り立っている、といっています。これにわかりやすく沿っているのが、テスラの創業者イーロン・マスクのナラティブです。彼は、いわば自分を主人公にした「神話」を書いている。まず彼は「敵」を設定します。敵とは、“化石燃料を使う文明”で、やがて世界に破滅をもたらす。しかし、そこにヒーローが現れた。それが自分だというわけです。そして仲間もいる。それが“あなたたち”だと。
ここで重要なポイントは、企業は「魅力的な敵を作り出せるか」ということです。
ナラティブを作るとき、多くの人が共通して嫌悪する「敵」を設定できれば、みんながその打倒のために結集し、懸命に努力するわけです。関わる人が増え、アウトプットが増えれば、そこには自ずと創造性が宿ります。
先ほど、アウトプットの量が創造性の源泉だと言いました。その量はどうやったら出せるのかといえば、これは残酷な話ですが、必要なのは「考えている時間」なんですよね。何かいいアイデアが欲しいとき、クリエイティブなリーダーが一人で考えている組織と、100人が寝る間も惜しんで考えている組織があったら、創造的なアイデアは後者から生まれる可能性が圧倒的に高い。ただ、寝る間も惜しんでやれとは言えないし、なんせサステナブルではない。ですが、みんながそれを打倒することに夢中になれるような「魅力的な敵」がいれば、寝る時間だって惜しまないでしょう。ですから、敵のデザインが非常に重要になってくるわけです。
しかし、AIは「魅力的な敵」を生み出すことはできません。AIの思考は統計的な中央値に基づきます。ですが、物語においてみんなが熱狂するのは「いままで味方だった奴が、敵だとわかった瞬間」です。
テスラのナラティブが狙ったのはまさにここです。誰もがガソリン車の恩恵を受け、経済的な豊かさを享受している、その最中で「“その車”こそ打倒すべき敵である」と叫んだわけです。でも、AIはそんなふうに敵を創造できない。「みんながそう思い込んでいること」という中央値からしか、アイデアを導き出せないからです。また、それを逆手にとって、価値観の転倒を促すような発想もすごく苦手です。
山口:AIには弱点がもう一つあります。みなさんわかりますか?それは「五感がない」ことです。見る・聞く・肌で感じるといった一次情報から、状況を先読みするということがAIにはできないんです。物事の動きは、必ずごく少数の人の“肌感覚”から始まります。ネットが動き出すのはもっと後の話で、AIはネット上に集積された二次情報を収集することしかできません。
リーダーの役割というのは、世の中の変化を先取りすることです。マジョリティが「当たり前だ」あるいは「不謹慎だ」と思っていることも批判的に見つめて、いずれ起こる価値観の変化を予見しなければいけません。
それはAIにはできない、人間にしかできないことです。既存の価値観がひっくり返って新しいビジネスが生まれている現状を思えば、これから一層必要になってくる力だと思いますね。
山根:日本の自動車メーカーは、テスラと違って、市場調査の結果としてEV開発を見送りました。両者の間にある、EV開発を「決断できる/できない」の差はどこにあるんでしょうか?
山口:やはり、ナラティブの有無でしょうね。神話のヒーローになろうとしたか否か。市場調査から出てくる結果には、マジョリティの価値観が色濃く反映されています。「ガソリン車でいいじゃないか」「今と何かが変わってしまうのは不安だ」という市場の声を得た結果、日本のメーカーは「EVの市場は無いな」と考えた。これはマーケティングの定石からいえば、当然の判断です。
市場を調査し、メジャーなニーズから満たしていく。そして徐々にマイナーなニーズも取り込んでいき、最後はフロンティアがなくなる。しかし、テスラはそのメジャーなニーズ、つまりマジョリティの価値観そのものが問題だと、逆転の発想をしたわけですね。この価値観が転倒したら、膠着した市場に、ものすごく大きなニーズが出現する。マーケティングのセオリーからすれば、非常にイレギュラーなビジネスです。
小山:本日のテーマは「Visibility」ということで、企業は顧客に何をどう見せるのか、という観点からお話を伺ってきました。最後にナラティブというところに話が及びましたが、これも「Visibility」において非常に重要なファクターですね。自分たちは何者なのか、企業が紡ぐ独自のナラティブは、その企業の価値につながります。
しかし、AIに聞いても多数派の声が返ってくるだけで、独自のナラティブは生み出せない。自分たちの内から発想されたナラティブは、企業や個人がアウトプットを積み重ねていった先に生み出されるのでしょう。今日のお話には、創造的であるためのヒントがたくさんありましたね。非常に有意義なお話でした。本日はありがとうございました。
関連記事:
アーティストの思考を取り入れることが、 これからの「アート×ビジネス」のあり方
ヤマハ発動機 | 外部人材による刺激が、企業の創造性を強固にする
![]()

GreatRIVER
GreatRIVER
澱みなき大河が、創造性を呼び起こす
Great RIVERは、目標を達成するための創造的な組織を共に創り上げるサービスです。各分野のプロフェッショナルである創造性人材が企業と一体となり、社内だけでは補えない視点や専門性、新たな視点や発想を持ち込みながらプロジェクトの基盤を支えます。